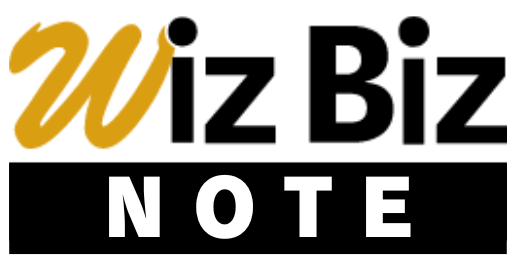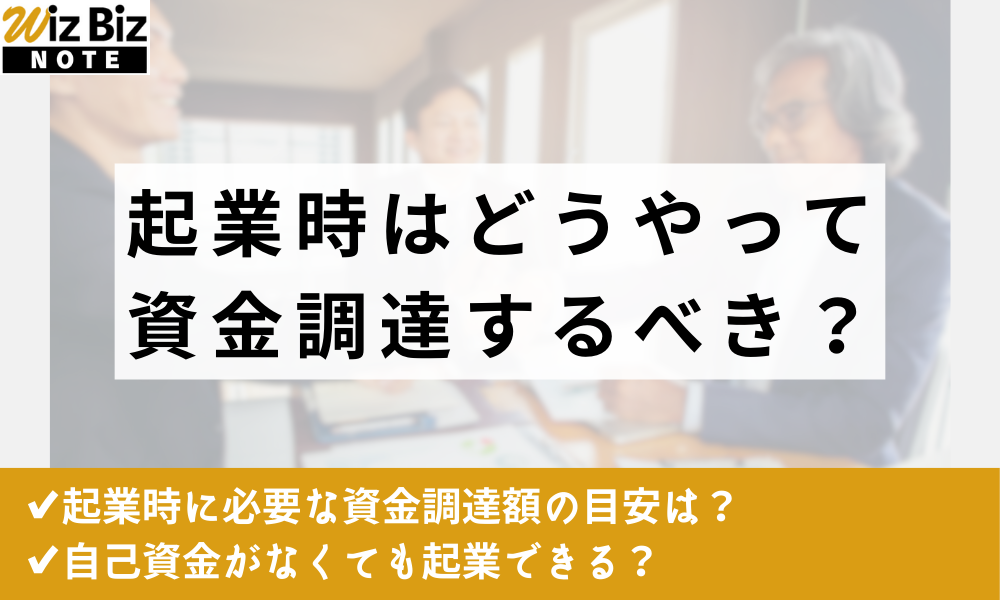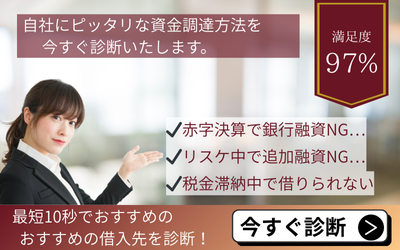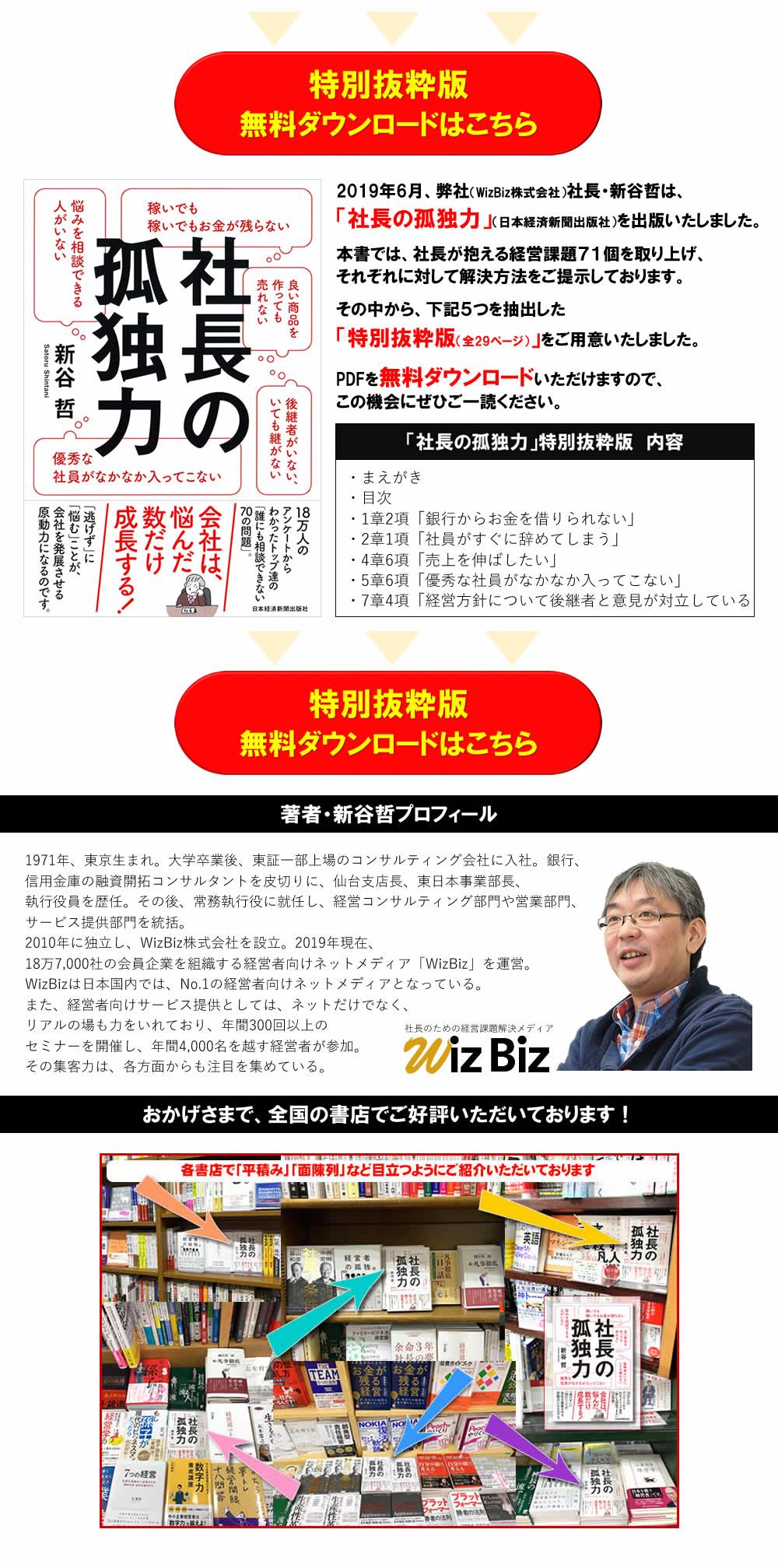起業を検討する際、資金調達をどう進めるか悩むケースも多いでしょう。
自己資金でまかなうのが理想ですが、開業時は思わぬ費用がかかることもあります。
起業時の資金調達方法には、公庫や銀行、信用金庫の制度融資、あるいは補助金や助成金など、さまざまな方法があります。
事業計画や業種に合わせ、最適な手段を選びましょう。
| まとまった金額の借入なら ビジネスローンがおすすめ! | 売掛金があるなら ファクタリングがおすすめ! |
|---|---|
AGビジネスサポート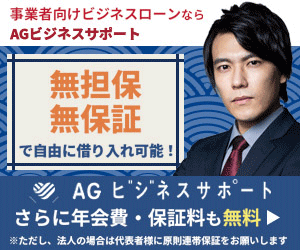 | ワイズコーポレーション |
| 迅速な審査ですぐに事業資金を融資してもらう方法 | 売掛金や請求書を買い取ってもらい現金化する方法 |
| 融資まで 最短即日 | 入金まで 最速当日中 |
| 申込〜入金 来店不要! | 申込〜入金 来店不要! |
| 融資限度額 50万円〜1,000万円 | 買取限度額 300万円〜上限なし※4 |
| 金利 年3.1%〜18.0% | 手数料 1%〜14.8% |
| 利用者※1 法人(赤字でもOK!) 個人事業主 | 利用者 法人(売掛金があればOK!) 個人事業主 |
| 必要書類※2 本人確認書類 決算書などのみ! | 必要書類 請求書 通帳などのみ! |
| 無担保無保証で借入可能!※3 | 取引先への通知なし! |
| AGビジネスサポート 公式サイトから今すぐ申込 | ワイズコーポレーション 公式サイトから今すぐ申込 |
※2:法人→代表者本人を確認する書類・決算書・その他必要に応じた書類
※2:個人事業主→本人を確認する書類・確定申告書・所定の事業内容確認書・その他必要に応じた書類
※3:原則不要。法人の場合は原則代表者が連帯保証
※4:該当しない方は要相談
貸付条件はこちら

WizBiz株式会社 代表取締役
経歴
1971年東京生まれ。大学卒業後、東証一部上場のコンサルティング会社に入社。銀行、信用金庫の融資コンサルタントを皮切りに、仙台支店長、東日本事業部長、執行役員を歴任。その後、常務執行役に就任し、経営コンサルティング部門や営業部門、サービス提供部門を統括。2010年に独立しWizBiz株式会社を設立。現在、経営者向けネットメディア「WizBiz」を運営。国内では経営者の会員登録数でNo.1のメディアとなっている。また、経営者向けサービス提供としては、ネットだけでなく、リアルの場も力をいれており、年500回以上のセミナーを開催し、4000名を越す経営者が参加。18万人の社長アンケートから1000個の悩みを回収。
著書:社長の孤独力
起業時・創業時に必要な資金調達額の目安
起業時に必要となる資金は、業種やビジネスモデル、店舗形態などによって異なります。自己資金や運転資金など、大まかな目安を知っておけば、資金ショートも防げるでしょう。
はじめに、起業時に必要となる資金や、業種別の開業資金の目安を見ていきます。
自己資金無しでも大丈夫?起業時に必要な資金の目安
起業時は、「初期費用+数ヵ月の運転資金+予備費」の合計で資金を用意しておくのが理想です。
過去、日本政策金融公庫では、創業資金に対し10%程度の自己資金を一つの目安としていましたが、その考えは正しいといえます。
必要資金の約10%を自己資金でまかなうことができれば、融資を受ける際も金融機関からの印象も良くなります。
初期費用には法人設立に必要な費用や内装工事費用、広告宣伝費用などが含まれます。家賃や人件費、仕入費など運転資金も考えておきましょう。
また、想定外のトラブルや急な支出にも対応できるように予備費も準備しておかなくてはいけません。開業時の収益は不安定になりやすいため、いざという時の余力があると心強いでしょう。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 自己資金 | 開業時の資金必要額の10%程度が目安。 10%の自己資金があると公庫や保証協会の創業融資で好感を持たれやすい |
| 初期費用 | ・法人設立費用や許認可申請費 ・広告宣伝費(チラシやHP) ・設備費(内装、家具、PC) ・物件取得費(敷金・保証金、仲介手数料) ・備品(事務用品やユニフォームなど) |
| 運転資金 | ・家賃や水道光熱費 ・人件費(給与や社会保険料) ・仕入れ費や外注費 ・通信費(電話やネット) ・広告宣伝の継続投下費用 |
| 予備費 | ・売上不足時のつなぎ ・予期せぬ出費(トラブルや機器故障など) ・個人事業の場合、生活費の一部として使うケースもある |
業種別|新規開業資金の例
開業資金は、業種や営業形態、規模によって大きく異なります。物件の家賃や内装費、仕入れに要する金額なども考慮しながら、余裕をもった資金計画を立てることが必要です。
| 業種 | 必要資金 | 詳細 |
|---|---|---|
| 飲食業 (カフェ・小規模店) | 200万~500万程度 | 店舗取得 厨房設備 内装工事 備品購入 運転資金 など |
| 移動販売 (キッチンカー) | 100万~300万程度 | 車両の購入費 車両の改装費 許可取得費 食材費 など |
| 軽貨物運送業 (個人事業) | 50万~200万程度 | 車両購入費 車両リース費 保険 営業許可 など |
| 設備工事業 (左官・リフォーム等) | 200万~500万程度 | 工具・機材 車両費 事務所賃貸費用 運転資金 など |
| 美容室・理容室 | 300万~800万程度 | 店舗取得 内装工事 機器購入 広告費 備品 など |
| 整体・整骨院 | 300万~600万程度 | 物件費用 施術ベッドや機器 許認可費用 など |
| 小売業 (雑貨・アパレル) | 200万~500万程度 | 物件取得 商品仕入れ 内装費 什器 広告宣伝 など |
| ネットショップ (EC) | 10万~100万程度 | サイト構築費 商品仕入れ 広告費 など |
| フリーランス (デザイナー等) | 5万~50万程度 | PCやソフト 周辺機器 マーケティング費用 など |
店舗型の業態は、賃貸物件の取得費や内装工事費が大きな負担になります。
フリーランスなら大幅に抑えられるケースもありますが、宣伝にかける資金やツール代なども見落とさずに準備しておきましょう。
起業時にできる金融機関からの資金調達
業種や形態によっては高額の開業資金が必要となるため、政府系金融機関や民間金融機関による融資を上手く活用しましょう。
起業時の資金調達に使える、日本政策金融公庫の創業融資や信用保証協会を利用した制度融資、銀行やノンバンク系ビジネスローンについて詳しく見ていきたいと思います。
日本政策金融公庫なら最大7200万円(運転資金4800万円)まで融資可能
起業時の資金を調達するなら、はじめに政府出資の金融機関である日本政策金融公庫を検討しましょう。
公庫融資なら、自己資金が少なくても申し込めますし、事業計画書を入念に作成して提出すれば、創業融資を受けやすくなる可能性も高まります。
ただし、公庫への手続きは借り手主体で行う必要があります。審査に時間がかかることもあるため、早めの準備を心がけましょう。
金利は民間金融機関のプロパー融資より低めで、創業後7年以内であれば追加で借りられる追加融資制度も用意されています。
ただし、審査が甘いわけではないため、事業計画の根拠を整えておくことが大事です。
- 事業計画を立て、必要資金を算出
- 公庫(または連携している金融機関)に相談
- 申込・審査
- 承諾
- 融資実行
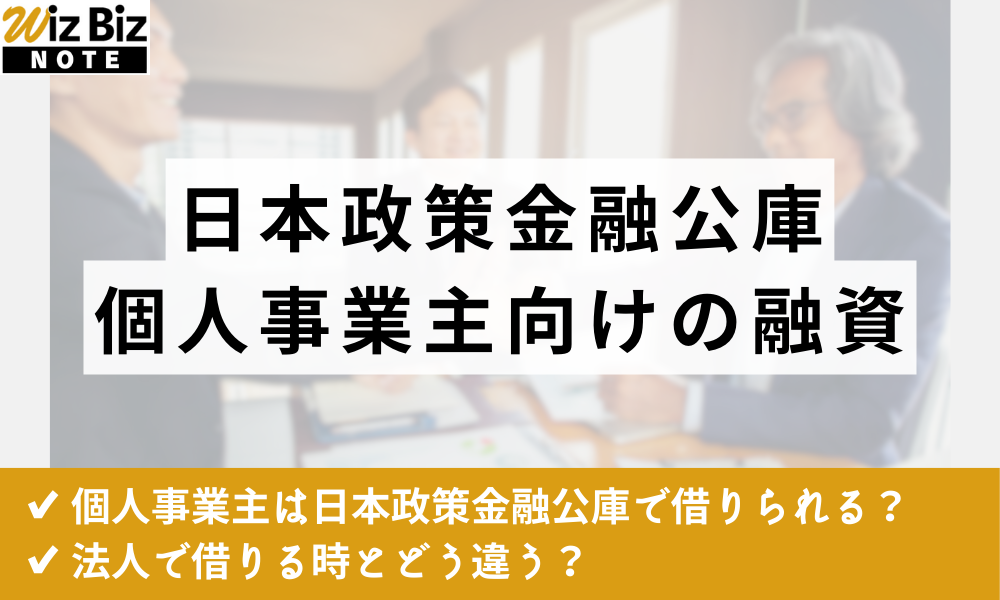
信用保証協会なら各種制度融資の利用ができる
信用保証協会は、中小企業や個人事業者が金融機関から融資を受ける際に保証を行う公的機関です。女性や若者、シニア向けなどに向け、金利優遇や保証料減免を設けた創業融資が数多く存在します。
保証協会に保証を頼めば、金融機関から見ればリスクを軽減できるため、結果として借り手が融資を受けやすくなる側面があります。
ただし、融資商品によっては、自己資金の10%ほどを要件としていることもあるため、利用条件を事前に確認しておきましょう。保証料はかかりますが、行政が補助してくれる場合もあります。
融資を申込む際は、金融機関へ行って相談するか、市区町村や商工会議所で紹介を受ける方法が一般的です。
すべての金融機関が同じ商品を取り扱っているわけではないため、事前にチェックしておくとスムーズです。
- 必要資金を算出し、事業計画をまとめる
- 金融機関窓口(または役所、商工会議所)に相談
- 申込・審査(保証協会と金融機関の二重審査)
- 保証承諾後、融資契約
- 融資実行
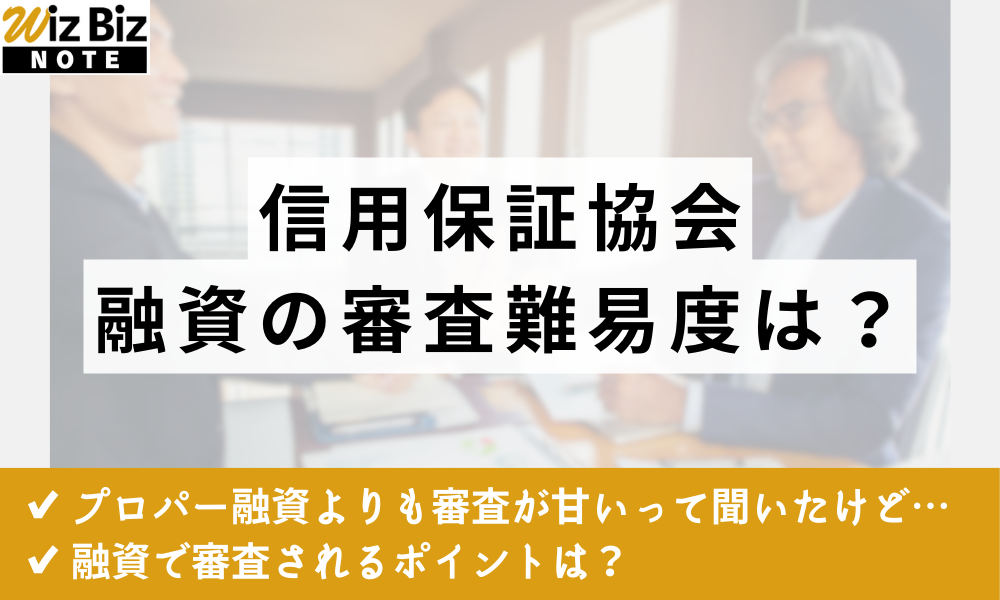
銀行(信用金庫)融資なら審査がスムーズ
銀行や信用金庫が行うプロパー融資は、保証協会を通さないため審査結果が出るまでのスピードが早めです。保証会社を利用しない場合は、保証料負担もないため、総返済額を抑えられる点もメリットといえるでしょう。
ただし、起業資金は「債権回収リスクが高い」とみなされがちです。特にメガバンクは、リスクが高い小口融資を積極的に扱わない傾向があります。
地元密着の信用金庫なら、地域活性化のために積極的に支援することもありますが、その場合でも自己資金が全くないとなると借入は厳しいでしょう。
申込時には事業計画や代表者の経歴をしっかり伝え、返済の裏付けを示すことが大切です。
実際には協会付き融資を提案されるケースもあるため、銀行独自のプロパー融資が利用できるかどうかは、支店や担当者とのやり取りに左右されるでしょう。
- 事業計画の作成
- 銀行(または信用金庫)へ相談
- 審査
- 融資承認
- 融資実行
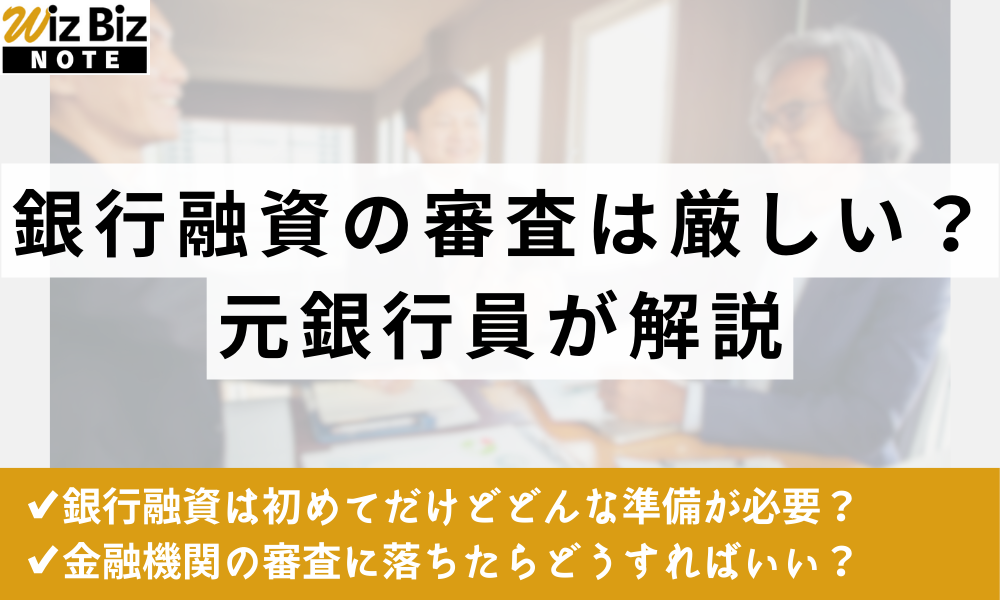
ノンバンクならスピーディーな資金調達が可能
ノンバンクのビジネスローンは、審査と融資実行までが早い点が魅力です。
Web申し込みでほぼ完結する商品も存在し、店舗への来店が不要なこともあります。資金使途を問わないタイプが多く、事業計画の詳細を詰めていなくても審査に通るケースも多いでしょう。
しかし、金利水準は公庫や銀行融資に比べて高めに設定されています。融資時に「融資額×数%」といった形で事務手数料を取られる場合もあり、総返済額が膨らむ恐れがあります。
ノンバンクは、公庫や銀行で借りられなかった方の最終手段になりがちですが、一方で金利が高く返済不能に陥るリスクには注意しましょう。
また、銀行の立場から見ると「ノンバンクの借入=信用力のない事業者」と判断される場合があるため、将来の銀行融資が難しくなる場合もあります。
ノンバンクを利用する場合は、「金利」と「将来の銀行融資の可能性」の両方を考えながら慎重に検討しましょう。
- 事業計画をざっくりまとめる
- Webなどから申込
- 簡易審査
- 契約締結
- 融資実行
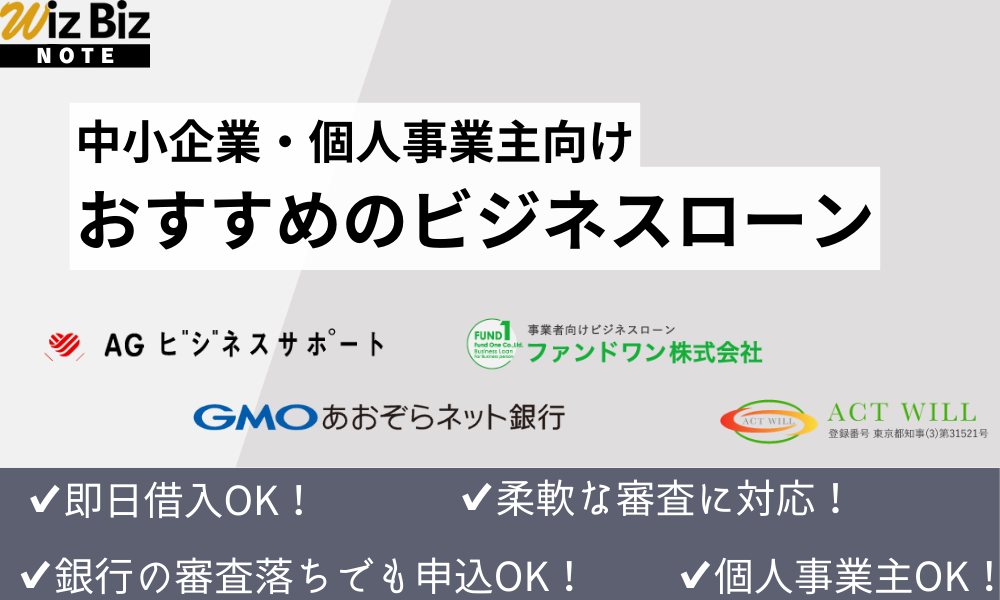
起業時にできる補助金・助成金の資金調達
起業を考えている方の中には、返済のいらない補助金や助成金を活用したいと考えるケースも多いでしょう。
補助金や助成金は返済不要です。しかし、公募期間や審査基準が設定されているため、希望のタイミングで使えない可能性もあります。
それでも採択されれば、初期費用や販路開拓に必要な経費の一部を補助してもらえるのが魅力です。
公募時期や要件をチェックしておき、事業計画と合致する制度を早めに見つけることが大切といえるでしょう。
また、補助金や助成金は後払いになる仕組みが多いので、先行投資を賄えるだけの手元資金を確保することも重要になってきます。
創業助成金(例:東京都中小企業振興公社)
東京都中小企業振興公社が提供する「創業助成金」では、返済不要の助成金を活用できる点が大きな魅力です。ただし、採択されるには一定の条件があり、公募期限にも注意が必要です。
対象は「東京都内で創業を予定していること」、あるいは「創業後5年未満の中小企業者」です。そのほか、下記の要件が定められています。
- TOKYO創業ステーションの事業計画書策定支援を修了している
- 東京都制度融資(創業)を利用している
- 都内の公的創業支援施設に入居している
助成対象期間は、交付決定日から6か月以上2年以下と定められています。
助成限度額は上限400万円・下限100万円で、助成率は助成対象経費の3分の2までです。賃借料や広告費、備品購入費なども支援対象になっており、起業時の資金も準備できるでしょう。
ただし、実際の精算は後払い方式となり、事業者は一度立て替えてから費用の2/3が助成される仕組みです。そのため、自己資金0円で利用するのはリスクが高いでしょう。
※参考:東京都中小企業振興公社
小規模事業者持続化補助金(創業型)
小規模事業者持続化補助金(創業型)は、創業後3年以内の小規模事業者が販路開拓や経営力強化を図るために使える補助金の一つです。
補助率は対象経費の3分の2で、上限額は通常200万円、特例を満たせば250万円まで拡大されます。
商工会や商工会議所のサポートを受けながら経営計画を作成し、審査で採択されると経費の一部を補助してもらえます。
対象となる小規模事業者の定義は業種によって異なります。商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)なら従業員5人以下、それ以外の業種や製造業などは20人以下です。
創業後まもない段階で資金に余裕がない事業者にとっては、返済が不要である点が魅力といえるでしょう。
ただし、この補助金も後払い方式なので、先に経費を立て替えて取り組んだうえで、報告書を提出して補助額を受け取る流れです。
また、公募期間が決められているため、申請時期は事前に確認しておきましょう。申請書類の作成には時間がかかるため、経営計画書なども余裕をもって作成しておくことが必要です。
人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金は、人材確保や労働環境の整備を推進する事業者に対し、厚生労働省が経費の一部を助成する制度です。
職場づくりや労働条件を改善することで人材の定着を図りたい場合、この助成金が使えます。ただし、コースによって細かい要件や助成額が異なるため、事前に自社の取り組みを整理してから選択する必要があるでしょう。
対象は、「魅力ある職場づくりを目的に、労働環境の向上策を実施する事業主」です。創業間もない段階で人を採用する際に検討できるでしょう。
ただし、助成金の申請から支給までに時間がかかることが多く、計画的な資金繰りが必要です。就業規則や賃金台帳などの書類を用意して手続きする形になるため、社会保険労務士のサポートを活用する事業者も多いようです。
公募時期が定期的に設定されるわけではない場合もあるため、下記の厚生労働省の公式ページをよくチェックして最新の情報を入手しておきましょう。
起業時にできるエクイティでの資金調達
起業時には、融資や補助金のほか、株式を発行して出資を受ける「エクイティファイナンス」を検討する方法もあります。
エクイティは返済義務がない点が魅力ですが、出資者が株主となり経営に影響を及ぼす可能性には注意しなければいけません。
クラウドファンディングやエンジェル投資家、ベンチャーキャピタル(VC)、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)といった手法について詳しく見ていきましょう。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、返済不要で多くの支援者から資金を集められる手段の一つです。事業計画を公開し、プラットフォームの審査を通過すれば、100万円から3,000万円程度が調達できる事例もあります。
資金調達の流れとしては、事業計画を作成し、必要資金を算出したうえでクラウドファンディングのプラットフォームを選ぶところから始まります。1件当たりの投資金額は小さいため、多くの投資家を獲得できるPR戦略が重要になるでしょう。
成立後は情報開示が必須となり、調達額の10~20%ほどのプラットフォーム手数料を支払う点も考えておく必要があります。
クラウドファンディングは、事業が成功すれば大勢のファンを獲得できるため、事業を軌道に乗せることも容易となります。逆に集客に失敗すると目標額に届かず、調達が成立しないリスクがあります。
エンジェル投資家からの出資
エンジェル投資家からの出資とは、個人投資家(エンジェル)が事業の成長を見込んで資金を提供する方法です。資金調達の目安は100万円から5,000万円程度とされており、投資家の資力や興味分野によって幅があります。
調達するには、事業計画を作成し、必要資金を算出したうえでエンジェル投資家とマッチングする場を探す必要があります。
具体的には、経済産業省のサイトやベンチャー系のアプリ・コミュニティなどを活用し、投資家との接点を持つ流れです。投資家が承諾すれば出資契約の交渉に入り、出資額と株式比率を決めたうえで契約を締結します。
出資が決まれば返済義務は生じませんが、株主として経営に発言力を持つ可能性が高まり、事業方針やスタッフの人事などに口を出される場合もあるため、経営の自由度が低くなると考えておきましょう。
ベンチャーキャピタル(VC)からの出資
ベンチャーキャピタル(VC)からの出資は、スタートアップ企業がよく利用する資金調達方法です。事業が大きく成長する見込みがあれば、数千万円から数億円単位の投資を受けられる可能性があります。
ただし、審査のハードルが高く、高い成長意欲や優位性のある技術、明確なマーケット戦略などを示す必要があります。
資金調達の方法は、まず事業計画書を完成させたうえでVCにアプローチし、面談やプレゼンで魅力を伝える流れです。投資契約を締結すると、VCから役員の派遣や経営へのアドバイスを受ける場合があり、事業を飛躍させるチャンスが生まれます。
その一方で、株式の一部を譲渡するため、経営権に影響が及ぶ可能性については注意しましょう。
投資が実行されるまでに3~6か月程度かかる例が多く、タイミングを見計らう必要があります。個人事業主は対象外になる傾向が強く、法人化して一定の売上実績や成長戦略が明確な企業が中心となります。
コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)からの出資
コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)からの出資とは、大企業の投資部門が自社の事業領域と相乗効果のあるスタートアップに出資する手法です。
数千万円から10億円を超える投資例も存在し、資金だけでなく大企業の販路や技術面での支援も期待できます。
調達の流れは、VCと類似し、事業計画を提出して興味を示してもらえれば面談やプレゼンを実施します。資金が大きいだけに審査も慎重に行われ、3~6ヵ月以上かかることもあります。
出資を受けると、事業提携や共同開発が進む利点がある一方、親会社の戦略に左右されがちです。自由度を重視する経営者にとっては好ましくない手法かもしれません。
個人事業主がCVCから出資を受ける例はほぼ見当たらず、法人化してある程度の規模を持ち、大企業との協業を望むスタートアップが対象になりやすいといえます。投資契約に加え、業務提携や具体的な開発プロジェクトの合意がセットになるケースも多々あります。
その他起業時に検討できる資金調達
融資や補助金、エクイティ出資といった方法以外にも、個別の人脈や取引関係を活用する調達方法も検討できるでしょう。
ビジネスパートナーとの共同出資や家族・知人からの借入、主要取引先からの借入などが利用できますが、これらは当事者同士の合意によって自由度が高い反面、金銭面でのトラブルが生じる可能性も否定できません。
自分の状況に合わせ、契約書や返済条件などをはっきり決めることが大切です。
ビジネスパートナーとの共同出資
ビジネスパートナーとの共同出資とは、複数の経営者が資金と経営リソースを出し合う方法です。
事業への想いやビジョンを共有する仲間がいれば、大きな相乗効果を期待できるでしょう。資金の負担が分散され、個人では難しい事業規模にも取り組める可能性があります。
ただし、出資比率によって意思決定権が変わるため、意見が合わないと経営方針をめぐって対立が生じる恐れがあります。
前職の同僚や友人などをパートナーにする場合も、事前にルールや契約を整えておかないと金銭トラブルに発展しかねません。共同出資者の資力や意欲が想定より低いと、十分な額を集められない不安もあります。
出資比率を同じにすることで対等な関係を築けるかもしれませんが、事業運営においては決裁プロセスが煩雑になる可能性もあります。逆に比率が異なると、意見の重みが変わる点に注意が必要です。
共同出資の良さを最大限に引き出すには、役割や責任範囲を具体的に決め、合意書に落とし込むことが大切です。
役員・家族・知人からの借入
役員・家族・知人からの借入は、金融機関の審査に通らない場合や、すぐにまとまった資金を用意できないときの最終手段として検討できるでしょう。
身近な人からの借入は、相手の懐事情が左右するため、希望額を確保できる保証はありません。
出資ではなく借入になるため、返済期日や利息の有無を契約で明示しないとトラブルになる点は注意する必要があります。特に「家族だから契約書を作らない」という発想は危険で、返済が滞れば家族関係にも大きな亀裂が走る恐れがあります。
あくまでも「これ以上他に頼れない」状況で検討する手段と、捉えるほうが安全です。
また、借入ではなく出資として扱う場合、株式の取り扱いが生じて意思決定の範囲に影響が出るかもしれません。いずれにせよ口約束で済ませず、書類の整備を徹底しておきましょう。
主要取引先からの借入
主要取引先からの借入とは、仕入れ先や販売先など、関係取引先から資金を借りる方法です。
大口取引が見込める場合、相手先企業にとっても自社の利益につながる場合も多いため、出資や融資を検討してくれる場合があります。
ただし、取引先からの借入は一社への依存度が高くなるため、返済が滞れば事業そのものの存続が危うくなるリスクがあります。
独立性が損なわれるリスクにも注意が必要です。場合によっては100%子会社のような位置づけになり、経営の自由度が下がる恐れもあります。
自社の将来像や自立をどこまで重視するかが、この調達方法を選ぶかどうかのポイントになるでしょう。
起業時に自己資金がなくても資金調達はできる?
起業時に自己資金がほとんど用意できないと「起業が難しいのでは?」と考える方も多いでしょう。
特に、他社借入を延滞しているなど、ブラックリストに載っており「融資が難しい」という場合は、公庫からの借入も慎重になりがちです。
ここからは、起業時に必要な自己資金の目安や、信用情報に問題があるときの対策について解説します。
起業時に用意しておくべき自己資金の目安
起業時の自己資金は、「運転資金の6ヵ月分」を考えておきましょう。
ただし、売掛金と買掛金の支払いタイミングがずれることが分かっている場合は、さらに上乗せしておかないと資金ショートにつながるリスクがあります。
また、すべて自己資金でまかなうと予備費が少なくなるリスクが生じます。
創業期は想定外のコストが生じることが多いため、無理のない範囲で融資を上手に利用することも視野に入れておきましょう。
自己資金0円や起業時にブラックリストに載っている時の対処法
公庫や信用協会の創業融資では、簡易的な信用調査で済ますこともあり、実際のところブラックリストに載っている人でも事業融資が利用できる場合があります。
ブラックリストに載っていても審査通過できる場合、「審査に影響するほどの金融事故ではなかった」というケースがほとんどです。
ただ、当座預金の事故などは照会されるため、全くの無条件で融資が可決されるわけではありません。
どうしても融資が難しいなら、配偶者や親族を代表者に立てて申し込む方法もあります。
信用情報に不安があるなら、「審査の通りやすいノンバンクで少額のビジネスローンを利用する」という方法があります。しかし、金利負担と将来の銀行取引への影響を考慮しなければいけません。
リスクが高い状態で起業すると、経営が軌道に乗る前に返済が苦しくなるリスクが増します。自己資金0円でも起業を優先するべきか、他の方法で収入を確保しつつ、自己資金を貯めてから起業するかは慎重に検討しましょう。
個人事業主が起業や開業資金を調達する際の注意点
個人事業主が起業や開業資金を調達する際は、金融機関からの融資より、先に公庫融資から検討しましょう。
個人事業主の場合は生活費と事業資金との区別が難しく、銀行のプロパー融資を得るのは容易ではありません。
公庫では創業融資を取り扱っており、比較的手厚い支援を受けられる可能性があります。商工会議所や役所の専門窓口を活用すれば、事業計画の作成もサポートしてもらえるでしょう。
ノンバンクや消費者金融系のビジネスローンは金利が高く、事業拡大に負担がかかりやすいため、最終手段として考えるほうが無難です。
起業時に資金調達をするメリット・デメリット
起業時に資金を調達する方法には、融資や助成金・補助金、資金援助などさまざまな方法があります。
どの方法を選ぶかによって返済義務の有無や調達できるまでのスピードも異なります。
それぞれの資金調達方法のメリットとデメリットを比較し、自身の状況に合った方法を選んで事業資金の計画を練りましょう。
融資で起業時の資金調達をするメリット&デメリット
融資で事業資金を調達する方法には、「まとまった資金を確保しやすい」というメリットがあります。利息負担はあるものの、自己資金を温存したまま開業できれば、安心して事業をスタートできるでしょう。
一方で、利息負担と毎月の返済義務が発生する点はデメリットです。返済が遅れると信用を損ない、事業継続が厳しくなるリスクもあります。
利息は経費処理が可能で節税につながる面もありますが、利益が安定していない段階では返済のプレッシャーが重荷になるため借り過ぎには注意しましょう。
補助金や助成金で起業時の資金調達をするメリット&デメリット
補助金や助成金による資金調達は、返済不要な資金を得られる点が最大のメリットです。
応募が採択されれば自己負担を減らせるため、運転資金や設備投資に使う資金にも余裕が出るでしょう。特に金融機関からの借入に抵抗がある方にはおすすめです。
一方で、補助金や助成金は公募期間が限られているため、事業計画を完成させてもタイミングが合わなければ申し込めません。
さらに申請書類を提出して審査通過しなければ支援が受けられないなど、不確実な要素もたくさんあります。もし審査通過できたとしても、補助金や助成金は後払い方式が多いため、先行して費用を立て替える必要もあります。
運転資金や設備資金に使えない商品もあるため、利用時には余裕をもったスケジュール管理と、要件の事前チェックが欠かせません。
自己資金100%で起業時の資金調達をするメリットデメリット
自己資金で起業時の資金を調達する方法は、借入や返済義務が発生しないことが最大のメリットです。
利息負担がなく、キャッシュフローの不安を抱えずに済むので、気持ちの面で余裕が生まれるでしょう。
一方で、手許資金が潤沢でない限り大きな投資や宣伝活動が難しくなり、事業拡大のタイミングを逃す点がデメリットといえます。売上が軌道に乗らない期間が長引くと、生活費を含めて厳しい状況に追い込まれるリスクもあります。
全額自己資金で起業する方法は、リスクを低く抑えられる一方、成長スピードが限定される点には注意が必要です。
起業時に金融機関で融資を受けやすくするポイント
金融機関から創業融資を引き出すには、返済可能な計画を示し、融資担当者に「貸しても問題ない」と思わせる必要があります。
事業計画や資金計画の整合性だけでなく、代表者の経歴や自己資金の有無、企業の独自性などが判断材料になるでしょう。
最後に、起業時に融資を受けやすくするためのポイントについても見ていきます。
事業計画と資金計画を立てる
融資を受ける際には、「事業計画書」が審査通過を左右すると言っても過言ではありません。
金融機関はこの計画書をもとに、返済の目途があるかどうかを判断します。事業計画書の数字に確かな根拠を持たせ、説得力がある売上や利益の見込みを見せるのがポイントです。
事業計画書には、どれだけの資金を必要としているか、なぜその額が妥当かを明確にする欄が設けられています。ここを曖昧にしてしまうと、「絵に描いた餅」とみなされ、審査通過は難しくなるでしょう。
必要資金を書く時は、実際に見積もりなどを取得し、業界の相場を踏まえた数字を提示すると説得力が増します。
売上計画についても、楽観的すぎず、企業努力や現実的なシミュレーションを含めて示すのが好ましいでしょう。
金融機関は「根拠のある数字」かどうかを厳しく見ています。
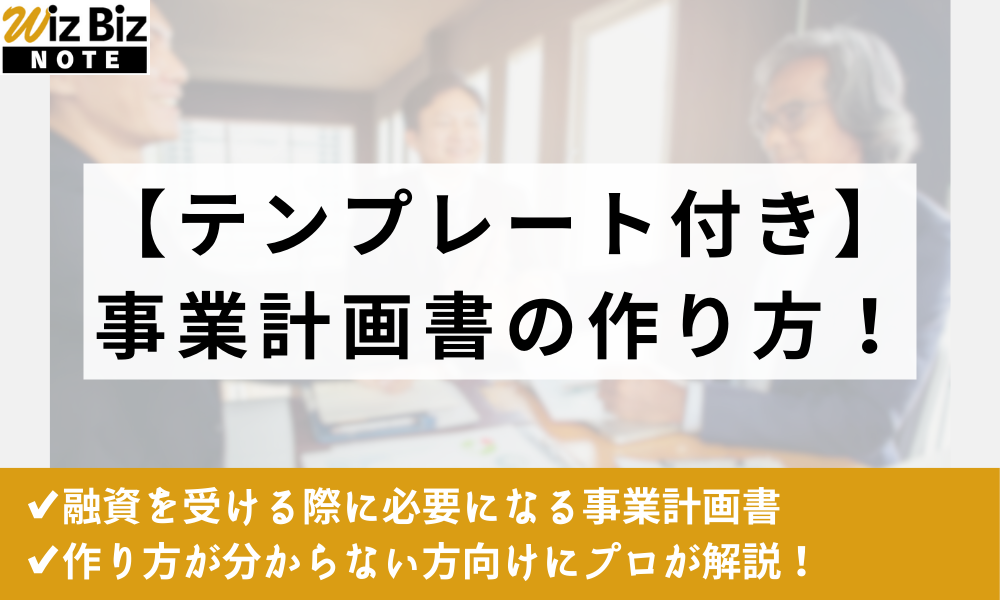
自己資金を準備する
起業時の融資では、「自己資金をどの程度持っているか?」が審査を左右します。
自己資金0円でも申込は可能ですが、「計画性が足りない」とみなされる恐れがあるため、実際には融資が可決されることは稀でしょう。たとえ少額でも、資金を積み立ててきた事実は担当者に好印象を与えます。
金融機関の担当者は、「事業が想定どおりに進まなくても、自己資金で補填できるかどうか?」をチェックしています。
1円も貯めずに起業する人は、どうしても「リスクが高い」と判断してしまうでしょう。50万円でも100万円でも自己資金を用意しておけば、融資の審査ではプラスに働きます。
具体的には、1,000万円を借りたいなら、融資額の10%である100万円の自己資金を目標にするのが目安です。
必要資金の根拠を明確にする
融資希望額と、その根拠を詳しく示すことも、審査通過のポイントです。
漠然と「1,000万円あれば安心」と述べるだけでは説得力に欠けます。見積書や内訳書をそろえ、初期費用と運転資金の内訳を具体的に示す姿勢が大切です。
起業融資を申し込む際は、事業計画書に基づく資金計画を金融機関に提出しなければいけません。
このとき、内装工事なら「工事会社からの見積」、広告宣伝なら「具体的なメディア出稿の費用根拠」などを添えると、金融機関の担当者も納得してくれるでしょう。
業種によっては仕入れリストや家賃契約書などを用意すると信ぴょう性が高まります。根拠がはっきりしていれば、大きめの金額でも妥当性を認めてもらえる可能性が上がります。
企業のアピールポイントを示す
同業他社との差別化や将来性を明確に提示することも、審査でプラスに働くポイントです。
金融機関は、「競争の激しい市場でどのように勝ち抜くのかを確認したい」と思っています。
その企業ならではの強みやサービスの魅力を計画書に盛り込むことで、担当者も稟議書にポジティブな要素を書きやすくなるでしょう。
商品の品質だけでなく、販路や集客方法なども含めて説明すれば、事業が軌道に乗る見込みを示しやすいです。単に「他社と違う」ではなく、「どこがどのように違うのか」を数字や具体例で補強すると説得力が増します。
代表者の経歴と実績をアピールする
創業融資の審査では、代表者がどの程度その業界を理解しているかが重視されます。
長年の勤務経験や経営実績があるなら、融資は有利に働くでしょう。経験ゼロでも、なぜその事業を選んだのかを具体的に説明することで、担当者が納得してくれる可能性があります。
金融機関の稟議資料には「事業経験」や「経営者の力量」に関する項目があります。
例えば、飲食店を開業する人が同じ業種で10年間働いた実績があれば、仕入れから調理、接客まで理解していると判断してもらえるでしょう。
経験が浅い場合は、研修や勉強を通じて補ってきたストーリーを示し、自分がこの事業を成功させる根拠を客観的に説明することがポイントです。
起業時の資金調達まとめ
起業の初期段階では、開業費や運転資金を確保しなければいけません。公庫融資は自己資金が少なくても利用しやすい反面、審査に時間がかかるため、余裕をもった手続きが必要となります。
補助金や助成金は返済不要ですが、公募時期や審査をクリアしないと使えません。
株式を発行して出資を受ける場合は返済負担を減らせますが、経営権の一部を譲渡するリスクにも注意する必要があるでしょう。
それぞれの資金調達方法には、メリットとデメリットがあります。安定した経営を目指すなら、複数の手段を組み合わせて、リスクを回避しながら資金を調達する方法がおすすめです。