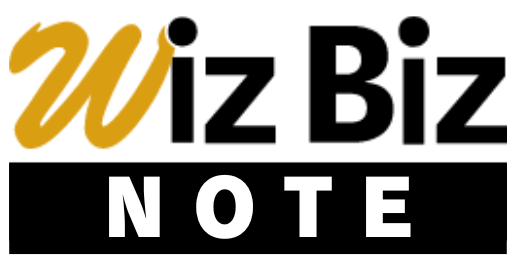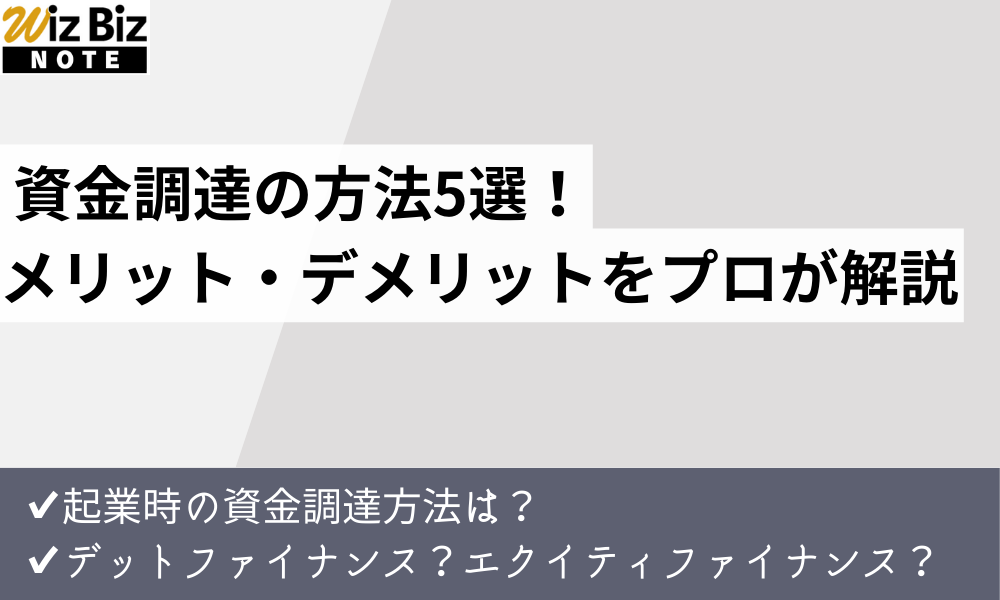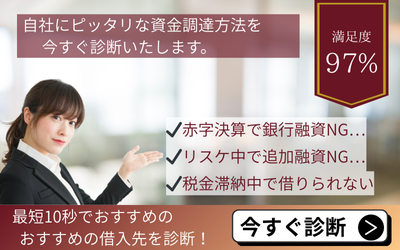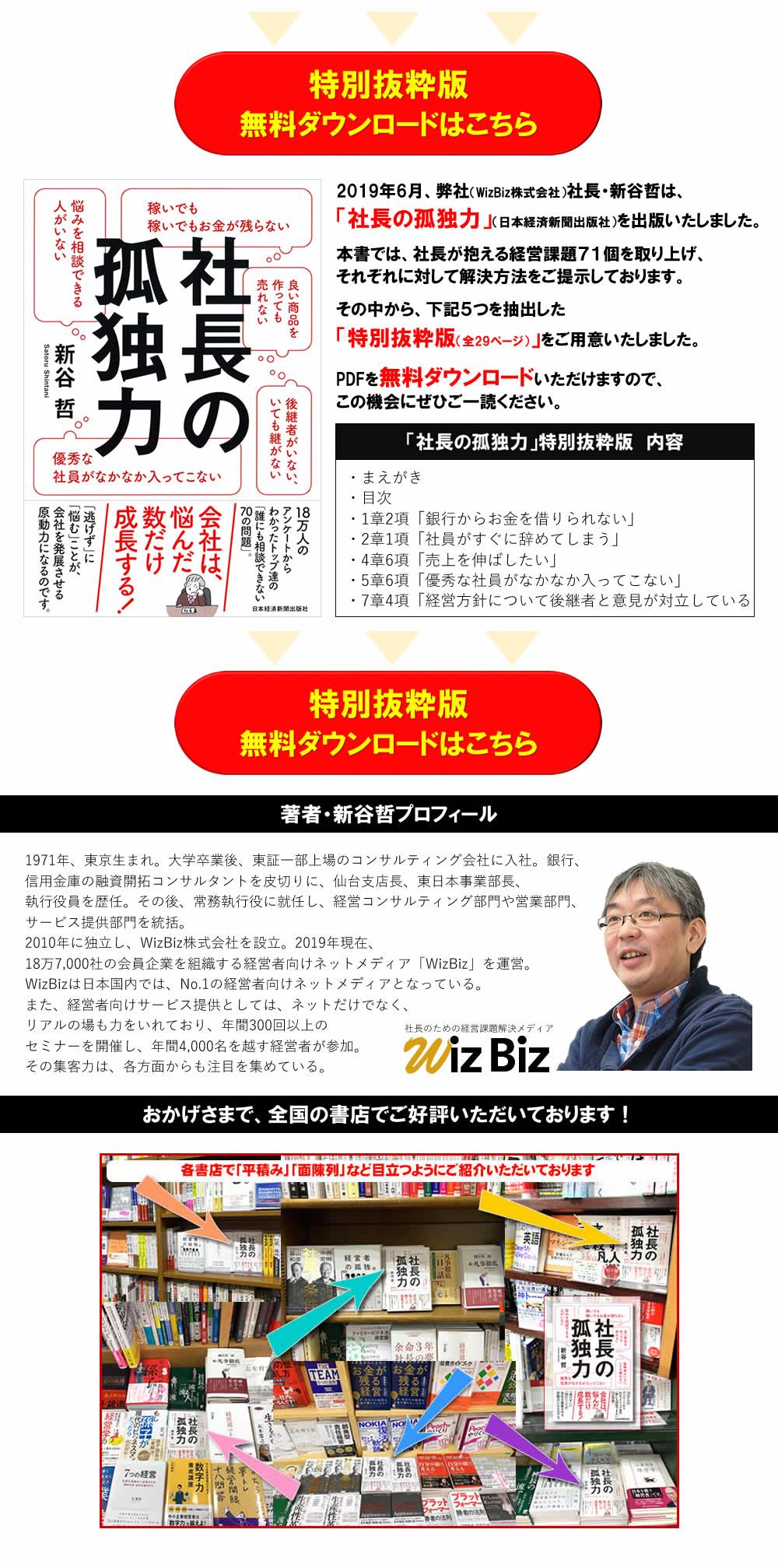事業を進めるうえでは、新商品の開発や設備投資、運転資金の確保など、さまざまな目的で資金が必要になります。
ただ、資金調達には銀行融資や増資・公的支援など、多種多様な方法があります。
自社の状況に合った方法を選ばないと、資金調達に時間を要したり余計な手数料コストがかかったりするため注意が必要です。
今回は、創業期など企業のステージ別や規模別など、状況に合わせた最適な資金調達方法について解説します。
| まとまった金額の借入なら ビジネスローンがおすすめ! | 売掛金があるなら ファクタリングがおすすめ! |
|---|---|
AGビジネスサポート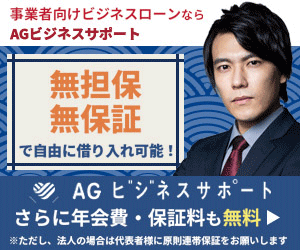 | ワイズコーポレーション |
| 迅速な審査ですぐに事業資金を融資してもらう方法 | 売掛金や請求書を買い取ってもらい現金化する方法 |
| 融資まで 最短即日 | 入金まで 最速当日中 |
| 申込〜入金 来店不要! | 申込〜入金 来店不要! |
| 融資限度額 50万円〜1,000万円 | 買取限度額 300万円〜上限なし※4 |
| 金利 年3.1%〜18.0% | 手数料 1%〜14.8% |
| 利用者※1 法人(赤字でもOK!) 個人事業主 | 利用者 法人(売掛金があればOK!) 個人事業主 |
| 必要書類※2 本人確認書類 決算書などのみ! | 必要書類 請求書 通帳などのみ! |
| 無担保無保証で借入可能!※3 | 取引先への通知なし! |
| AGビジネスサポート 公式サイトから今すぐ申込 | ワイズコーポレーション 公式サイトから今すぐ申込 |
※2:法人→代表者本人を確認する書類・決算書・その他必要に応じた書類
※2:個人事業主→本人を確認する書類・確定申告書・所定の事業内容確認書・その他必要に応じた書類
※3:原則不要。法人の場合は原則代表者が連帯保証
※4:該当しない方は要相談
貸付条件はこちら

WizBiz株式会社 代表取締役
経歴
1971年東京生まれ。大学卒業後、東証一部上場のコンサルティング会社に入社。銀行、信用金庫の融資コンサルタントを皮切りに、仙台支店長、東日本事業部長、執行役員を歴任。その後、常務執行役に就任し、経営コンサルティング部門や営業部門、サービス提供部門を統括。2010年に独立しWizBiz株式会社を設立。現在、経営者向けネットメディア「WizBiz」を運営。国内では経営者の会員登録数でNo.1のメディアとなっている。また、経営者向けサービス提供としては、ネットだけでなく、リアルの場も力をいれており、年500回以上のセミナーを開催し、4000名を越す経営者が参加。18万人の社長アンケートから1000個の悩みを回収。
著書:社長の孤独力
法人・事業主の資金調達には主に5つの手段がある
会社が必要な資金を集める方法には、主に5つの手段があります。
- 借入(デットファイナンス)
- 出資(エクイティファイナンス)
- 自社の資産を活用するアセットファイナンス
- 国や自治体からの助成金・補助金
- クラウドファンディング
どの方法を使うかによって、必要書類や審査手続き、返済負担、経営への干渉度合いなどが大きく変わります。
まずは、それぞれの手段の大まかな特徴を把握し、自社の事業計画や資金ニーズに合致するかどうかを見極めることが重要です。
デットファイナンス
デットファイナンスとは、銀行や信用金庫、ビジネスローン、社債などのデット(有利子負債)を利用し、負債を計上しながら資金を確保する方法です。
利息を払わなければいけない一方、経営権を渡さずに済む点が大きな特徴です。
財務内容が安定している企業や、キャッシュフローに余裕があり、返済に支障がない事業者に向いている資金調達方法です。
運転資金の融資を受ける際は、業種によって月商の数ヵ月分が目安となり、小売業では2~3ヵ月分、製造業では6~9ヵ月分が一般的です。
設備資金の場合、必要資金の7~9割を借りられるケースが多く、負担する利息を低く抑えられるかどうかがポイントになります。
エクイティファイナンス
エクイティファイナンスは、新株を発行して資金を集める方法です。
返済が不要で高額の資金調達に対応できるものの、投資家に経営の一部を譲る形になるため、意思決定の自由度が下がる可能性があります。
スタートアップの成長資金や、研究開発を続ける企業が手元に十分なキャッシュを確保したい場合、あるいは株式上場をめざす企業にとっては欠かせない手段です。
小さくて数百万円、場合によっては数十億円単位の資金が動くこともあり、調達金額や企業の成長戦略に合わせて柔軟に活用しやすい点がメリットと言えます。
アセットファイナンス
アセットファイナンスは、不動産や動産、売掛債権など、自社が保有する資産を売却・流動化することで資金を作る方法です。
- 余っている不動産を手放す
- 売掛金をファクタリングで売却する
- リースバックで資産を売却しながら使用を続ける
借入を増やさなくても済むため、バランスシートの膨張を避けたい企業や、売却益を借入金の返済にあてて財務内容を改善したい企業にとっては魅力的です。
ただし、売却益が発生すると法人税負担が増えたり、資産を手放すタイミングを誤ると損失につながったりするリスクもあるため、入念なシミュレーションが欠かせません。
助成金・補助金による調達
助成金や補助金による資金調達では、返済不要の資金を得られるため、創業期や新分野への進出を計画する企業にとって大きなメリットがあります。
国や自治体の目的と合致する事業や、地域活性化、環境保護、IT化などの要素を含むプロジェクトであれば数十万円から200万円程度の支援を受けられます。
ただし、申請要件が細かく定められていたり、補助金を受け取るまでに時間がかかったりする点には注意が必要です。
細かな書類が必要で審査通過をしなければ補助が受けられないため、早めの情報収集と計画作成が求められます。
クラウドファンディングによる調達
クラウドファンディングは、インターネットを利用して、広く一般から資金を募る方法です。
クラウドファンディングには、大きく分けて下記3つの方法があります。
- リターンが不要な寄付型
- 商品・サービスを提供する購入型
- 株式や配当などでリターンをする投資型
購入型や寄付型は数百万円程度の事例が多いのに対し、投資型では数億円規模の調達も行われています。
ただし、プロジェクトの広報やリターンの準備に手間がかかるため、実施前には十分な計画とプロモーション戦略が求められます。
デットファイナンスによる資金調達方法
デットファイナンスによる資金調達方法には、銀行融資・日本政策金融公庫の公的融資・ビジネスローン・社債の発行など、さまざまな方法があります。
どれも返済義務があり金利コストを伴いますが、それぞれ審査基準や限度額、担保・保証の有無などに違いがあります。
銀行・信用金庫からの借入
銀行や信用金庫からの借入は、運転資金や設備資金などを低金利で借りられる方法ですが、創業間もない企業には審査が厳しい傾向があります。
融資に通るためには、一定期間の業歴や安定した収益、事業計画書や財務諸表の提出が必要です。審査通過にも時間や手間がかかるため、急ぎの融資には不向きでしょう。
コミットメントラインやシンジケートローン(※)など、用途や期間に応じた多様な融資形態も利用できますが、少額借入では手続きの手間や金利手数料のコストが見合わないかもしれません。
創業後3年程度経過し、事業が安定してきたタイミングで、メインの資金調達手段として利用するケースがほとんどです。
※コミットメントライン: 事前契約で一定額を必要時に借りられる融資枠
※シンジケートローン: 複数の金融機関が協調して提供する大口融資

日本政策金融公庫からの借入
日本政策金融公庫は、国が設立した公的金融機関であり、創業支援を目的とした融資制度が充実しています。
民間銀行よりも低金利で、担保や保証人が不要な商品もあるため、創業前や創業直後のタイミングでの資金調達に向いているでしょう。
設備資金なら最長20年の長期融資も可能で、運転資金でも7年返済で利用できるなど、返済期間に余裕があり、女性や若者向けの優遇制度も用意されています。
限度額は最大7,200万円(運転資金は4,800万円)で、民間の銀行と比べるとやや上限が低めですが、審査のハードルが比較的低く、創業初期の資金調達をしっかり支えてくれるでしょう。
ただし、申し込みから融資実行までに時間がかかることや、創業実績がまったくない状態だと事業計画書をしっかり作りこまなければならない点には注意が必要です。
金融機関からビジネスローンでの借入
銀行やノンバンク・信用組合などが扱うビジネスローンは、担保や保証人が不要でスピーディに資金を確保しやすい反面、金利がやや高めに設定される傾向があります。
審査結果が早く出るため、即日~数週間以内での融資が可能なケースもあります。
融資額は数百万円~数千万円程度までが多く、創業初期の運転資金や、予想外の出費が重なった際の穴埋めなど、短期的な資金繰りに利用するケースがほとんどです。
銀行のプロパー融資を利用できるほど信用力がなくても、ビジネスローンなら審査に通る可能性があるため、銀行との取引実績がまだ浅い事業者にとっては有力な選択肢です。
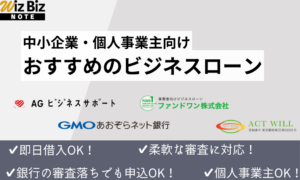
社債を発行する
普通社債や転換社債、ワラント債などを発行して投資家から資金を集める手法は、銀行融資よりも自由度が高く、長期で大きな額を調達しやすい点が魅力です。
また、発行コストは銀行借入と同等だとしても、発行費用など初年度にかかる費用が大きく、初年度の節税効果が高い手法といえます。
社債発行で資金調達する流れは、下記のとおりです。
- 社債発行計画の策定
- 社債の種類決定
普通債、転換社債、ワラント債、劣後債、私募債など
- 発行準備
引受証券会社との選定、信用格付けの取得、財務・事業計画などの開示資料作成、法的手続きなど
- 社債の募集と発行
ただし、格付けを取得しなければならないケースや、情報開示などの手続きにコストがかかるため、一定の信用力や財務基盤を持つ企業でないと難易度が高い場合があります。
いったん発行すると、銀行融資のように返済猶予を受けるのは難しく、利払いと元本返済を厳格に行わなければいけません。
大規模な設備投資や長期的な事業拡大の予定があり、かつ信用格付けを取ることで金利を低く抑えられるような企業であれば、銀行融資に代わる選択肢として検討する余地はあります。
エクイティファイナンスによる資金調達方法
企業が株式を発行して資金を集めるエクイティファイナンスでは、元本返済の負担がない代わりに、出資者が株主になるため、議決権が分散するリスクがあります。
大きな額を調達しやすい一方、投資家と利害や経営方針のすり合わせを行わなければなりません。
スタートアップや研究開発型の企業など、長期的な視点で大きく事業を伸ばす計画がある場合には、活用を検討してみましょう。
自己資金による増資
「自己資金による増資」とは、経営者自身が個人資金を拠出して株式を取得し、会社の資本金を増やす方法を指します。
借入ではないため利息の支払いはなく、外部投資家を入れないことから経営権が変わらないメリットがあります。
おもに、下記のような事業者に向いている資金調達の方法です。
- 自己資金のみで必要な金額をカバーできる事業者
- 経営権を第三者に渡したくない事業者
- 経営の自由度を保ちたい事業者
- 増資した自己資金が戻ってこなくても問題ないと考える事業者
具体的な増資の流れは、下記のとおりです。
- 増資の目的と事業計画を策定
- 取締役会の決議、株主総会の決議
- 増資方法の決定(発行株数、発行価格、払い込み方法など)
- 払い込み
- 増資の登記申請
- 税務署等に資本金変更の届出
ただし、事業に失敗したときは個人資産を失うリスクが高く、出せる資金にも限界があるため、大規模な資金調達には不向きです。
また、一度増資すると、あらためて資本金を減らすのは手間がかかり、信用にも影響が及ぶ点には注意しなければいけません。
VCやCVCからの出資
ベンチャーキャピタル(VC)や、大企業が自社戦略の一環として運営するコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)からの出資は、比較的大きな額を集めやすく、事業を急成長させるための専門的な支援が得られる点も大きなメリットといえます。
一方で、しっかりとした事業資産(技術力、成長可能性など)、事業計画や成長戦略が描けていないと承認を得ることは難しいでしょう。
VCやCVCから出資を受ける、おおまかな流れは下記のとおりです。
- 増資の目的と事業計画の策定
- 投資家の選定・交渉、条件の合意・契約(株主間協定など)
- 取締役会の決議、株主総会の決議
- 増資方法の決定(発行株数、発行価格、払い込み方法など)
- 払い込み
- 増資の登記申請
- 税務署等に資本金変更の届出
ただし、株式を引き受けてもらう形になるため、議決権の一部は譲ることになり、配当方針や重要な経営判断に投資家が関与する可能性が出てきます。
VCは、投資先が株式上場やM&Aによってキャピタルゲインを得ることが目的であるため、早期にEXIT(※)を求められる可能性もあります。
※EXIT: 投資回収のための株式売却やM&A、IPOなどの手段
急成長を目指し、将来的にIPOやM&Aを狙うスタートアップや中小企業にとっては大きなチャンスですが、投資家の意向も踏まえながら経営していく必要があります。
エンジェル投資家からの出資
エンジェル投資家からの出資は、VCよりも投資判断がスピーディで、条件面が柔軟にまとまることが多い一方、調達できる額は数千万円規模までが中心です。
エンジェル投資家から出資を受ける、おおまかな流れは下記のとおりです。
- 増資の目的と事業計画の策定
- 投資家の選定・交渉、条件の合意・契約(株主間協定など)
- 取締役会の決議、株主総会の決議
- 増資方法の決定(発行株数、発行価格、払い込み方法など)
- 払い込み
- 増資の登記申請
- 税務署等に資本金変更の届出
エンジェル投資では、投資家が個人的に起業家を応援する側面が強いため、経営者の熱意やビジョンに共感して資金を出してくれることもあります。
一方で、個人同士の関係が近くなりすぎることで、意見対立が起こると軋轢(あつれき)が起こってしまう点には注意が必要です。
アセットファイナンスによる資金調達方法
不動産や動産、売掛債権などを積極的に活用することで、借入を増やさずに資金を調達できるのが「アセットファイナンス」です。
遊んでいる不動産や機械設備があれば、それを売却したり、リースバックを使うことで、引き続き使用しながら資金を確保できるのがメリットです。
ただ、売却すれば将来の資産価値上昇の機会を失う場合もあり、ファクタリングでは手数料負担が銀行融資より高くなることもあります。
固定資産の売却
不動産や車両、機械設備などの固定資産を売却して資金を調達する方法は、短期間でまとまった資金を得たい場合や、不動産などの維持コストも削減したい場合に向いている資金調達手段です。
一方、後で試算が必要になったときには買い戻しが難しく、値上がり益を逃す可能性もあるため、売るタイミングや資産の有効性を慎重に見極める必要があります。
- メリットデメリットを踏まえて売却対象資産を検討する
- 市場価格の査定を受ける
- 金融機関、リース会社、売却先との契約交渉
- 売買契約締結、売却資金受取
売却益が大きく出た場合には法人税が増え、逆に売却損であれば節税になるケースもあるため、税務上のシミュレーションも含めて検討することが重要です。
売掛債権の売却
「売掛債権の売却」とは、いわゆるファクタリングと呼ばれる方法で、売掛金をファクタリング会社に売却して早期に資金化する方法です。
自社よりも売掛先の信用力が重視されるため、自社の財務状況が芳しくなくても利用できる可能性があります。
また、売掛先の与信管理の一環として、ファクタリングを活用する方法もあります。(実際に売却しなくても、ファクタリング会社が照会をかけた反応で判断できる)
- ファクタリング会社の選定
- 必要書類の提出と売掛先との契約の確認(売却の可否)
- 売却不可の場合は、売掛先との契約変更の交渉、契約変更
- ファクタリング会社による審査
- 売却契約の締結
- 売掛債権化売却資金の入金
借入ではないため貸借対照表の負債を増やさずに済み、短期間で資金を調達できるメリットがありますが、手数料が高めに設定されることが多い点には注意が必要です。
長期的な資金ニーズにはあまり向いておらず、売掛先との関係がどうなるかも含めて検討する必要があります。

リースバック
「リースバック」は、不動産や設備を売却して得た資金を事業に回しつつ、売却後もリース契約によって継続利用する方法のことを指します。
資産を売っても使い続けられるため、設備投資額を一度現金化したうえで運転資金にあてたり、借入金を返済して財務を改善したりといった柔軟な使い方が可能です。
- 対象資産の選定
- 売却先となる、不動産投資会社、リース会社、金融機関の選定
- 売却契約・リース契約の条件交渉
- 売却契約・リース契約の締結
- 売却代金の入金、リース料の支払開始
ただし、売却価格は市場価格より低くなる場合が多く、リース料がかかり続けるリスクがあるため、諸条件は入念に確認しなければなりません。
再購入オプションが設定されるケースもありますが、将来的な買い戻し価格が高くなることもあります。
リースバックは、契約期間満了後に資産を使えなくなるリスクがあることを理解しておく必要があります。
また、売却のタイミングは、利益と法人税の状況も踏まえて判断する必要があるため、税理士によく相談してから利用するのがおすすめです。
助成金・補助金による調達
助成金や補助金は返済不要である点が魅力ですが、募集内容や審査基準、申請手続きなどが複雑です。
採択されれば資金負担を軽減できる反面、実際に入金されるまでに時間がかかるため、事業内容によっては立て替え資金を準備する必要もあります。
経済産業省の「ものづくり補助金」、地方自治体の「地域資源活用補助金」、日本商工会議所の「小規模事業者持続化補助金」の例を取り上げ、共通して気をつけるべきポイントも含めて見ていきましょう。
経済産業省の「ものづくり補助金」
経済産業省の「ものづくり補助金」は、幅広い業種において新製品開発やサービス開発のための設備投資を支援する制度です。
採択されると返済不要の補助金が受け取れるため、新しい技術や製品を世に出そうとしている企業は、ぜひ検討してみましょう。
ただし、申請段階で事業計画書や投資内容、期待される成果などをしっかり作り込む必要があるほか、実際に交付されるまでには1ヵ月以上の期間を要します。
さらに、使途が限定され、自由度が低い点にも注意が必要です。
地方自治体の「地域資源活用補助金」
地方自治体の「地域資源活用補助金」は、地域の農産物や伝統技術の発展、観光資源の活用など、地域経済に貢献する事業を対象とした補助金制度です。
地方自治体によって具体的な対象事業や申請方法が異なるため、事前に詳細情報を収集し、要件に合致するか確認しておくことが大切です。
- 申請要件の確認
- 申請書類の準備
- 審査
- 採択決定
- 補助金受取
- 報告書提出
参考:東京都産業労働局「地域資源活用・都市課題解決のための助成」
日本商工会議所の「小規模事業者持続化補助金」
「小規模事業者持続化補助金」は、小規模事業者が販路拡大や業務効率化を目的に利用できる補助金の一つです。
採択率が比較的高いとされ、商工会議所の支援を受けながら申請書類を作ることができます。
- 申請要件の確認
- 申請書類の準備(事業計画や申請書など)
- 審査
- 採択決定
- 事業実施(補助対象経費の支払い)
- 報告書・補助金請求書の提出
ただし、補助金は後払いが基本です。
まずは、事業者が自力で資金を用意して取り組みを進め、そのあと実績報告書を提出して補助金を受け取る流れになります。
補助金額にも上限があるため、大がかりな投資には適さない場合がありますが、商工会議所からの助言が得られる点も含め、小さな事業者が比較的取り組みやすい制度といえます。
クラウドファンディングによる調達
多数の個人や投資家から資金を集めるクラウドファンディングには、下記3つのパターンがあります。
- 返済不要の寄付型
- 商品の予約販売に近い購入型
- 株式や配当などでリターンを行う投資型
クラウドファンディングは、SNSやプラットフォームを活用し、多くの支援者に存在を知ってもらえるなどのメリットがありますが、目標金額に達しないと資金を受け取れないなど、リスクもあります。
寄付型のクラウドファンディング
「寄付型のクラウドファンディング」は、資金提供者には対価を渡さず、社会貢献や非営利的な活動への賛同を得て資金を集める方法です。
- プロジェクトの企画・目的の設定(支援者に共感してもらえるような仕立てが必要)
- プラットフォームの選定
- プラットフォームでプロジェクトページ作成・公開
- 広報・PR活動
- 資金調達
- 活動報告
共感が得られると返済不要の大きな資金が集まるケースもありますが、規模の大きい資金調達には不向きです。
また、資金を受け取ったあとは、活動報告や結果の共有を丁寧に行わなければならなりません。
また、寄付金は課税対象となることがあり、税務上の取り扱いには注意が必要です。
購入型のクラウドファンディング
「購入型のクラウドファンディング」は。支援者から集めた資金に対して、自社の商品やサービスをリターンとして提供する仕組みです。
- プロジェクトの企画・目的、リターンの設定
- プラットフォームの選定
- プラットフォームでプロジェクトページ作成・公開
- 広報・PR活動
- 資金調達
- リターンの提供・送付
新商品の開発コストを先に集められるだけでなく、プロモーションやテストマーケティングを同時に行えるのがメリットです。
プロジェクトの話題性や独自性が高ければ、短期間で目標額を達成することもあります。
ただ、製品の完成が遅れたり品質に問題が発生したりすると支援者の信用を失いかねないため、スケジュール管理と支援者とのコミュニケーションが非常に重要です。
また、購入型クラウドファンディングは販売取引として取り扱われるため、消費税やその他税金が発生する場合がある点には注意しましょう。
投資型のクラウドファンディング
「投資型のクラウドファンディング」は、株式の持ち分や配当、あるいは事業への投資による利息をリターンとして提供する方式で「エクイティ型」とも呼ばれています。
- 事業計画の策定
- プラットフォームの選定
- プラットフォームでプロジェクトページ作成・公開
- 投資家募集活動
- 資金調達
- 投資家への定期的な報告、リターン(株式買取、配当、利息など)の支払
投資家からするとハイリスク・ハイリターンの要素が強いため、集まる金額が大きくなる可能性があります。
ただ出資を受けた企業としては、株主構成が変わる、あるいは配当を行うなど、経営上の負担が生じる点も考慮する必要があります。
数億円規模の調達に成功した事例もあり、スタートアップ企業やIPOを目指す企業など、急拡大を目指す場合に向いている方法です。
うまく資金調達するためのポイント
企業の資金調達には多彩な手段があり、それぞれメリット・デメリットが異なります。
どの方法を選ぶにしても、「資金調達の目的を明確化する」「調達コストと税金のリスクを考える」など、いくつか注意すべきポイントがあります。
調達をスムーズに進めるうえで、押さえておくべきポイントを4つ紹介します。
資金調達の目的を明確化する
資金を調達する際は、「何のために資金調達が必要なのか」を明確にしましょう。
企業が資金を必要とする理由はさまざまで、運転資金の確保や設備投資、資金繰りの改善、財務体質の強化などが考えられます。
目的によって、必要額や調達方法も異なります。
必要性をはっきりさせずに「とにかくお金を集めたい」というスタンスで動くと、かえって利息や手数料を余分に支払うことになったり、将来の返済に追われたりする可能性が高まります。
まずは、調達目的と必要金額をきちんと洗い出すことが大切です。
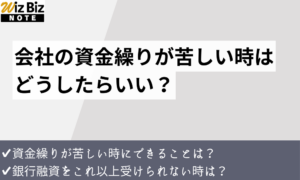
資金調達に活用できる資産がないか確認する
不動産や動産・在庫があるなら、アセットファイナンスで活用できるものがあるかどうか確認してみましょう。
必ずしも、借入や増資に頼らなくても資金繰りを改善できるケースがあります。
遊休資産を売却して維持コストを減らしつつまとまった現金を得たり、ファクタリングを活用して売掛金を即座に資金化したりすることで、新たな投資に回すチャンスも増えるでしょう。
不要な固定資産があるなら、そのまま保有するより財務バランスを見直したほうがよい場合もあるため、事業計画と合わせて検討してみることが大切です。
資金調達コストと税金への影響を確認する
資金調達を行う際には、必ず資金調達コストと税金への影響を確認しましょう。
借入金には利息が発生し、社債やリースには発行費用やリース料がかかるなど、調達方法ごとに必要なコストが異なります。
また、資産を売却すると売却益や売却損が計上され、法人税額に影響が出るかもしれません。
資金調達を上手に行うためには、表面的な金利や手数料だけではなく、中長期的なキャッシュフローと税金を合わせてシミュレーションしておくことが重要です。
税理士や公認会計士など専門家のアドバイスを得ながら、最適な調達手段を判断するとリスクを抑えやすくなるでしょう。
事業計画を作成する
どの資金調達を選んでも、「返済可能性」や「投資価値」を証明しなければならないため、まずは「事業計画」を策定しましょう。
融資であれば「返済原資をどう生み出すか?」、株式発行なら「どのように事業を成長させて出資者のリターンを確保するか?」を説明しなければなりません。
売上と利益をいくら伸ばせるのか、何年かけてどれだけの返済(あるいは配当)が可能かなどを数字で示すことで、調達がスムーズに進む可能性が高まります。
逆に計画を練らずに手当たり次第に資金を借りると、返済トラブルや経営の行き詰まりにつながるリスクが大きくなります。
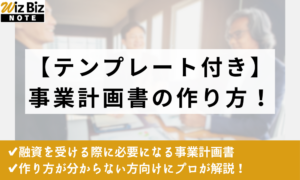
企業規模別でおすすめの資金調達方法
会社の規模や従業員数、売上高などによっても、向いている資金調達方法は違ってきます。
ここでは従業員数をひとつの目安として、3つのパターンでおすすめの資金調達方法をご紹介します。
従業員50名以下の小規模事業者
事業規模が小さい場合は、審査が複雑な大口融資よりも、以下のような手段が活用しやすいでしょう。
- 日本政策金融公庫の融資(最大7,200万円程度まで)
- ビジネスローン(短期間で数百万円〜数千万円)
- 小規模事業者持続化補助金など補助金・助成金(返済不要だが上限200万円程度が目安)
- クラウドファンディング(購入型なら数百万円程度までが中心)
なかでも、ビジネスローンは比較的審査が早く、創業前後の企業でも利用できる場合が多いでしょう。
補助金は採択までに時間がかかりますが、返済義務がないため、売上が不安定になりがちな小規模事業者におすすめです。
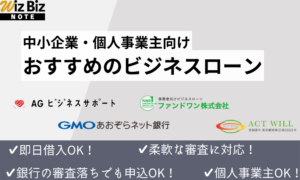
従業員300名以下の中規模事業者
売上高や社員数が増え、ある程度の実績を積んでいるなら、銀行融資やVC・CVCとの出資交渉、アセットファイナンスを検討しましょう。
運転資金は売掛債権の売却(ファクタリング)で補い、設備投資には銀行融資を利用するなど、複数の調達手段を組み合わせる企業も少なくありません。
ただし、大きな投資の資金をすべてVCに頼ると、株式の希薄化によって経営の自由度を失いかねません。
銀行との関係を深め、必要額を融資でまかなう方法もあわせて検討するとよいでしょう。
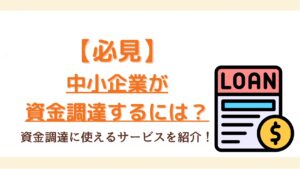
従業員1,000名前後の事業者
企業規模がさらに大きくなると、銀行融資はもちろん、社債の発行によって大規模な設備投資などが行えるようになります。
増資をすれば、自己資本比率を高めて財務体質を強化でき、将来的に株式上場も目指せるでしょう。
ただし、増資で外部出資者が入る場合は、議決権や配当方針などの調整が必要になるため、経営の自由度と資本増強のバランスを慎重に考える必要があります。
資金調達の手段を複線化しておくとリスクが分散され、安定したキャッシュフローを確保できる体制を築きやすくなります。
起業時におすすめの資金調達方法
創業前後の企業は実績が少ないため、資金調達で苦労するケースも多いでしょう。
起業時は、日本政策金融公庫や自治体の制度融資をはじめ、補助金・助成金、さらにはベンチャーキャピタルやクラウドファンディングなどの方法を、上手に組み合わせていきましょう。
日本政策金融公庫の新規開業資金
日本政策金融公庫には、創業期の事業者に特化した商品が数多く用意されています。
無担保・無保証で借りられる制度や、女性やシニア層が優遇される制度など、民間金融機関にはないメリットがあるのが特徴です。
- 事業計画を策定して窓口に相談
- 必要書類を提出して審査を受ける
- 融資実施
ただし、申し込みから融資実行までに時間がかかる点には注意しましょう。
金利も低めに設定されており、設備投資では最長20年の返済期間が認められるため、起業時には最初に検討しておきたい手段の一つです。
国や地方公共団体の補助金・助成金
創業時は、国や自治体が提供する返済不要の補助金を検討してみましょう。
たとえば、小規模事業者向けの創業支援補助金や、IT導入補助金、地域特化の助成金などが該当します。
- 申請要件を確認し、申請に必要な書類を準備する
- 国や地方公共団体に提出
- 審査が通れば補助金・助成金が支給される
採択までに時間がかかり、要件が限定されることも多いですが、審査に通れば返済義務がないため、資金繰りを大幅に改善できる可能性があります。
募集期間が設けられていることや、経費精算が後払いになるなど精度が複雑であるため、自治体とよくコミュニケーションをとっておくのがポイントです。
ベンチャーキャピタル(VCまたはCVC)の出資・融資
将来的に大きな事業成長が見込める企業であれば、VCやCVCからの出資を受けるのも選択肢の一つです。
投資家から厳しい要求を受けることもありますが、経営ノウハウのアドバイスが受けられたり人脈を広げられるチャンスがあったりするのは、ベンチャーキャピタルならではのメリットといえます。
- 事業計画を策定し、その業種に成長支援ができそうなベンチャーキャピタルを選定
- 条件交渉などを行い、審査を受ける
- 審査が通れば出資金または融資として資金調達ができる
ただし、株式を渡すことで議決権比率が変わり、将来的にIPOやM&AによるEXITを求められる場合もあるため、スピード感を持った成長戦略を描く必要があります。
融資という形をとる場合もありますが、多くは出資という手段が取られます。
クラウドファンディングによる調達(購入型)
新商品や新サービスを軸に企業するなら、購入型クラウドファンディングを利用し、テストマーケティングを兼ねて資金調達するのがおすすめです。
- プロジェクトの企画やリターンの設定を行い、プラットフォームにプロジェクトページ公開する
- 広報、PR活動を行い、幅広く支援者から資金を調達する
- リターンとして商品やサービスを返す
支援者は将来の製品やサービスを先行予約するようなイメージで資金を出し、その対価として完成品を受け取る流れです。
目標金額が達成できれば、在庫リスクを抑えてスタートを切りやすく、SNSやメディアでの話題づくりにもつながります。
ただし、リターンの提供が遅れたり品質面でトラブルが起きたりすると信用を損ねるため、開発スケジュールやコミュニケーションは慎重に管理する必要があります。
資金調達の方法まとめ
企業が資金を調達する方法には、借入や出資、自社資産の現金化や助成金など、さまざまな方法があります。
事業規模や成長ステージ、必要額や返済能力などによって適切な選択肢は変わるため、それぞれの特徴をよく理解し、複数の方法を組み合わせることが理想です。
目的や返済計画をしっかり定め、事業計画を明確に示すことができれば、銀行や投資家、公的機関などとの交渉がスムーズに進み、不要な負担やリスクも避けられるでしょう。