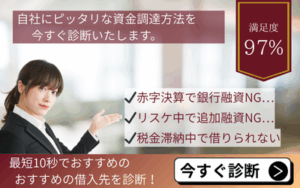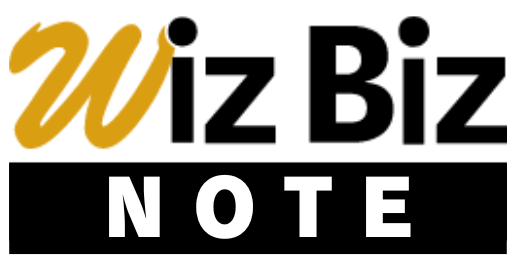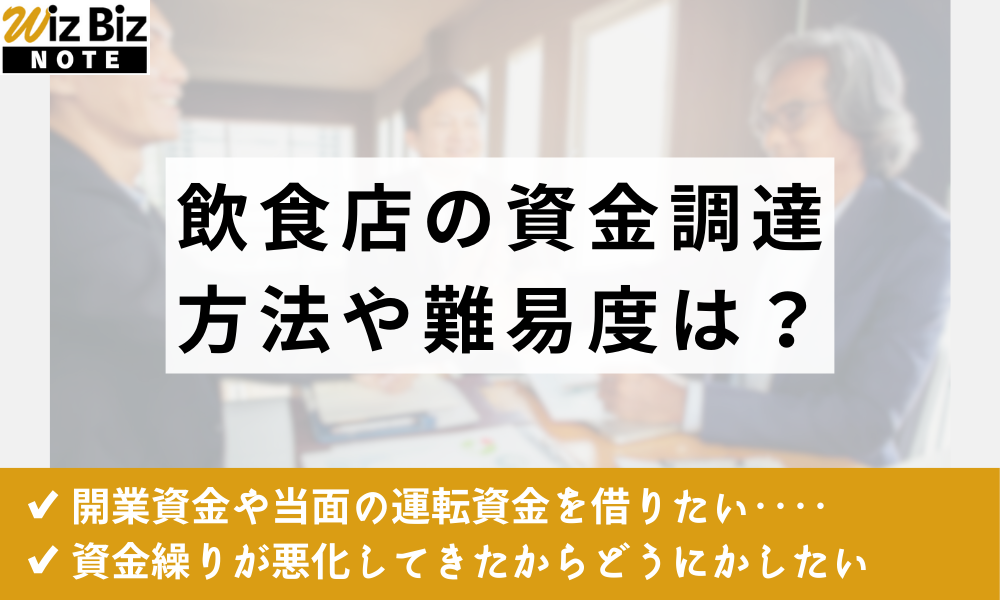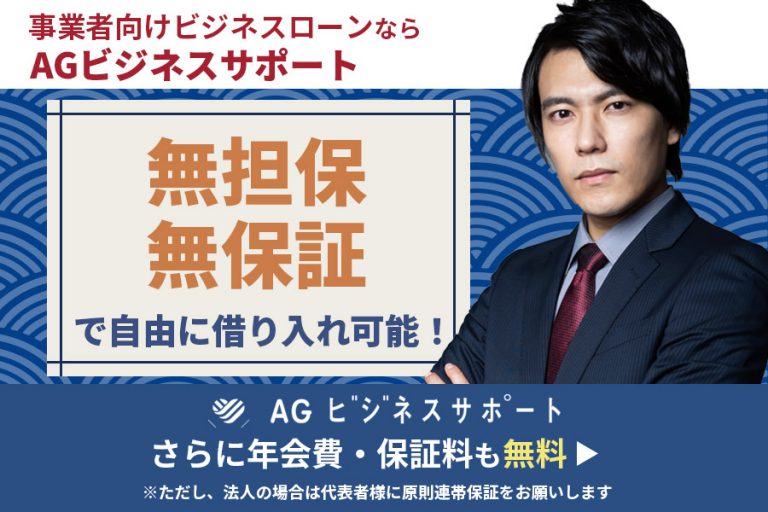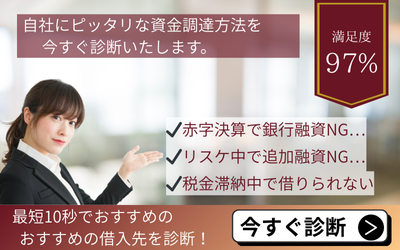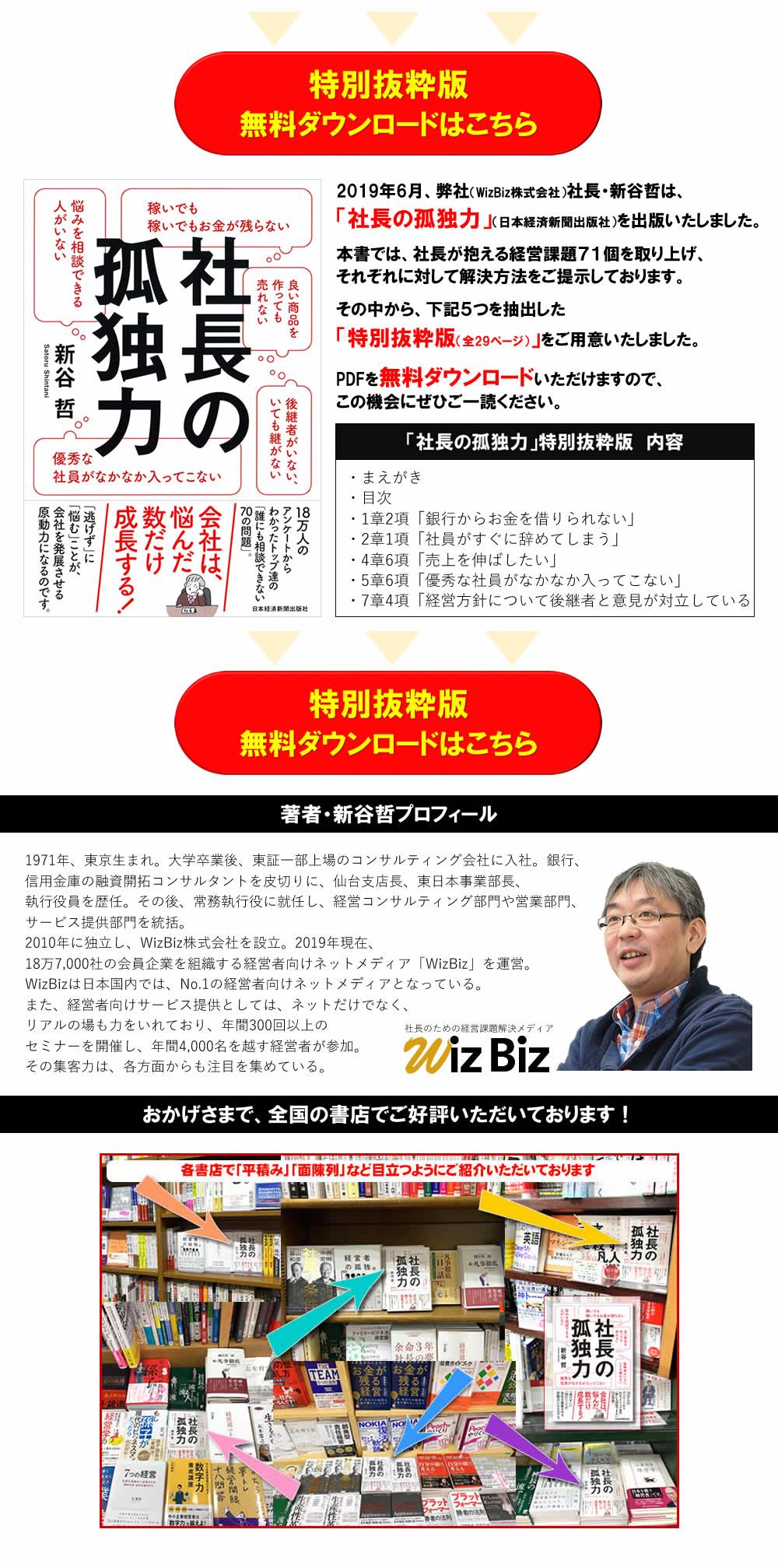飲食店経営では、開業時の設備投資や運転資金、予期せぬ売上低下など、さまざまな局面で資金調達が必要になることがあります。
今回は、日本政策金融公庫や信用保証協会、そして助成金やクラウドファンディングなど、飲食店経営者におすすめの資金調達方法をいくつかご紹介します。
それぞれのメリットやデメリットも含めてわかりやすく解説しますので、これから飲食店を開店する人も、経営を安定させたい人もぜひ参考にしてください。
【最短即日・個人事業主もOK!】
資金繰りに困ったら「AGビジネスサポート」の無担保ビジネスローンがおすすめ。
銀行融資ではないため、銀行融資を断られた方でもビジネスローンを組める可能性は非常に高いです。
また、AGビジネスサポートなら原則無担保・無保証で即日融資を受けることができます!
※AGビジネスサポートは法人・個人事業主を対象としたビジネスローンです。
| まとまった金額の借入なら ビジネスローンがおすすめ! | 売掛金があるなら ファクタリングがおすすめ! |
|---|---|
AGビジネスサポート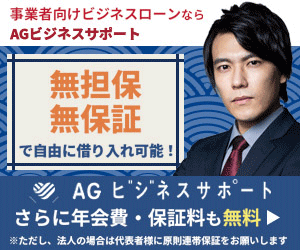 | QuQuMo |
| 柔軟な審査ですぐに事業資金を融資してもらう方法 | 売掛金や請求書を買い取ってもらい現金化する方法 |
| 融資まで 最短即日 | 入金まで 最速2時間 |
| 申込〜入金 来店不要! | 申込〜入金 来店不要! |
| 融資限度額 50万円〜1,000万円 | 買取限度額 上限なし |
| 金利 年3.1%〜18.0% | 手数料 1%〜14.8% |
| 利用者※1 法人(赤字でもOK!) 個人事業主 | 利用者 法人(売掛金があればOK!) 個人事業主 |
| 必要書類※2 本人確認書類 決算書などのみ! | 必要書類 請求書 通帳の2点のみ! |
| 無担保無保証で借入可能!※3 | 取引先への通知なし! |
| AGビジネスサポート 公式サイトから今すぐ申込 | QuQuMo 公式サイトから今すぐ申込 |
※2:法人→代表者本人を確認する書類・決算書・その他必要に応じた書類
※2:個人事業主→本人を確認する書類・確定申告書・所定の事業内容確認書・その他必要に応じた書類
※3:原則不要。法人の場合は原則代表者が連帯保証

1971年東京生まれ。大学卒業後、東証一部上場のコンサルティング会社に入社。銀行、信用金庫の融資コンサルタントを皮切りに、仙台支店長、東日本事業部長、執行役員を歴任。その後、常務執行役に就任し、経営コンサルティング部門や営業部門、サービス提供部門を統括。2010年に独立しWizBiz株式会社を設立。現在、経営者向けネットメディア「WizBiz」を運営。国内では経営者の会員登録数でNo.1のメディアとなっている。また、経営者向けサービス提供としては、ネットだけでなく、リアルの場も力をいれており、年500回以上のセミナーを開催し、4000名を越す経営者が参加。18万人の社長アンケートから1000個の悩みを回収。
著書:社長の孤独力
飲食店で資金調達が必要なケース
飲食店経営をしていると、さまざまな局面で資金が必要になることがあります。
開業時には多額の初期費用がかかり、営業中も仕入れや人件費といった運転資金が必要になるでしょう。
売上不振や外的要因による赤字など、予期せぬ事態への備えとして資金調達が必要になることも少なくありません。
想定されるケースを事前に把握し、資金を確保する方法を考えておくことが大切です。
開業資金を調達するケース
飲食店を開業するには、物件取得費や内装工事費、厨房機器などの初期投資に加え、当面の運転資金も確保しなければいけません。
十分な資金を用意しておけば、開業初期の不安定な売上にも対応でき、スムーズな事業運営が可能になります。
【開業時に必要な資金の目安(一般例)】
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 物件取得費(保証金・礼金など) | 100〜300万円 |
| 内装・外装工事費 | 300〜1,000万円 |
| 厨房機器・設備費 | 100〜500万円 |
| 初期仕入れ・備品費 | 50〜100万円 |
| 広告宣伝費 | 10〜50万円 |
| 運転資金(最低3ヵ月分) | 100〜300万円 |
| 合計目安 | 約700〜2,000万円 |
都心部や駅近物件で開業する場合は、上記よりもさらに高額になるケースもあります。
一方で、居抜き物件を活用すれば、初期投資は抑えられるでしょう。
ちなみに、日本政策金融公庫の創業融資制度では、上記の金額を用意することを前提に審査が行われています。
【関連記事】
個人で開業資金を調達するおすすめの方法は?いくら必要?
運転資金を調達するケース
飲食店の営業を継続するには、毎月の固定費や仕入れなど、運転資金の確保も必要です。
売上が減少したり、原材料費や人件費が高騰したりすることもあり、予備の資金は確保しておく必要があります。
黒字経営であっても、売上増加に伴う仕入れや人件費の増大に対応するため、追加の運転資金が求められるケースもあります。
【小規模店舗における月次運転資金の目安】
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 家賃 | 10〜30万円 |
| 人件費(社員+アルバイト) | 15〜30万円 |
| 食材などの仕入れ費 | 15〜20万円 |
| 光熱費 | 3〜8万円 |
| その他経費(広告・雑費) | 1〜5万円 |
| 合計の目安 | 約50〜100万円 |
一般的には、上記金額×3ヵ月分を、運転資金として確保しておくのが理想です。売上低迷などのリスク対策だけではなく、積極的に店舗展開を試みるタイミングでも運転資金は必要になってくるでしょう。
日々の資金繰りを見える化し、必要に応じて早めに資金調達の準備を進めることが大切です。
赤字補てんで資金調達するケース
飲食店が赤字になったタイミングでも、適切なタイミングで資金調達ができれば、再起を図ることができます。
- 赤字が一時的で回復の見込みがある場合
- 数ヵ月後に支払い資金が不足することが明らかなとき
- 借入返済や支払が継続できず、リスケなどの対策が必要となる場合
赤字になった時は、いかに早く対策するかが重要です。
資金繰り表などの数値をもとに、資金ショートのリスクを客観的に把握し、必要に応じてリスケジュールや融資申請を行いましょう。
【関連記事】
事業の資金繰りが苦しい時にすべきこと・してはいけないこととは?資金ショートせず倒産回避をする方法
飲食店におすすめの資金調達方法【開業時】
飲食店の開業にあたっては、物件取得や設備投資、広告宣伝など多くの初期費用が発生します。
これらを自己資金だけでまかなうのは難しく、金融機関の融資制度や公的支援を活用する経営者がほとんどです。
飲食店の開業時における資金調達方法には、どのようなものがあるか詳しく見ていきましょう。
日本政策金融公庫の創業融資
日本政策金融公庫は、政府が100%出資する公的金融機関であり、特に中小企業や個人事業主、創業者への融資に積極的です。
物件取得費や内装工事費・運転資金目的など、幅広く対応してもらえるため、開業時には最初に検討したい金融機関といえます。
また、民間の金融機関と異なり、実績のない創業者でも借りやすく審査も比較的柔軟です。
申込みに際しては、必要書類(事業計画書、資金計画書など)を揃えたうえで、最寄りの公庫や金融機関への相談からはじめましょう。
そのあと、面談・審査を経て契約・融資実行となります。申請から融資実行までに1ヵ月以上かかるケースもあるため、早めの準備が不可欠です。
【日本政策金融公庫の創業融資メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・金融機関の融資と比較して、審査基準が柔軟で融資を受けやすい ・低金利で利用できる ・返済期間が長いため毎月の返済負担が少ない | ・面談を経て融資が行われるため、資料の用意など早めの準備が必要 ・実現可能性の高い事業計画書が必要。綿密な計画書の作成には時間と労力がかかる |
【関連記事】
日本政策金融公庫の審査は厳しい?審査通過のために意識すべきポイントを解説
信用保証協会の創業融資
信用保証協会による創業融資は、信用保証協会の保証が付いているため、創業間もない事業者でも資金を借りやすいのが特徴です。
ただし、創業融資では、自己資金の有無や金額が審査に影響を及ぼす場合があります。
申込額の10分の1程度の自己資金が必要な融資もあるため、ある程度の自己資金は用意しておきましょう。
保証付き融資を利用する際は、はじめに金融機関に相談し、協力を得ながら事業計画書を作成します。
そのあと、金融機関と保証協会の両方の審査を経て、保証が承諾されると融資が実行されます。なお、保証料が別途発生する点や、融資までに時間を要する点については注意が必要です。
【信用保証協会の創業融資メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・協会の保証があることで、事業実績のない創業者でも融資が受けやすい ・創業時期や事業規模、業種などに合わせたさまざまな保証制度が用意されている | ・融資実行時に所定の保証料を差し引かれる。 ・融資実行までに時間がかかる場合がある(金融機関と信用保証協会の両方の審査が必要となるため) |
【関連記事】
個人事業主は信用金庫で融資を受けられる?審査に通りやすくなるコツや注意点とは?
地方自治体の創業者向け制度融資
地方自治体の創業者向け制度融資は、地域の経済活性化を目的としたもので、信用保証協会と連携した商品が多数提供されているのが特徴です。
自治体が保証料や利子の一部を補助してくれるケースが多く、創業時においても資金調達はしやすいでしょう。
利用する場合は、はじめに自治体へ相談し、保証協会の審査を経てから金融機関による審査へ進む流れとなります。
保証承諾さえ得ることができれば、基本的に金融機関の審査で落ちることはありません。
ただし、融資実行までの期間が長くなる点には注意が必要です。制度によっては利用限度額が制限されている場合もあるため、ほかの融資と合わせて利用することも検討しておきましょう。
【地方自治体の制度融資メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・自治体の支援があるため、実績のない創業者でも融資を受けやすい ・保証料や利子補給の優遇を受けられる場合がある(自治体によって取扱いは異なる) | ・融資額が低い ・融資実行までに時間がかかる |
助成金(補助金)
助成金や補助金は、国や自治体が特定の条件を満たす事業者に対して支給する、返済不要の資金です。
飲食店向けにも、設備導入や雇用創出など、目的に応じた制度が多数用意されています。ただし、多くは「後払い方式」であり、まず自己資金で費用を立て替える必要がある点には注意が必要です。
さらに、採択制のため申請しても必ず受給できるとは限らず、申請書の記載内容や事業内容の社会的意義が重視されます。
行政書士など専門家のサポートを受ける必要もあり、手続きには時間がかかる点がデメリットです。
【助成金(補助金)メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・返済不要(資金繰りを圧迫しない) ・自己資金の補填に利用できる | ・採択(審査)制のため、必ず利用できる訳ではない。 ・申請書類や実績報告が煩雑で手間がかかる |
飲食店におすすめの資金調達方法【追加の運転資金確保したい時】
飲食店を運営していると、急な売上減や原材料費の高騰、人件費の上昇などにより、一時的に運転資金が不足することがあります。
このような「追加の運転資金を確保する場合」で使える資金調達方法についても詳しく見ていきましょう。
日本政策金融公庫の制度融資
日本政策金融公庫では、追加の運転資金に使える制度融資を多数用意しています。低金利かつ長期返済が可能で、返済負担も軽いのが特徴です。
ただし、申請には明確な資金使途と収支根拠を示す必要があり、確定申告書や試算表、資金繰り表などの書類を準備しなければいけない点は覚えておきましょう。
【日本政策金融公庫の制度融資】
| 融資限度額 | 最大4,800万円 |
|---|---|
| 返済期間 | 最長7年(据置期間あり) |
| 金利 | 年1.5~2.0%(固定金利) |
| 融資対象 | 財務・事業計画重視、創業後間もない企業も可 |
| 資金使途 | 人件費・仕入・光熱費など運転資金全般 |
【メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
| ・低金利かつ固定金利で資金調達が可能・返済期間が最長7年であり、毎月の返済が軽く済む | ・財務状況によっては融資を受けられない・明確な資金使途を示す必要があり、提出書類も多い |
参考:日本政策金融公庫融資のご案内
信用保証協会の保証付き融資
信用保証協会の保証付き融資でも、追加の運転資金調達に利用できる融資が用意されています。無担保でも最大8,000万円までの融資が受けられるため、資金に余裕を持たせることもできるでしょう。
【信用保証協会の保証付き融資】
| 融資限度額 | 一般枠:最大2億8,000万円(無担保は8,000万円) |
| 返済期間 | 通常5〜7年(制度により変動) |
| 金利 | 年2.0〜3.0%前後+保証料(0.45〜2.0%) |
| 審査 | 金融機関+協会の二重審査 |
| 資金使途 | 運転資金全般(仕入・人件費・光熱費など) |
【メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・審査が柔軟(中小事業者支援が目的のため) ・利用実績を積み重ねることで継続的に融資が受けられる | ・信用保証料がかかる ・金融機関と協会両方の審査に通過する必要がある(時間がかかる) |
銀行・信用金庫のプロパー融資
銀行や信用金庫から直接借りる「プロパー融資」を利用する方法もあります。
ただし、プロパー融資は審査が厳しく、資金使途や財務の健全性が求められるため、営業実績に乏しい飲食店だと融資を受けるのは難しいかもしれません。
【プロパー融資】
| 融資限度額 | 数百万円~数千万円(信用力による) |
|---|---|
| 返済期間 | 通常3〜7年 |
| 金利 | 年1.0〜3.0%(業況と信用により変動) |
| 審査 | 財務内容を重視した厳格な与信審査 |
| 資金使途 | 運転資金・設備資金など自由度が高い |
【メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| メリット | デメリット |
| ・業績好調で信用力があれば、高額融資を受けられる可能性がある ・銀行単独で融資可否を判断するため、融資実行までは比較的早い | ・審査が厳しい(信用力のない事業者に融資することはない) ・信用力の乏しい事業主は厳しい貸付条件を提示される |
【関連記事】
銀行融資の審査は厳しい?審査基準や通過率を上げるためのコツを法人融資のプロが解説
ノンバンクのビジネスローン
ノンバンクによるビジネスローンは、審査が柔軟かつスピーディで、金融機関の審査に通らない飲食店でも借りやすいのが特徴です。
ただし、金利は高いため、あくまで短期資金としての利用を心がけましょう。
【ノンバンクのビジネスローン】
| 融資限度額 | 数十万~500万円程度 |
|---|---|
| 返済期間 | 最長1〜3年程度 |
| 金利 | 年5.0〜18.0%前後(商品により変動) |
| 審査 | 業績よりも資産や返済実績を重視、即日対応可 |
| 資金使途 | 緊急資金・つなぎ資金などに限定されがち |
【メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・即日融資も可能 ・業況が芳しくない場合でも柔軟に審査してもらえる | ・金利が高い ・利用額が少額 ・必要額を調達できない場合がある |
【関連記事】
ビジネスローンのおすすめ20選比較ランキング!即日低金利で事業資金を借りられるところは?
飲食店におすすめの資金調達方法【資金繰りが悪化した時】
飲食店を経営していると、資金繰りが急に悪化することがあります。
そうした緊急事態においては、融資に頼るだけではなく「融資条件の変更依頼※リスケ」や、ファクタリングなど、ほかの方法も検討しておくと良いでしょう。
資金繰りが悪化した場合に使える、4つの資金調達方法についてもご紹介します。
リスケジュール
リスケジュール(リスケ)とは、返済期限の延長など、融資の条件を一時的に変更してもらい資金繰りを改善する手法です。
代表的な方法としては、「元金返済の猶予」や「返済期間の延長」などがあります。
ただし、リスケは金融機関と交渉しながら進める必要があり、確実に応じてもらえるとは限りません。
また、今後の返済計画を厳しく見られるため、資金繰り表や改善計画書の準備も必要です。リスケ実施中は新たな融資が受けられなくなるため、あくまで一時的な措置として捉える必要があります。
【メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・手元資金を確保できる ・信用悪化を最小限に抑えられるため倒産危機を免れる | ・新たな借入ができない(リスケ中は、金融機関からの融資は難しい) ・リスケを続けると、一括返済を求められる場合がある(改善されないと金融機関に判断された場合) |
リースバック
リースバックとは、保有している不動産や設備などの資産をいったんリース会社に売却し、売却益を得たあとリース契約を結んで設備を継続使用する方法です。飲食店の場合は、物件や厨房機器を対象とするケースが多く、金融機関からの融資が難しい場合に検討できるでしょう。
ただし、資産価値がないと十分な金額を調達できないこともあり、売却後はリース料という新たな固定費も発生します。実行に際しては、キャッシュフローとのバランスを慎重に見極めることが重要です。
【メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・資産があれば手軽に資金調達ができる ・固定資産税や保険料の支払いがなくなるためキャッシュフローの改善につながる | ・資産価値によっては、希望額を用意できない ・リース料が発生する |
ファクタリング
ファクタリングとは、売掛金をファクタリング会社に売却し、手数料を差し引いた金額を早期に受け取る資金調達の方法です。最短即日で資金調達ができるため、売掛金の入金タイミングよりも早く資金を得られるというメリットがあります。
ただし、現金商売が多い飲食業では売掛金自体が少ないことが多く、利用は限定的です。また手数料も高いため、あくまでも短期的な資金調達で使うのが賢い利用方法といえます。
【メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・急な資金需要に対応できる ・業況に影響されることなく資金調達が可能(売掛先の信用度のみがチェックされるため) | ・銀行融資と比較すると手数料が高い ・売掛金がないと利用できない(現金商売である飲食業は売掛金が少ないため) |
公的支援(セーフティネット)の利用
セーフティネット保証制度や、政府系金融機関の特別貸付制度など、公的支援を受ける方法もあります。
セーフティネット保証制度では、売上が減少している事業者を対象に、低金利や元金据置期間のある融資が多数提供されています。ただし、申請条件は厳しく申請手続きにも多くの書類が必要なため、早めの情報収集と準備が必要です。
利用を検討しているなら、まずは市区町村の産業振興課や商工会などへ相談してみましょう。
【メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・金融機関の融資に比べて金利が低い(無利子の場合もある) ・返済期間が長い ・元金据置期間の利用も可能 | ・要件が厳しく利用できない場合がある ・申請から融資の申込みまで必要書類も多く、手続きが煩雑 |
飲食店が融資で資金調達をする際にすること
飲食店が融資を通じて資金調達を行う際は、事前に準備しておくポイントがいくつかあります。自己資金の準備や事業計画書の作成、適切な融資先の選定など、最低限「経営者として準備しておくこと」は押さえておきましょう。
自己資金を用意する
融資を受ける際、金融機関は「自己資金をどの程度用意しているか?」を必ずチェックします。経営者の本気度を示すためにも、ある程度の自己資金は準備しておきましょう。自己資金を事業に投じることで、経営者としての意気込みも伝わり、金融機関からの信頼も得られます。
さらに、自己資金は返済能力の裏付けともなります。事業が計画通りに進まなかった場合でも、一定の備えがあれば損失を軽減できるという判断材料になり、審査ではこのような「耐性」も評価対象です。
制度融資では自己資金の明確な要件が設けられていないケースもありますが、実際には自己資金があれば審査は有利に進みます。
事業計画書の作成
事業計画書は、金融機関に対して「返済根拠」を示すための重要資料です。単に理想やビジョンを述べるだけではなく、数値や戦略に基づいた実現可能性の高い計画を示す必要があります。
事業計画書を使って、「どのように売上を上げるのか」「どれだけの利益が見込まれるのか」「返済原資は何か」などを具体的に示すと良いでしょう。これにより、金融機関は貸し倒れのリスクを客観的に判断できます。
飲食店は、立地やメニュー構成、価格帯や集客方法などにより売上が左右されるため、事業計画書でそれぞれを論理的に説明できれば、事業の将来性も理解してもらいやすいでしょう。
収支計画では、開業後の売上予測や利益見込みを記載し、中期的な資金管理能力もアピールする必要があります。赤字が出る想定月や資金が足りなくなるタイミングにどう対応するかといった記述があると、審査担当者の印象も良くなるでしょう。
【関連記事】
【テンプレートつき】事業計画書の作り方をプロが解説!融資時に見られるポイントとキャッシュフローの見直し方
融資申込み先の選定
融資の申込先によって、審査基準や貸付条件は大きく異なります。そのため、店舗規模や経営状況、資金使途に応じた金融機関を選ぶことが非常に重要です。
例えば、創業間もない飲食店の場合は、融資のハードルが低い日本政策金融公庫の融資がおすすめです。信用力が高ければ、高額を低金利で借りられるプロパー融資を検討しましょう。赤字に陥っている場合は、信用保証協会の保証が得られる保証付き融資がいいかもしれません。
また、金融機関ごとに「得意とする業種」がある点にも注意が必要です。ある信用金庫は地域の飲食店支援に注力しているが、別の金融機関ではIT業向けの制度しか扱っていないといったケースがあります。
こうした情報は、各金融機関のサイトや商工会議所で得られることも多いため、情報収集にも努めましょう。
さらに、融資後の相談対応など、「ソフト面の支援があるか?」も融資先選定の重要なポイントです。金利や融資額だけで比較するのではなく、今後の取引パートナーとして信頼できる金融機関かどうかを見極めることが大切です。
飲食店経営者におすすめなその他の資金調達方法
飲食店が資金調達を検討する際、融資以外にもさまざまな選択肢があります。クラウドファンディングや親族・知人からの借入、さらにはエンジェル投資家からの出資など、いくつかの方法を見ていきましょう。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、インターネット上で新規開業や商品開発などのプロジェクトを立ち上げ、支援者から資金を募る資金調達方法です。支援者は、食事券や限定メニューなどのリターンが得られるというメリットがあります。
自己資金を抑えて資金を調達できるうえ、開業前から集客につなげるPR効果も期待されるため、積極的に活用してみましょう。ただし、ありきたりな施策やプランでは共感を得ることはできません。社会的意義や、独自性のあるアイデアを考える必要があります。
【クラウドファンディングのメリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・返済の必要がない ・プロジェクトを通じて多くの人に認知される(PR効果が期待できる) | ・目標金額に達しない場合がある ・手数料が発生する(プラットフォームの利用料や決済手数料などが必要) |
参考:クラウドファンディングのMAKUAKE「プロジェクトの掲載を申し込む」
親族や知人からの借入
親族や友人、知人などから資金を借りる方法もあります。金利や返済期間などを当事者間で自由に設定できるため、無利息での借入や長期返済も可能でしょう。ただし、返済の遅延などによって人間関係が悪化するリスクがあるため、借用書は条件を記載しておく必要があります。
【クラウドファンディングのメリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・金利、返済期間、返済方法などを自由に設定できる ・金融機関のような審査や書類手続きが不要 | ・人間関係に悪影響を及ぼす可能性がある ・甘えが生じやすい |
エンジェル投資家からの出資
「エンジェル投資家」からの支援を受ける方法もあるでしょう。援助を受けられるケースは稀ですが、革新的な事業計画があり高い成長性が見込まれるなら、出資を受けることも可能です。
ただし、出資の見返りとして株式の一部を譲渡する必要があり、投資家が経営に関与してくる可能性がある点には注意しましょう。資金調達だけでなく、経営のノウハウを得られるメリットもある資金調達方法といえます。
【クラウドファンディングのメリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・返済義務がない ・信用力の向上が見込める(エンジェル投資家からの出資実績は、他の投資家や金融機関からの評価を高める可能性がある) | ・投資家の選定が難しい(飲食業界に理解のあるエンジェル投資家を見つけなければならない) ・経営に関与される可能性がある |
飲食店開業に必要な自己資金の目安
飲食店の開業には、物件取得費や内外装工事費、厨房設備の購入など、さまざまな費用がかかります。
これらの開業資金を、すべて借入でまかなうのは現実的ではありません。金融機関から融資を受ける際には、ある程度の自己資金は用意しておきましょう。
飲食店開業に必要な自己資金相場
飲食店を開業する場合は、一般的に「総開業資金の10~20%程度の自己資金」を用意するのが理想です。
10坪程度の小規模な店舗なら300万〜500万円程度の開業資金が必要で、そのうち50万〜100万円程度の自己資金を準備しておく必要があります。
【店舗規模別の開業資金と自己資金の目安】
| 店舗規模 | 店内面積 | 開業資金の目安 | 自己資金の目安 |
|---|---|---|---|
| 小規模 | 10坪程度 | 300~500万円 | 50~100万円 |
| 中規模 | 10~20坪程度 | 800~1,000万円 | 100~150万円 |
| 標準規模 | 20~30坪程度 | 1,000~1,500万円 | 150~200万円 |
信用保証協会の融資など、一部の融資では「創業資金の10分の1の自己資金要件」が設けられているケースもあります。
フランチャイズ(FC)を利用する場合の自己資金相場
フランチャイズ(FC)に加盟して開業する場合も、自己資金は必要です。
FCではノウハウ提供が得られるメリットがある一方で、加盟料や保証金などの初期費用が別途発生します。
店舗の取得費や内装工事、設備導入費用を加盟者自身が負担するケースもあるため、ある程度の自己資金は準備しておきましょう。
【FCに加盟する場合も自己資金目安】
| 業態 | 店内面積 | 開業資金の目安 | 自己資金の目安 |
|---|---|---|---|
| カフェなど | 10~15坪程度 | 800万〜1,500万円 | 100~150万円 |
| ラーメン・居酒屋など | 20~30坪程度 | 1,000万〜1,800万円 | 100~200万円 |
FC開業の際は、初期投資額が高額になることを想定し、目安より多めに自己資金を準備しておくと安心です。また、事前に本部と契約条件やサポート体制についても協議しておきましょう。
飲食店経営で資金繰りが悪化した時の対処法
飲食店の経営では、原材料高騰や感染症流行など、突発的な外的要因によって資金繰りが急に悪化することがあります。
経営危機を回避するために、飲食店が取るべき具体的な対処法についても見ていきましょう。
支出項目の見直し
資金繰りが悪化したタイミングでは、まず支出項目の棚卸しをしてみましょう。
仕入れ費用、人件費、家賃や広告宣伝費など、それぞれの支出がもたらす価値を精査し、優先度の低い項目から削減を検討しましょう。
- 仕入業者の見直しによる材料費のコストダウン
- 閑散時間帯の人員シフト調整による人件費削減
- 通信費や光熱費など変動費用削減
ただし、無理な経費削減はサービス品質の低下や従業員のモチベーション低下につながるリスクがあるため、慎重に見直しましょう。
収益力強化
支出削減だけでは根本的な経営改善につながらないため、同時に収益力の強化にも取り組むことが必要です。
顧客ニーズを再度リサーチし、限定メニューの導入やキャンペーンの実施なども検討してみましょう。
また、デリバリーなどイートイン以外の収益チャネルを確保することも、収益安定化の面では効果的です。空きスペースを活用したワークショップやイベント開催、キッチンカーによる移動販売なども検討してみましょう。
早いタイミングで金融機関へ相談する
資金繰りの悪化が見え始めたなら、できるだけ早く取引金融機関に相談するのがポイントです。悪化が表面化していない段階であれば、金融機関としても支援しやすいでしょう。
早めに相談すれば、追加融資やリスケ・保証付き融資制度の活用など、状況に応じさまざまな解決策も検討できます。
逆に、相談が遅れると打てる手が限られ、経営破綻に至るリスクも高まります。「資金繰りが苦しい」と感じた段階で、早めの相談を心がけましょう。
飲食店の資金調達でよくある質問
飲食店の資金調達に関しては、開業前後の自己資金の目安や、赤字での融資可能性など、さまざまな不安が出てくるものです。最後に、飲食店の資金調達でよくある質問についても見ていきましょう。
自己資金0円でも飲食店を開業できますか?
開業は可能ですが、リスクは高いでしょう。自己資金が0円の場合でも、日本政策金融公庫などでは審査通過できる可能性もあります。
しかし、金融機関は自己資金の額を見て「事業への意気込みはあるか?」や「計画性はあるか?」といった点を見ています。そのため、自己資金がないと審査に落ちるケースは少なくありません。
特に信用保証協会の創業融資などでは、申込額の10分の1程度の自己資金を要件とする商品もあります
。事業計画書には、「自己資金は手元に確保し予備資金として使う」という旨を記載しておくと、金融機関からの印象も良くなるでしょう。
赤字でも融資を受けられますか?
赤字でも融資を受けられる可能性はありますが、最も重視されるのは「返済能力があるかどうか」です。
赤字の内容が一過性であり、原因分析と回復の見込みが説明できるなら、融資が認められることがあります。
反対に、連続して赤字が続いていたり、赤字原因の要因を把握できていなかったりすると、「返済リスクが高い」と見なされ審査には落ちるでしょう。
赤字でも信頼されるためには、資金繰り表などを用いて「どう改善するか」を丁寧に説明することが必要です。
【関連記事】
赤字決算でも融資を受けられる?銀行・信金の融資審査に落ちたらどうすればいい?
飲食店の開業にはいくらの自己資金が必要ですか?
開業に必要な自己資金の額は、店舗の規模や立地、業態によって異なります。一般的には「開業資金全体の10%」程度を目安と考えておきましょう。
例えば、開業資金が1,200万円であれば、120万円程度の自己資金を用意しておくのが理想です。
日本政策金融公庫の融資は自己資金要件を明文化していませんが、保証協会を利用する場合は自己資金の条件が定められている場合もあります。
飲食店の運転資金はいくら用意しておくべきですか?
一般的には「月商の3ヵ月分」の運転資金を用意するのが理想です。
例えば、月商が100万円の店舗であれば、300万円程度の運転資金を確保しておくと安心でしょう。
また、プロパー融資であれば自己資金×1.5倍、信用保証協会融資であれば2.0倍が申込上限額の目安です。
飲食店は光熱費や仕入れ、家賃などの固定費が重いため、資金繰りに余裕を持たせるためにも、ある程度の余剰資金は確保しておきましょう。
個人事業主でも飲食店の事業資金調達は可能ですか?
はい、個人事業主でも問題なく融資を受けることは可能です。ただし、法人と比較して信用力が劣ると判断されるケースも多く、希望額によっては審査が通らないこともあります。
個人事業主が資金調達する場合は、下記のポイントを意識しておきましょう。
- 返済計画を盛り込んだ詳細な事業計画書を作成すること
- 自己資金をある程度確保しておくこと
- 金融機関との預金取引などで信頼関係を構築しておくこと
個人事業主であること自体はハンデではなく、事前準備次第で資金調達は十分可能です。
飲食店経営には資金調達に関する知識が重要
飲食店を経営する場合は、開業時や赤字対応など、あらゆる局面で資金調達が必要になることがあります。
さまざまな資金調達方法を知っておけば、いざという時でも慌てずに済むでしょう。
また、融資の手続きをスムーズに進めるためにも、普段から資金繰り表や事業計画書の作成など、準備も少しづつはじめておくのがおすすめです。
【最短即日・個人事業主もOK!】
資金繰りに困ったら「AGビジネスサポート」の無担保ビジネスローンがおすすめ。
銀行融資ではないため、銀行融資を断られた方でもビジネスローンを組める可能性は非常に高いです。
また、AGビジネスサポートなら原則無担保・無保証で即日融資を受けることができます!
※AGビジネスサポートは法人・個人事業主を対象としたビジネスローンです。