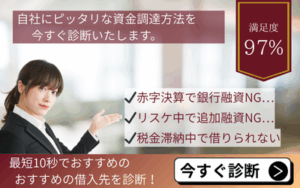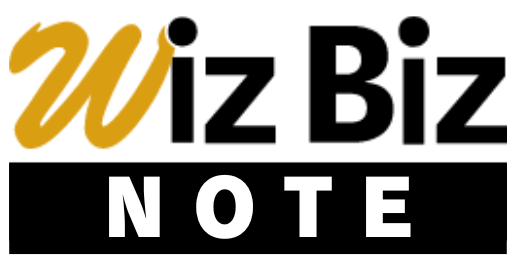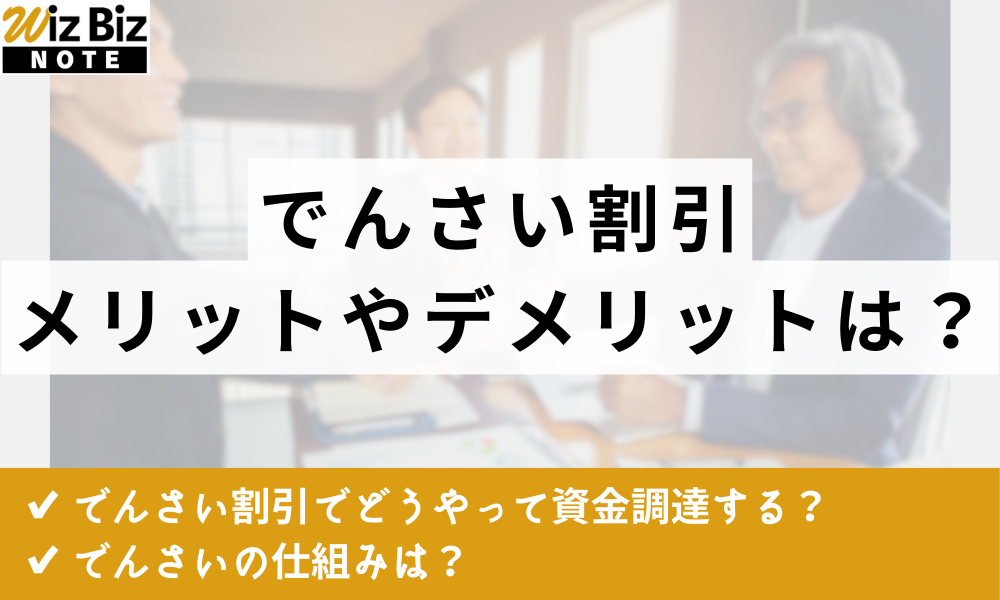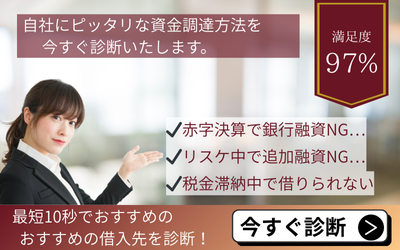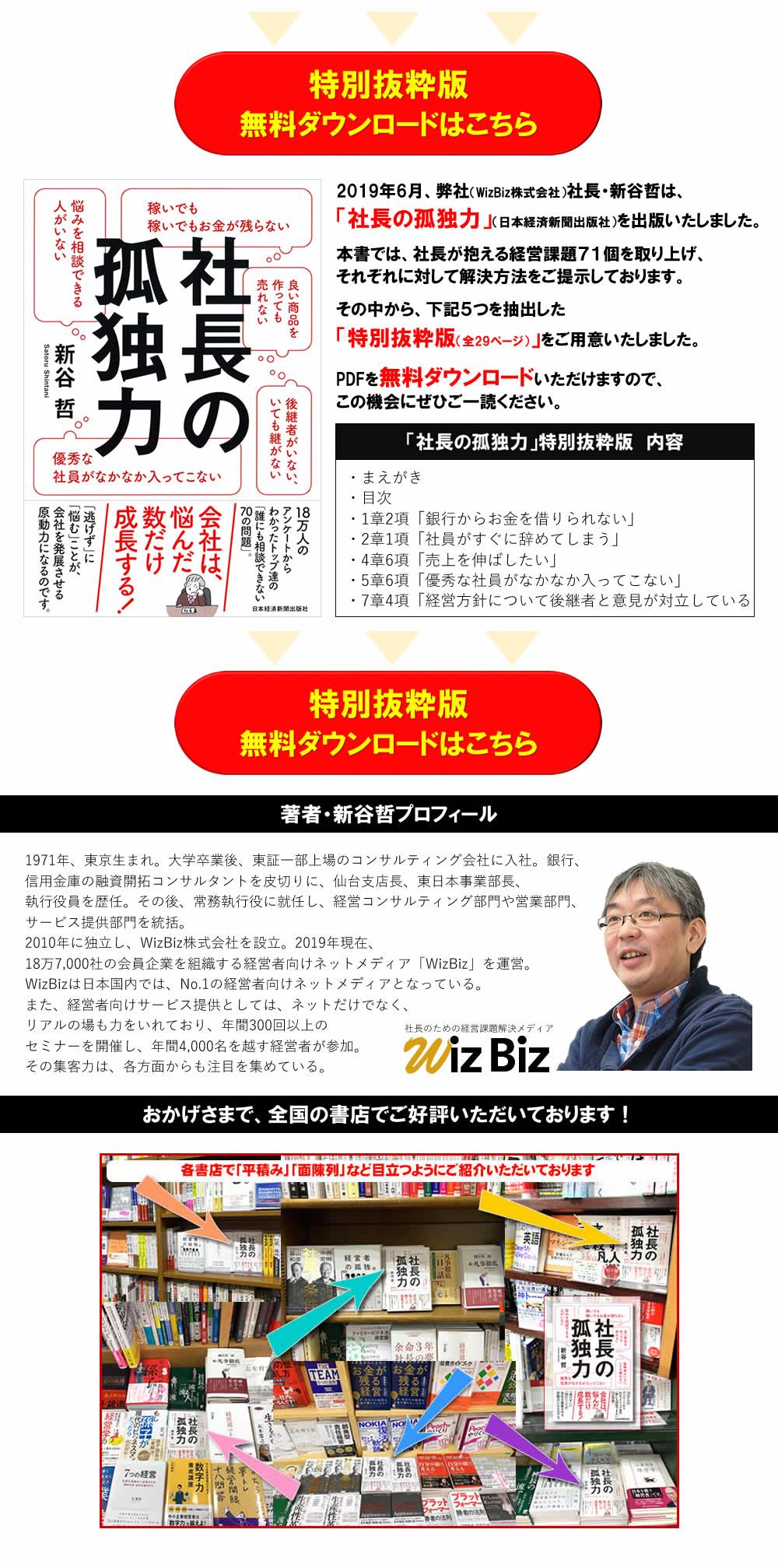でんさい割引とは、電子記録債権(通称:でんさい)を金融機関に譲渡し、支払期日前に現金化する資金調達の方法です。
紙の手形に代わる仕組みとして普及が進み、迅速な資金調達や事務負担の軽減といった多くのメリットがあります。
一方で、審査基準や割引料・買い戻しリスクなど、事前に注意すべき点もいくつかあります。
今回は、でんさい割引の仕組みや活用シーン、他の資金調達方法との違いについて詳しく見ていきましょう。
| まとまった金額の借入なら ビジネスローンがおすすめ! | 売掛金があるなら ファクタリングがおすすめ! |
|---|---|
AGビジネスサポート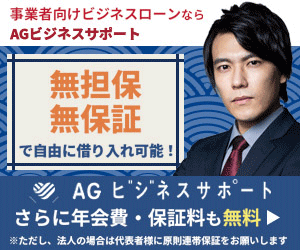 | ワイズコーポレーション |
| 柔軟な審査ですぐに事業資金を融資してもらう方法 | 売掛金や請求書を買い取ってもらい現金化する方法 |
| 融資まで 最短即日 | 入金まで 最速当日中 |
| 申込〜入金 来店不要! | 申込〜入金 来店不要! |
| 融資限度額 50万円〜1,000万円 | 買取限度額 300万円〜上限なし※4 |
| 金利 年3.1%〜18.0% | 手数料 1%〜14.8% |
| 利用者※1 法人(赤字でもOK!) 個人事業主 | 利用者 法人(売掛金があればOK!) 個人事業主 |
| 必要書類※2 本人確認書類 決算書などのみ! | 必要書類 請求書 通帳などのみ! |
| 無担保無保証で借入可能!※3 | 取引先への通知なし! |
| AGビジネスサポート 公式サイトから今すぐ申込 | ワイズコーポレーション 公式サイトから今すぐ申込 |
※2:法人→代表者本人を確認する書類・決算書・その他必要に応じた書類
※2:個人事業主→本人を確認する書類・確定申告書・所定の事業内容確認書・その他必要に応じた書類
※3:原則不要。法人の場合は原則代表者が連帯保証
※4:該当しない方は要相談

WizBiz株式会社 代表取締役
経歴
1971年東京生まれ。大学卒業後、東証一部上場のコンサルティング会社に入社。銀行、信用金庫の融資コンサルタントを皮切りに、仙台支店長、東日本事業部長、執行役員を歴任。その後、常務執行役に就任し、経営コンサルティング部門や営業部門、サービス提供部門を統括。2010年に独立しWizBiz株式会社を設立。現在、経営者向けネットメディア「WizBiz」を運営。国内では経営者の会員登録数でNo.1のメディアとなっている。また、経営者向けサービス提供としては、ネットだけでなく、リアルの場も力をいれており、年500回以上のセミナーを開催し、4000名を越す経営者が参加。18万人の社長アンケートから1000個の悩みを回収。
著書:社長の孤独力
でんさい割引とは電子記録債権を期日前に現金化する方法
企業間取引で発生する売掛金を、紙の手形ではなく電子的に記録・管理できる仕組みが「でんさい(電子記録債権)」です。でんさい割引とは、その電子記録債権を期日前に金融機関へ譲渡し、現金化する方法のことを指します。
でんさいは、手続きすべてが電子上で完結するため、紛失リスクや印紙税の負担もなく、セキュリティの面でもメリットの多い決済方法です。
でんさいネットを通じて記録される電子債権は、全国の金融機関が連携し取り扱っており、法人・個人事業主問わず利用できます。
でんさい※電子記録債権の概要
でんさい(電子記録債権)とは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)が提供する電子的な金銭債権のことを指し、従来の「手形」の課題を解消する目的で整備された経緯があります。手形との主な違いは、おもに下記の通りです。
【手形取引との主な相違点】
| でんさい | 手形 | |
|---|---|---|
| 記録方法 | 電子記録 | 紙媒体 |
| 管理 | 電子債権記録機関(でんさいネット) | 受領側企業と金融機関 |
| 印紙税 | 不要 | 手形の額面金額に応じて必要 |
| 紛失・盗難リスク | 低い | 高い |
| 支払期日 | 自動決済 | 手動決済(交換所への呈示) |
| 譲渡 | 分割譲渡可能 | 分割譲渡不可 |
- 発生……債務者が支払期日や金額などの債権情報を記録することで、でんさいが成立する。
- 譲渡……成立したでんさいは、第三者に全額・分割で譲渡することができ、金融機関に割引を依頼することで現金化も可能。
- 支払……支払期日になると、でんさいネットが債務者の口座から自動的に資金を引き落とし、債権者の口座に入金される。これにより、決済遅延のリスクも軽減される。
でんさい割引を利用できる事業者と利用シーン
でんさい割引は、法人および個人事業主の双方が利用できる決済方法です。売掛債権の回収までに時間がかかる業種や、一時的に資金が不足しやすい事業者にとっては、有効な資金調達手段といえるでしょう。
【でんさい割引の対象者と利用シーン】
| 対象者 | ・中小企業から大企業までの法人・売掛債権(電子債権)を保有する個人事業主 |
|---|---|
| 利用シーン | ・急な仕入れや支払いに備えて短期の資金を調達したい場合・売掛金の入金前に現金化したい場合・建設業など、工事完了から入金までのタイムラグがある業種で早期に資金調達したい場合 |
でんさい割引で資金調達をするメリット
でんさい割引は、手形割引と同様に債権を現金化できる手法ですが、手形割引より多くのメリットがあります。でんさいで資金調達をするメリットについて、詳しく見ていきましょう。
手続きが簡単
でんさい割引は、すべての手続きがオンラインで完結するため、事務作業の大幅な効率化が図れます。従来は、手形の発行に伴い、手形受入帳などを作成して手作業で残高を記録する必要がありました。一方、でんさいネットでは割引取引の履歴や債権残高をデータ上で一元管理できるため、手続きも簡単です。
また、手続きにかかる人員コストや印紙税などの間接コストが不要な点も、企業にとっては大きなメリットといえるでしょう。
迅速な現金化によるキャッシュフロー改善
でんさい割引は、審査や実行手続きが比較的スピーディーに進むため、「キャッシュフローを改善できる」というメリットがあります。手形割引は、手形要件のチェックを入念に行なうため、資金化まで一定の時間を要します。手形貸付や証書貸付のように、都度審査を受ける必要がない点も経営者にとっては嬉しいポイントといえるでしょう。
でんさい割引では、金融機関で割引可能額の上限を設定しており、その枠内であれば都度の審査が省略され、迅速に資金化することが可能です。これにより、急な支払いや売掛金入金のタイムラグによる資金ショートも回避できるでしょう。
必要な金額だけを資金化できる効率性
でんさいは「分割譲渡」ができるため、必要な額だけ資金化できる点も大きなメリットです。例えば、100万円の電子債権を受領している場合でも、資金ニーズが30万円であれば、その分だけ割引して現金化できます。これにより、不要な利息の支払いや過剰な資金調達も回避できるでしょう。
従来の紙の手形割引では、一度に全額を資金化する必要があり、必要以上の割引手数料や取立手数料が発生していました。その点、でんさい割引は経費負担を抑えた効率的な資金繰りが可能です。
でんさい割引で資金調達をする際の注意点
でんさい割引は、便利な資金調達方法ですが、利用にあたっては事前に注意すべき点があります。特に、希望通りの資金化ができないケースがある点は覚えておきましょう。
審査基準は金融機関ごとに異なる
でんさい割引における審査は、依頼者の信用力だけでなく、でんさいを発行した企業(債務者)の信用力が大きく影響します。
金融機関では、それぞれ異なる審査基準を設けているため、同じ電子債権であっても「A銀行では割引が認められ、B銀行では断られる」といったことも珍しくありません。
でんさい割引で重視されるのは、「買い戻し能力」と「銘柄の信頼性」です。利用企業の業績が悪くても、銘柄(発行企業)の信用力が高ければ審査が通る場合があり、逆に銘柄が不安定だと審査に通らないこともあります。
金融機関によっては特定の銘柄を対象外としたり、割引限度額を設定して取扱量を制限したりするケースもあるため「絶対に資金化できるわけではない」という点は覚えておきましょう。
ちなみに、信用力が不十分な場合は、「経営セーフティ共済」へ加入すると、審査が有利に進む場合があります。買い戻し能力の裏付けとして評価されるほか、万が一に備えるリスク管理の手段としても有効です。
参考:制度の概要|共済制度|独立行政法人中小企業基盤整備機構
割引料や手数料の負担がある
でんさい割引を利用する際には、割引料(利息)や各種手数料がかかる点に注意しなければいけません。割引料は、依頼者自身と債務者である支払企業の信用力によって変動し、買い戻し能力が高ければ低料率が適用されやすくなります。
割引料以外にも、金融機関によっては、でんさいネットを利用する際に記録手数料や管理手数料などが発生することもあります。利用する際は、割引料とあわせて総費用がいくらかかるのか、よく確認しておきましょう。
買い戻し義務が発生する
でんさい割引で債権が支払不能となった場合、依頼者はその債権を買い戻さなければなりません。この「買い戻し義務」が発生する可能性があることを理解したうえで利用しましょう。
支払不能が発生した際に買い戻せないと、資金繰りは一気に悪化してしまいます。
そのため、常に一定の資金余力を確保するか、万一に備えて経営セーフティ共済などの保障制度に加入しておくとよいでしょう。複数のでんさいを保有している場合は、できるだけ信用力の高い銘柄を優先して割引依頼するのが基本です。
でんさい割引ですぐに現金化する流れ
でんさい割引でスムーズに資金調達をするには、手続きの流れを正しく理解しておきましょう。でんさい割引を利用する場合の、相談から審査、実行までの具体的な流れについて解説します。
STEP1:相談
でんさい割引を利用する際は、はじめに金融機関へ「でんさい割引を使いたい」旨を伝え、電子債権に関する情報(支払企業、金額、支払期日など)を提示します。
申込みに進む際は、割引依頼書の提出に加え、決算書(確定申告書)や試算表、事業計画書のほか、対象となるでんさい(銘柄)の詳細がわかる資料の提出が必要です。
なお、初めてでんさい割引を利用する場合には、でんさいネットの利用登録が求められるケースもあるため、事前に必要な手続きについて金融機関に確認しておくことが重要です。
STEP2:審査
審査では、依頼者と支払企業(債務者)の信用力が総合的に判断されます。依頼者の買い戻し能力が高いと評価されると、債務者の信用力がやや劣っていても審査に通ることがありますし、その逆もあり得ます。
さらに、割引対象となる電子債権の内容(支払期日、金額、サイトなど)についても、事業実態に合っているか確認されるでしょう。
電子債権の額面が不相応に大きい場合や、取引実態に疑義がある場合には、割引不可または料率引き上げの対象となるかもしれません。支払企業が新興企業や中小零細企業である場合、信用調査の結果次第では審査が通らないこともあるため、銘柄の選定も重要です。
審査通過後には、提示された割引条件(料率や極度額)を確認し、約定書など必要書類を金融機関に提出して契約を締結します。法人の場合は履歴事項全部証明書や印鑑証明書、個人事業主の場合は所得税の納税証明書などが求められることがあります。
STEP3:割引依頼
契約完了後、割引実行の手続きに移ります。依頼者は、実行を希望する電子債権について、割引依頼書および債権の内容がわかる資料を提出し、金融機関へ割引の実施を依頼します。でんさいネットを通じて電子債権を金融機関へ譲渡することで割引処理が完了し、金融機関が正式な譲受人となる流れです。
そのあと、割引料(利息)および手数料を差し引いた金額が、指定口座に入金されます。
でんさい割引の割引率や手数料の相場
でんさい割引における割引率は、利用者と電子債権の信用力によって異なり、同じ債権でも金融機関によって条件が変わるケースもあります。割引率や手数料の目安と決まり方、そしてでんさいネットの利用料について詳しく見ていきましょう。
割引率の目安と決まり方
でんさい割引の割引率は、一般的に年1〜5%程度が目安です。決済までの期間が短いため、証書貸付や手形貸付に比べて低めに設定されるケースが多いでしょう。
ちなみに、割引率は下記の要素で決まります。
- 依頼者の信用力
業績や資産状況などから、支払不能時に「買い戻し」が可能かどうかを金融機関が判断。
信用力が高いと評価されると割引率は低くなる。
- 電子債権(銘柄)の信用力
発行企業の信用力が高ければ、支払リスクが低いと判断され、低い割引率が適用される。
- 金融機関独自の審査基準
各行が保有するリスク評価基準と債務者(支払企業)の格付けにより、割引率は異なる。
たとえ同じ債権であっても、A銀行では1.2%、B銀行では2.5%という違いが出る場合もある。
- 定性情報
法人であれば経営者や役員との取引歴や資産保有状況、個人事業主であれば事業の安定性や家族間での取引状況なども総合的に評価され、料率が決まる。
金融機関ごとの手数料の違いと各種手数料
でんさい割引では、取引に関わる事業者の信用力により割引料が変わりますが、銀行や信用金庫によっても料率は変わってきます。
- メガバンク:料率が比較的低い
- 地方銀行:中間的な料率
- 信用金庫:若干高めの料率設定が多い
また、でんさい割引を行うには、「でんさいネット」の利用が前提となるため、システム利用に伴う手数料なども事前に確認しておきましょう。
- 初期契約料:利用開始時に発生する一時的な費用
- 基本手数料:月額利用料(数百円〜数千円程度)
- 取引手数料:電子債権の発生、譲渡、分割などの操作ごとに発生
- 開示手数料:残高や履歴などの情報開示時に発生
- 支払不能情報照会手数料:債務者に関する支払不能情報を照会する際に必要
でんさい割引とファクタリングの違い
でんさい割引とファクタリングは、いずれも債権をもとに現金化をする方法ですが、仕組みや審査の対象、手数料などに違いがあります。それぞれどのような違いがあるのかについても解説します。
仕組みの違い
でんさい割引とファクタリングは、いずれも債権を早期に現金化する手段ですが、仕組みが若干違います。
まず、ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社に売却する「債権譲渡」に該当します。
債権の所有権がファクタリング会社に移ることで、売掛先から直接支払いを受けることができ、依頼者は売掛金の回収リスクを回避しつつ資金を得られます。
一方で、でんさい割引は、電子記録債権を金融機関に「譲渡(割引)」することで、支払期日前に資金を調達する方法です。
こちらは「電子記録債権に関する法律」に基づく特殊な譲渡方式であり、融資に近い性質を持ちます。
信用調査対象者の違い
ファクタリングとでんさい割引では、信用調査の対象にも明確な違いがあります。
ファクタリングでは、主に売掛先企業(債務者)の信用力が審査対象となります。これは、ファクタリング会社が売掛債権を引き受けて、支払いを受ける立場となるためです。依頼者の信用力が低くても、売掛先の企業がしっかりしていれば利用可能な場合があります。
一方、でんさい割引では、依頼者(割引を求める側)の信用力と、でんさいの債務者(支払企業)の両方が審査対象です。割引依頼者に買い戻し義務があるため、金融機関は貸倒リスクを抑えるべく、依頼者の資金繰り能力や財務内容も厳しく確認します。
手数料や資金調達までのスピードの違い
資金化にかかるコストやスピードにも違いがあります。
ファクタリングでは、手数料が比較的高めに設定されています。特に、売掛先に通知を行わない「2社間ファクタリング」は、信用リスクが高いため手数料率も高くなる傾向があります。資金調達のスピードについては、簡易的な審査で済むケースも多く、最短即日での資金調達も可能です。
一方で、でんさい割引は初回利用時に審査が必要なため、即日資金化は難しいでしょう。継続利用により2回目以降はスムーズに割引が可能になるケースもありますが、手続きはあくまで貸付取引の一環であるため、ファクタリングほどの即時性は期待できません。
でんさい割引についてよくある質問
でんさい割引は、比較的新しい資金調達手段であることから、制度の仕組みや手続き、会計処理に関して疑問点も多いでしょう。最後に、でんさい割引に関するよくある質問についても見ていきます。
でんさい割引は誰でも利用できますか?
いいえ、誰でも利用できるわけではありません。でんさい割引は事業者を対象とした制度で、事業活動に基づいて電子債権を保有している必要があります。さらに、利用にあたっては金融機関の審査を受ける必要があり、その審査を通過した事業者のみが割引を受けられます。
でんさい割引ができないケースはありますか?
はい、あります。電子債権を割引するには、割引依頼者の信用力に加え、債権そのもの(支払企業)の信用力も重要です。
電子債権があっても、下記のケースでは審査通過できない可能性があります。
- 申込企業の財務状況が不安定で、買い戻し能力が乏しい
- 債務者(支払企業)の信用力が低く、支払不能の懸念がある
- 支払期日が近すぎて、割引の事務処理が間に合わない
でんさい割引の仕訳はどうすればよいですか?
以下のように仕訳します(例:100万円の債権を5,000円の割引料で現金化した場合)。
【100万円の電子債権を割引した場合】
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 現預金(割引後の受取金額) | 995,000 | 電子記録債権(割引前の電子債権額) | 1,000,000 |
| 割引料 | 5,000 | ||
※現預金を普通預金や当座預金など具体的にする場合もある
※割引料を支払利息とする場合もある
※手数料を徴求される場合は、「借方」に1科目増やして記入する(手形割引は割引料の他に取立手数料が発生するが、でんさい割引においては発生しないのが一般的)
決算書上では「支払利息・割引料」として営業外費用に分類されるため、勘定科目の整合性を保ちつつ処理することが重要です。
まとめ
でんさい割引は、電子記録債権を活用した近年注目されつつある資金調達手段のひとつです。手続きも簡単で、分割譲渡により必要な額だけを現金化できる点は、大きなメリットといえるでしょう。
一方で、割引には金融機関ごとの審査基準や買い戻し義務、割引料・手数料など注意すべき点も多く、事前の確認が不可欠です。
適切に制度を理解し、自社の信用力や資金需要に合った形で上手に利用しましょう。