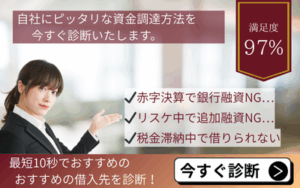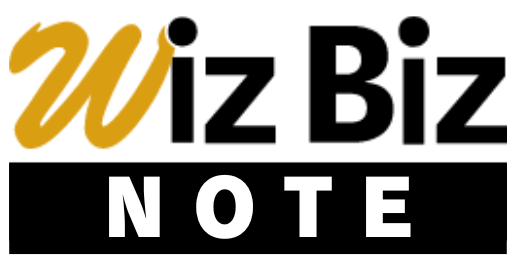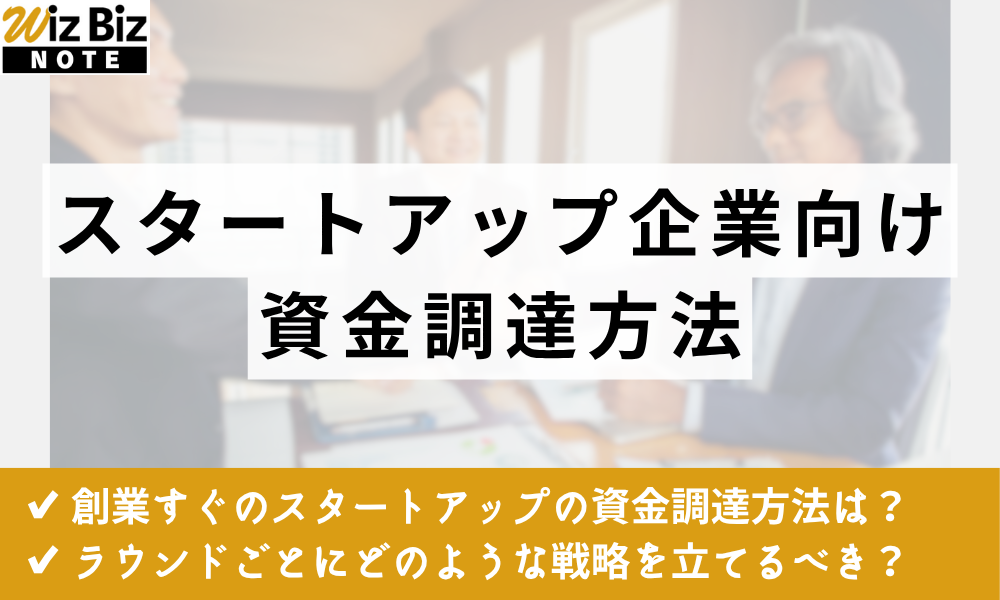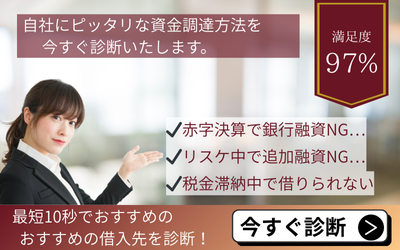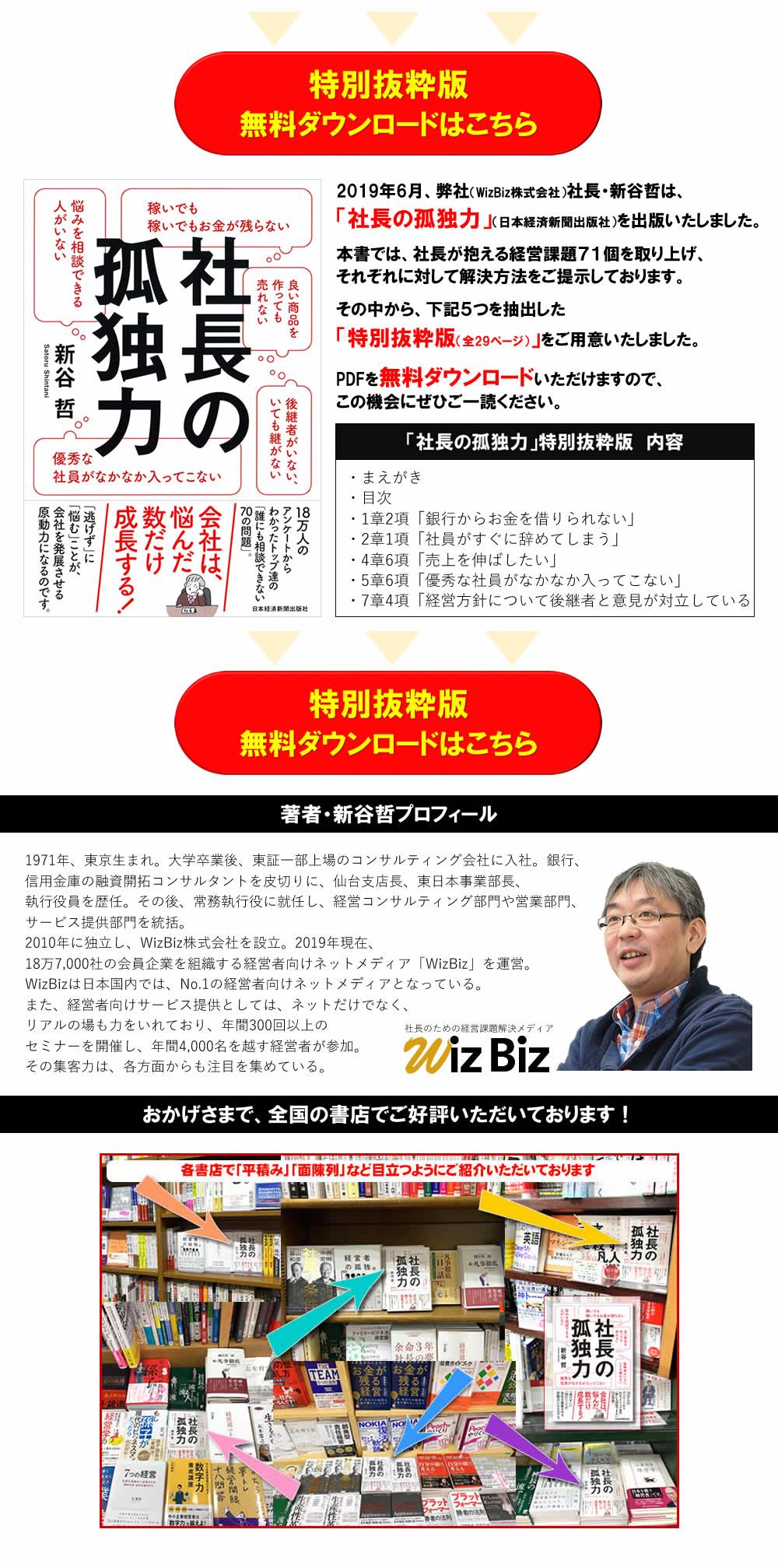スタートアップ企業が成長するには、成長段階に応じた資金調達を考えていくことが重要です。資金の使い道や必要額は、シード期・アーリー期・ミドル期・レイター期で大きく異なります。
一方で、資金調達方法によっては、一部の経営権が渡るリスクについては注意しなければいけません。
今回は、スタートアップ企業に必要な、各成長フェーズに応じた資金調達方法と注意点について解説します。
◎事業計画書テンプレート
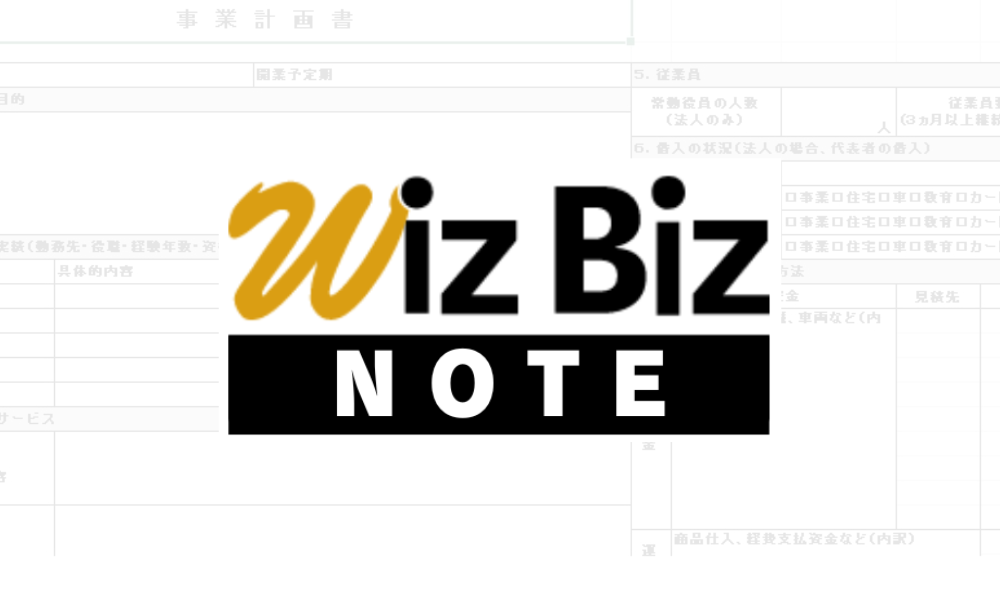
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、事業計画書のテンプレートをお送りします。

1971年東京生まれ。大学卒業後、東証一部上場のコンサルティング会社に入社。銀行、信用金庫の融資コンサルタントを皮切りに、仙台支店長、東日本事業部長、執行役員を歴任。その後、常務執行役に就任し、経営コンサルティング部門や営業部門、サービス提供部門を統括。2010年に独立しWizBiz株式会社を設立。現在、経営者向けネットメディア「WizBiz」を運営。国内では経営者の会員登録数でNo.1のメディアとなっている。また、経営者向けサービス提供としては、ネットだけでなく、リアルの場も力をいれており、年500回以上のセミナーを開催し、4000名を越す経営者が参加。18万人の社長アンケートから1000個の悩みを回収。
著書:社長の孤独力
スタートアップの成長は資金調達がカギになる
スタートアップの成長には、適切なタイミングでの資金調達が欠かせません。プロダクトの開発や人材の採用、マーケティング展開には多額の資金が必要です。
資金調達が重要になる理由
スタートアップが短期間で成果を出すためには、タイミングを逃さずに資金調達をする必要があります。
開発段階ではPoC(概念実証)やプロトタイプ製作のための資金が求められますし、優秀な人材を早期に確保するには相応の資金的余力が必要です。
また、プロダクトやサービスを市場に届けるには、広告や営業といったマーケティング活動への継続的な投資も必要になってきます。
スタートアップにとって資金調達は、単なる「お金集め」ではなく、「事業成長に必要な戦略的ツール」として考える必要があります。
スタートアップのラウンド別に応じた資金調達が必要
スタートアップは成長のラウンド別で資金ニーズが異なり、それに応じた調達手段を選ぶ必要があります。事業の成熟度に応じ、必要な額や投資家との関係性も大きく変化します。
- シード期
創業者のビジョンに共感するエンジェル投資家などからの少額出資が中心。
- アーリー期
プロダクトや市場の検証結果をもとに、VCから資金調達を行う。
事業化に向けて経営支援や業界知見を活かすことが重要。
- ミドル期
事業拡大を見据え、大型のマーケティング費用などの資金を確保。 - 複数VCやCVCからの共同出資が一般的。
- レイター期
IPOやM&Aを見据えたステージ。
PEファンドや海外投資家など、新たな支援者を取り込みつつ、規模拡大と出口戦略を両立させる。
企業の成長を軌道に乗せるには、ラウンドごとに資金調達の目的と役割を明確化し、それに見合う調達手段を選ぶ必要があります。
資金調達は事業の信頼性を高める手段でもある
資金調達は資金面を補うだけでなく、企業としての信頼性を高める手段にもなります。
著名なベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から出資を受けることは、それ自体が事業の一定の評価基準をクリアした証明となり、信頼感につながります。
出資者のブランド力やネットワークを借りることで、メディア露出や人材採用の強化も期待できるでしょう。
さらに、調達情報を公式に発信することで、顧客や取引先からの信頼が増し、新たなビジネスチャンスの獲得にもつながります。
「信頼構築の手段」としても、戦略的な資金調達は極めて重要といえます。
スタートアップ企業の資金調達方法
スタートアップが成長するには、自社のフェーズや戦略に合った資金調達手段を選ぶ必要があります。
「出資」「融資」「補助金」など、資金調達の方法ごとでメリットデメリットがあり、それぞれの仕組みも正しく理解しておく必要があります。
【関連記事】
資金調達をする方法とそれぞれのメリット・デメリットは?経営者向けにプロがポイントを解説
エクイティ(出資)による資金調達
エクイティによる資金調達とは、自社の株式を投資家に提供し、その対価として資金を得る方法です。
ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家などが主な出資元となり、成長性を評価したうえで出資が行われます。
【デメリット】
ただし、返済義務がない一方で、株式の一部を手放すリスクには注意しなければいけません。
- 返済義務がないため、キャッシュフローの負担が少ない
- 投資家のネットワークやノウハウを活用できる
- 株式の一部を手放すため、経営権(議決権)の分散が起こり、経営の自由度が下がる
- 投資家との意見の相違により経営判断が複雑になることもある
投資家を探す時は、資金面だけでなく経営アドバイスなどの支援内容も含め、慎重に選ぶことが重要です。
デット(融資)による資金調達
融資は、金融機関やノンバンクなどから資金を借り返済していく資金調達方法となります。
返済義務はありますが、株式を手放す必要がないため、経営権の維持が可能です。
- 株式を手放さずに済むため、経営権を維持できる
- 要件さえ満たせば最短1週間以内の融資も可能
- 担保や保証人が求められる場合がある
- 金利手数料の負担が経営を圧迫するリスクがある
キャッシュフローが安定し始めた段階であれば、融資は「経営権を維持しつつ資金を得られる有効な資金調達手段」といえます。
補助金や助成金の活用
補助金や助成金は、国や自治体が提供する返済不要の資金です。採択には審査が必要ですが、資金的な負担を大きく軽減できる方法といえます。
- 返済不要なので資金面のリスクが低い
- 採択されるだけでも外部の信頼を得られる
- 財務内容にも影響がない
- 採択率が低く、申請手続きや事務負担が大きい
- 使途に制限があるため、柔軟性に欠ける
- はじめに資金を立て替える必要があるため自己資金が必要
活用を検討する際は、自社の事業内容と補助金の目的が合致しているかを見極めることが大切です。
アセットファイナンスによる資金調達
アセットファイナンスとは、設備や売掛債権・在庫といった保有資産を担保として資金化する方法です。スピーディーな資金調達が可能で、負債を避けながら資金調達をしたいスタートアップに向いています。
- 売掛債権を活用する場合、売掛先の信用力が重視されるため、自社の信用力に関わらず調達ができる
- 自社資産を使って迅速に資金を確保できる
- 借入ではないため、負債計上されず財務が悪化しにくい
- 融資に比べて手数料が高い
- 売掛先の信用力により審査が通らないことや、調達額に限界がある
- 長期的な資金調達には向かない
返済不能に陥るリスクを避けながら、短期資金をスピーディーに確保したい場合には、アセットファイナンスが向いています。
クラウドファンディングによる資金調達
クラウドファンディングは、製品・サービスに共感した個人や投資家から広く資金を募る手法です。購入型や投資型など複数の形式があり、マーケティングと資金調達を同時に行えるメリットがあります。
- 返済不要な資金を調達できる
- 初期ファンを獲得できるマーケティング効果がある。
- 投資家の共感を得られると資金調達額が大きくなる(数億円の事例も)
- 投資家とのネットワークが広がる
- 十分な資金を集めるには高い発信力が必要(高額資金の調達が難しい)
- 支援者への報告義務や、リターンの準備・配送などの手間がある
- 商品開発やサービス提供が遅れると信頼を失う
- 株式持ち分の売却、議決権を譲るケースもあり、経営への口出しを受けることもある
プロダクト開発段階で共感を得られる内容であれば、クラウドファンディングは実行の価値が高い資金調達手段といえるでしょう。
シード期のスタートアップに最適な資金調達方法
創業初期のシード期は、事業の土台を築く非常に重要な時期です。
売上が立っていないなかで、アイデアの実現や体制構築のための資金が必要となります。
このフェーズでは、返済負担が軽く、かつ信頼関係を重視した資金調達手段を選ぶことが重要です。
【関連記事】
起業時の資金調達はどうするべき?創業初期でも融資をしてくれるところはある?
エンジェル投資家からの出資
エンジェル投資家とは、創業直後の企業に出資を行う個人投資家を指します。
ビジョンに共感して支援するスタイルが多く、資金面だけでなく人的支援や経営アドバイスがもらえるケースもあります。
調達額は数百万円から数千万円規模が一般的で、起業家の人柄や将来性が重視され、出資額が決まるケースがほとんどです。
一方で、資金と引き換えに一定の株式を手放す必要があり、双方の関係性が悪化すると、経営に影響を及ぼすことも少なくありません。
エンジェル投資家との信頼関係を築くことができれば、もっとも有効なパートナーになってくれるでしょう。
創業融資制度の活用(日本政策金融公庫など)
創業融資制度は、売上実績がない段階でも利用でき、日本政策金融公庫をはじめとする政府系金融機関が提供しています。
無担保・無保証でも利用可能なケースが多く、調達額は数百万円規模が目安です。
金利は民間の金融機関と比べて低めに設定されており、創業期のキャッシュフローが圧迫されないというメリットがあります。
また、公庫の返済の実績を積み上げることで信用力が上がり、将来的には公庫や金融機関からの追加融資の可能性も上がるでしょう。
ただし、将来にわたる事業計画を具体的に立て、現実的な返済計画を提示することが重要です。
ピッチイベントやコンテストでの資金獲得
スタートアップ向けのビジネスコンテストやピッチイベントでは、事業内容をプレゼンテーション形式で発表し、出資や賞金、さらには支援機関からのサポートが受けられます。
資金調達だけでなく、認知拡大や採用広報にも効果がある点は大きなメリットといえるでしょう。
審査員の評価だけでなく、投資家とのネットワーク作りも可能で、新しいビジネスチャンスが生まれることも珍しくありません。
一方で、資金を得るまでには高い競争倍率をクリアする必要があり、プレゼン資料の完成度や話し方、説得力など多方面の準備も必要です。
アーリー期のスタートアップに最適な資金調達方法
アーリー期は、製品やサービスの検証を終え、本格的な事業化を目指す段階です。
このフェーズでは、ある程度の実績をもとに、事業拡大をするための大きな資金を調達する必要があります。
出資や補助金、融資など多くの選択肢のなかから、自社にとって最適な方法を選びましょう。
ベンチャーキャピタル(VC)からの出資
VC(※)は、スタートアップの成長性を見込んで株式を取得。企業価値が高まった段階での上場や、M&Aによるリターンを期待して投資します。
そのため、出資を受けるには企業価値評価(バリュエーション)が必要であり、経営計画や実績に対しても高い説得力が求められるでしょう。
※ベンチャーキャピタル(VC)とは……将来有望な未上場のスタートアップ企業に投資し、株式上場や売却によってリターンを得るファンド
調達に成功すれば、資金だけでなく、「事業戦略のアドバイス」や「人的ネットワークの提供」といった支援も受けられます。
ただし、経営権の一部を委ねることになるため、経営の自由度が制限される可能性や、EXIT(IPOやM&A)に向けたプレッシャーを受ける点には注意しなければいけません。
補助金や助成金との併用
アーリー期のスタートアップでは、出資だけでなく補助金や助成金を活用する方法もおすすめです。
国や自治体が提供する各種支援制度は、スタートアップに特化したものから、研究開発や設備投資に使える一般的なものまで幅広く存在します。
「ものづくり補助金」や「小規模事業者持続化補助金」に加え、NEDOやJSTの技術系補助金を活用できれば、資金面の負担を軽減しながら開発を進められるでしょう。
ただし、申請書類の作成や採択後の実績報告など、事務的な対応が多く、補助率や金額の上限・用途の制約にも注意が必要です。
計画的に申請を行い、ほかの資金調達と並行して活用するのがポイントといえます。
銀行や公庫の追加融資
売上実績や利益が出始めたアーリー期では、銀行や日本政策金融公庫からの追加融資も検討できます。
ただし、運転資金や設備投資資金などを確保するには、事業実績と実現可能な事業計画が不可欠です。
既存の借入に対しても安定した返済実績があることが前提となり、説得力のある収支見通しも求められるでしょう。
日頃から「1円でも黒字にしておくこと」や、「税金は絶対に滞納しない」といったことも重要になってきます。
【関連記事】
【元銀行員が解説】銀行融資の審査は厳しい?審査基準や通過率を上げるためのコツを法人融資のプロが解説
ミドル期のスタートアップに最適な資金調達方法
スタートアップがミドル期に差しかかると、市場でのシェア拡大や新拠点展開などを見据え、億単位の資金が必要になるケースもあります。
そのため、従来の小規模融資や補助金だけでは、資金が枯渇することも。ミドル期は、戦略的パートナーとの提携など、多角的な視点での資金調達が必要です。
大型出資先の検討
ミドル期のスタートアップが次の成長ステージへと進むには、グロースステージ向けのファンドや投資機関との連携が必要です。
こうした出資元からの資金提供は、数億円単位にもおよぶことがあり、エグジット(IPO/M&A)を前提にした支援が行われます。
支援を受けることができれば外部からの信頼性がさらに高まり、「人材採用」や「大手企業との提携」といった波及効果も大きく、事業も加速するでしょう。
一方で、出資者の数が増えることで株主構成が複雑になり、経営判断に時間がかかるリスクには注意しなければいけません。
複数VC・CVCからの共同出資
複数のベンチャーキャピタル(VC)や、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)から同時に出資を受け、大きな資金援助を受ける方法もあります。
CVCは、出資元の業界知見や販路を活かし、製品開発や営業面での支援を受けられる点が大きな強みです。
※コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)とは……事業会社が自社の戦略目的でスタートアップに投資するベンチャーキャピタル
支援を受けることができれば、業界内での信用力も向上し、資金調達だけでなく事業提携の機会も広がるでしょう。
一方で、複数の出資者間での合意形成に時間がかかったり、調達条件の交渉や株主間契約(SHA)に手間がかかる点には注意が必要です。
レイター期のスタートアップに最適な資金調達方法
レイター期に入ったスタートアップは、事業モデルの確立や収益の安定を背景に、さらなる拡大や上場を視野に入れた資金調達をする必要があります。
IPOの準備
IPO(新規株式公開)は、レイター期において、もっとも代表的な資金調達手段のひとつです。
上場に成功できれば、数十億円から数百億円規模の資金調達が可能となるほか、企業の知名度や信用力が大きく向上し、人材確保や取引先との交渉力にも好影響が出るでしょう。
ただし、上場後は四半期ごとの開示義務や株主対応などが生じ、経営の自由度が一定制限される点もあります。
PEファンドや海外投資家の出資受け入れ
海外市場への進出や、事業の多角化を加速させたいなら、PEファンド(※)や海外投資家からの出資も検討できるでしょう。
海外からの出資によって現地との連携も深まり、グローバル展開も期待できるかもしれません。
一方で、英語でのIR対応や現地法規制への理解が必要など、注意すべき点もあります。
投資家の価値観や経営関与の度合いが日本の投資家とは異なるケースも多く、丁寧な対応と交渉が不可欠です。
※PEファンド……投資銀行出身者や経営者などで構成される運用会社(PEファーム)が運営する投資ファンド。未上場企業に投資して企業価値を高めたうえで売却益を得る
スタートアップ企業が資金調達をする際に注意すべき点
スタートアップ企業が資金調達をする際に注意すべき点についても、詳しく見ていきましょう。特に、資金調達により経営権が分散される点には、注意が必要です。
出資比率と経営権のバランス
出資を受けると、資金を得ると同時に株式の一部を手放すことになります。出資比率のバランスを誤ると、経営に大きな制約を受けることにもなりかねません。
また、投資契約に含まれる拒否権や特別決議条項によって、重要な経営判断に投資家の同意が必須となるケースもあります。
こうした状況を防ぐためには、あらかじめ株主構成のシミュレーションを行い、種類株式(※)の活用や、投資契約において経営権関連条項(拒否権など)を盛り込むことも検討しましょう。
※種類株式とは……普通株式とは異なる権利内容(議決権、配当、残余財産分配など)をもつ特別な株式のこと。
企業が柔軟な資本政策を行うために発行し、投資家や経営陣との利害調整に使われる。
調達資金の使途管理とモニタリング
支援を受けた資金をどのように活用するかは、投資家や金融機関からの信頼を維持するうえで極めて重要なポイントです。
当初の想定とは異なる用途に資金を使ってしまうと、投資家からの信頼を失ってしまいます。
特に銀行融資では資金使途違反が重く見られ、信用の失墜や融資打ち切りにつながるリスクもあります。
調達資金は必ず明確な目的に基づいて運用し、使途を定期的にチェックするモニタリング体制も構築しておきましょう。VCから出資を受けている場合は、四半期単位での報告義務が課されることもあります。
フェーズに合わない調達方法は逆効果になることも
スタートアップにおいては、成長段階に応じて適切な資金調達方法を選ぶことが鉄則です。
事業基盤がまだ未熟な段階で大型出資を受けると、資金を有効活用できず、資金の使い道に困ったり無駄遣いが常態化する恐れがあります。
さらに、VCの出資が早すぎると、必要以上に議決権を与えることで経営への干渉が強まり、意思決定の柔軟性が損なわれます。
自社の成長フェーズを正しく理解し、状況に合った調達額と手法を見極めることが重要です。
成長フェーズに応じた資金調達で、スタートアップの可能性を最大化しよう!
スタートアップ企業の成長には、成長フェーズごとに最適な資金調達が欠かせません。
ただし、どの資金調達方法にも「金利負担」や「経営に関与される」などのリスクが存在する点には注意しましょう。
必要な資金額や、資金使途の管理、投資家との関係性などを総合的に判断し、自社のフェーズにあった適切な資金調達方法を選ぶのが重要です。
◎事業計画書テンプレート
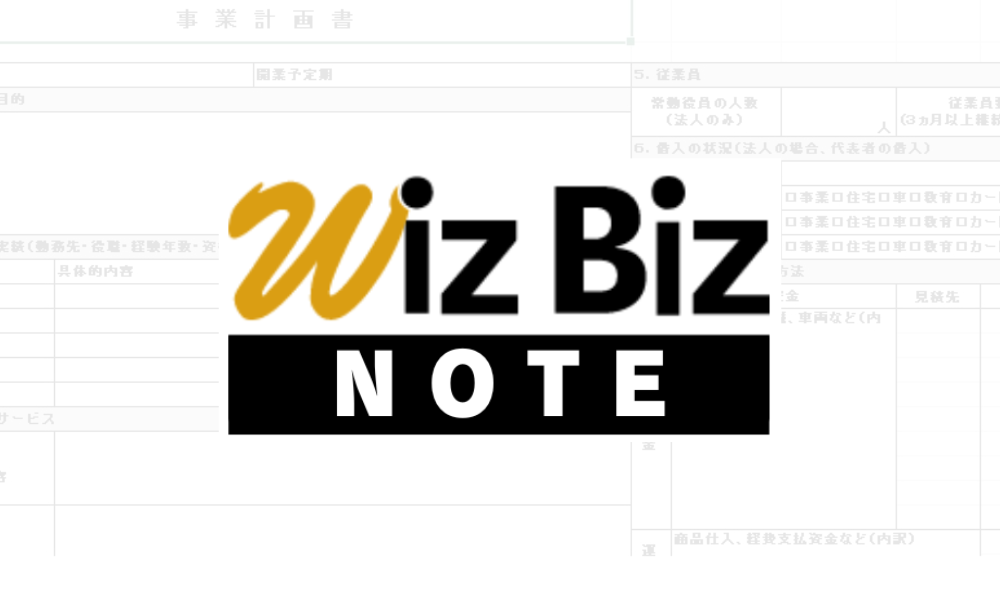
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、事業計画書のテンプレートをお送りします。