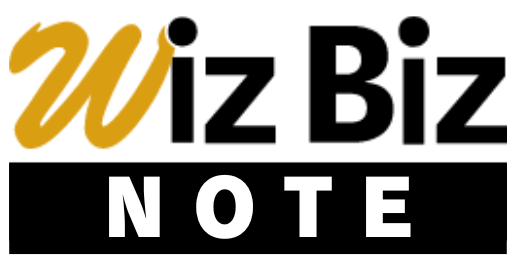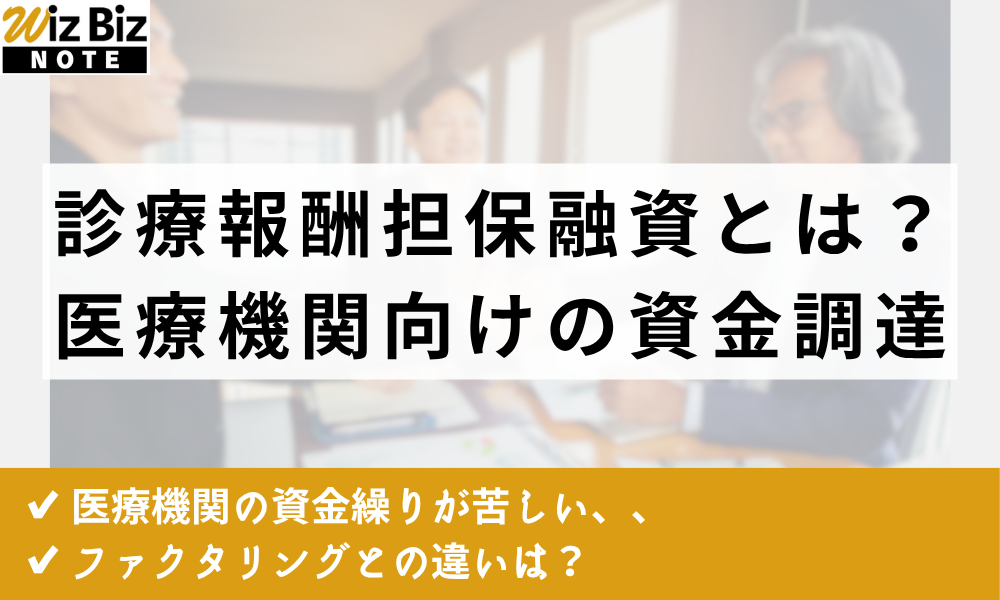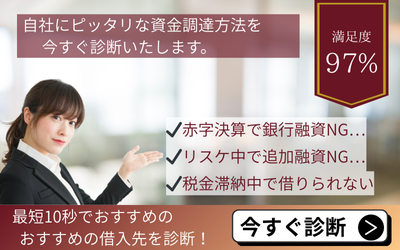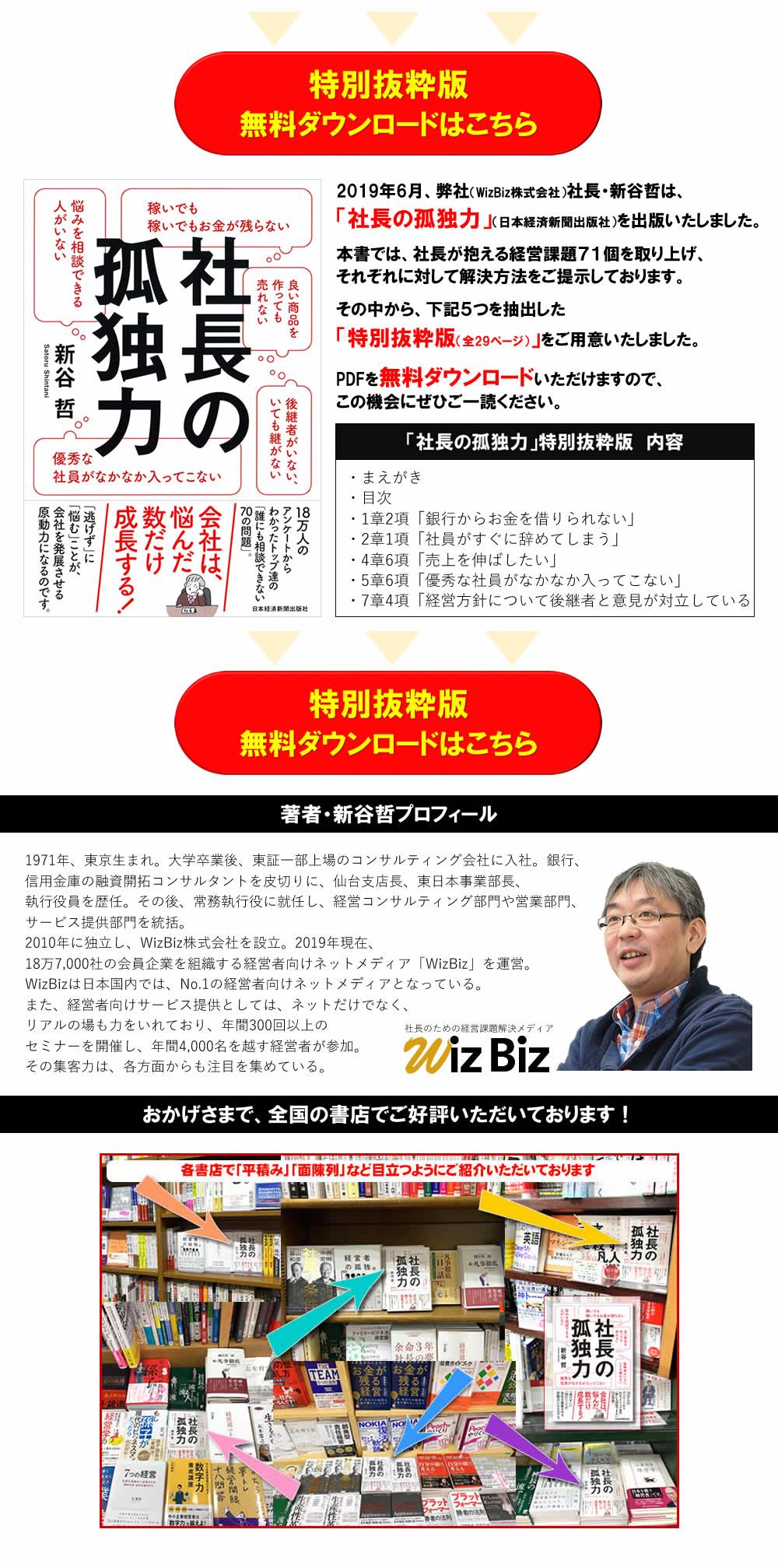診療報酬担保融資は、病院やクリニック・薬局などが、将来受け取る診療報酬を担保に融資が受けられる商品のことです。
信用の高い診療報酬が活用でき、さらに保証人や不動産担保が不要なため、資金繰りに悩む医療機関にとっては頼りになるサービスといえるでしょう。
今回は、診療報酬店舗融資の仕組みやメリット、利用上の注意点などを詳しく見ていきます。
【医療・介護事業者の新しい融資】

ヘルスケア事業者が資金繰りに困ったら「AGメディカル」の診療報酬担保融資がおすすめ。
赤字OKで、将来入る診療報酬を担保にすることで最大4ヶ月分の借入が可能!
ファクタリングから乗り換えるヘルスケア事業者様が増えています。

WizBiz株式会社 代表取締役
経歴
1971年東京生まれ。大学卒業後、東証一部上場のコンサルティング会社に入社。銀行、信用金庫の融資コンサルタントを皮切りに、仙台支店長、東日本事業部長、執行役員を歴任。その後、常務執行役に就任し、経営コンサルティング部門や営業部門、サービス提供部門を統括。2010年に独立しWizBiz株式会社を設立。現在、経営者向けネットメディア「WizBiz」を運営。国内では経営者の会員登録数でNo.1のメディアとなっている。また、経営者向けサービス提供としては、ネットだけでなく、リアルの場も力をいれており、年500回以上のセミナーを開催し、4000名を越す経営者が参加。18万人の社長アンケートから1000個の悩みを回収。
著書:社長の孤独力
診療報酬担保融資とは
診療報酬担保融資は、将来的に支払われる診療報酬債権を担保に、金融機関やノンバンクから融資を受けることを意味します。
国民健康保険団体連合会や社会保険診療報酬支払基金といった公的機関から支払われる報酬を担保にするため、信用度が高く、金融機関からも安定した債権として評価されるのが特徴です。
また、診療報酬以外の担保や連帯保証人が不要なケースも多く、資産の少ない開業医や中小規模の医療法人にとっても利用しやすいでしょう。
診療報酬担保融資の仕組み
診療報酬担保融資は、医療機関が将来受け取る診療報酬(レセプト請求に基づく債権)を担保に設定し、その範囲内で金融機関から融資を受ける仕組みになっています。
診療報酬の支払元が「国民健康保険団体連合会」や「社会保険診療報酬支払基金」といった公的機関であるため、債権としての信頼性が極めて高い点が特徴です。
金融機関は、医療機関から債権譲渡契約を締結したうえで、支払機関へ債権譲渡通知を行い、譲渡が正式に受理された段階で融資を実行します。
- 診療報酬債権を担保に現金化できる
- 通常、診療報酬が支払われるまで約2ヵ月かかるが、融資を利用すれば素早く資金調達ができる
- 不動産や連帯保証人が不要な場合が多い
- 信用が高い債権のため、比較的低金利で利用可能
主な申込先はノンバンク
診療報酬担保融資は、すべての金融機関で提供されているわけではありません。主に医療専門の金融会社やノンバンク、または一部の銀行・信用金庫が取り扱っています。
銀行や信用金庫では、診療報酬担保融資を取り扱う例は少数で、審査に時間がかかることが一般的です。
一方、ノンバンクや医療専門の金融会社は、診療報酬担保融資を取り扱うことも多く、審査の柔軟性やスピード融資が可能な点が特徴といえます。
- 一部の地方銀行、信用金庫(取り扱い実績は少数)
- ノンバンク系貸金業者(審査が比較的柔軟)
- 医療機器リース会社のグループ企業
- 医療機関向け融資を専門とする民間金融会社
特に医療機器リース会社系列の金融業者は、医療機関の設備投資支援と診療報酬担保融資の両方ができることから、総合的な支援が受けられる特徴があります。
業者ごとに融資条件や対応スピードが異なるため、融資を利用する際は複数の業者を比較し、最適な業者を選びましょう。
【関連記事】
ビジネスローンのおすすめランキング!即日低金利で事業資金を借りられるところは?
対象となる医療機関や事業者
融資の対象は、「健康保険制度に基づく診療報酬請求が可能な事業者」、つまり保険医療機関に該当する医療・福祉関連です。
診療報酬という債権があれば、規模や法人格に関係なく利用できるのが特徴です。
主に医療・介護分野の事業者が対象となりますが、最近では柔道整復師や訪問看護など、比較的小規模な事業所の利用も増加しています。
- 病院、クリニック、診療所(個人・法人問わず)
- 歯科医院や調剤薬局
- 訪問介護・デイサービスなどの介護事業所
- 整骨院・接骨院
通常の融資と異なり、過去の決算内容よりも診療報酬実績や将来の入金見込みが重視されるため、信用力に不安がある医療機関でも利用しやすいでしょう。
診療報酬担保融資を利用する流れ
診療報酬担保融資の流れについても見ていきます。
医療報酬担保融資は、一般的な金融機関の融資と比較し、迅速に資金を調達できるというメリットがありますが、必要書類の準備や審査対応には一定の手間が伴います。
診療報酬債権の確認と必要書類の準備
診療報酬担保融資を利用するには、まず保有する診療報酬債権の内容を把握することから始めましょう。
具体的には、下記の内容を確認します。
- レセプト請求金額と入金状況(直近数ヵ月)
- 請求先と入金サイト(サイクル)
- 未入金や差し戻しの有無
- 今後の診療実績見込み
次に、下記の書類を準備します。
- 診療報酬支払通知書(3〜6ヵ月分)
- 決算書・確定申告書(直近2〜3期分)
- 登記簿謄本・身分証明書
- 診療報酬振込口座の通帳コピー
- 診療所や薬局の開設許可証(業種による)
提出書類の内容や必要年数は金融機関によって異なるため、事前に金融機関やノンバンクの条件を確認しておくことが重要です。
金融機関への申込みと審査
必要書類をそろえたら、申込みに進みます。
申込方法は業者によって異なり、オンライン申請で完結するケースもあれば、面談を必要とする場合もあります。
審査では、診療報酬の安定性と返済能力が確認されるでしょう。
金融機関は、売上推移や保険請求の安定性、税金や社会保険料の納付状況などを審査し、継続的に返済が可能かを見極めます。
診療報酬が担保となるとはいえ、事業としての健全性が求められる点は通常の融資と同様です。
- 診療報酬の月次安定性
- 税金、社会保険料の滞納の有無
- 信用情報(延滞・事故履歴)
- 借入残高や債務超過の有無
審査期間は申込先によって差があります。
銀行や信用金庫の場合は1〜2週間程度を要することもありますが、ノンバンク系や医療系民間金融会社の場合は、即日〜5営業日以内で対応してくれるケースがほとんどでしょう。
契約締結から融資実行
審査に通過すると、契約手続きに進みます。融資額、金利、返済方法、返済期間などを確認し、金銭消費貸借契約を締結しましょう。
続いて、債権譲渡担保契約を締結し、診療報酬債権の譲渡通知を支払機関(国保連合会や支払基金)へ送付します。
これにより、貸主は債権に対する回収権を法的に確保し、正式に債権譲渡を受理することで、融資実行の準備が整います。
融資実行は、債権譲渡通知の受理確認後に行われる流れです。
融資金は原則として医療機関の指定口座に振り込まれ、そのあと入金された診療報酬から自動的に返済が行われます。
診療報酬が満額入金されなかった場合でも、差額は医療機関に返金される形で処理されるのが一般的です。
医療機関が診療報酬を担保に融資を受けるメリット
診療報酬担保融資は、一般的な融資と比べて、さまざまなメリットがあります。
診療報酬という安定的な収入を前提とするため、信用力や資産が乏しくても利用しやすい点は、大きなメリットといえるでしょう。
そのほか、診療報酬担保融資の5つの主要なメリットについて詳しく解説します。
診療報酬という安定した将来債権を活用できる
診療報酬は国の公的保険制度に基づいて支払われるものであり、支払元は「国民健康保険団体連合会」や「社会保険診療報酬支払基金」といった公的機関です。
そのため、債権としての信用度は非常に高く、売掛金の中でも極めて安定性があるとみなされます。
金融機関は「貸し倒れリスクの少ない債権」と判断するため担保価値が高く、融資実行の判断も前向きです。
一方で、医療機関側にとっては、診療実績そのものが担保力と見なされるため、資産に乏しい事業者でも借りられる点がメリットといえます。
また、一定の診療報酬実績がある場合には、年利2%台の低金利で対応してもらえるケースもあり、金利面でもメリットが大きい融資です。
担保や保証人が不要で利用できる場合が多い
診療報酬担保融資では、担保に設定されるのはあくまでも診療報酬債権であり、不動産や機械設備などの物的担保を求められることは基本的にありません。
また、代表者の連帯保証についても、診療報酬の安定性が評価されるため不要となるケースが多く、最低限のリスクで事業資金を調達できるメリットもあります。
資産を保有していない開業直後の医師や、中小規模の医療法人にとっては、担保や保証に依存せずに資金調達ができるという点は大きなメリットといえるでしょう。
過去の業績が芳しくない場合でも利用できるケースも多く、銀行で断られた医療機関でも融資が受けられるというメリットもあります。
短期間での資金調達が可能
診療報酬担保融資は、決算書や確定申告書ではなく、診療報酬の実績に基づいた審査が行われます。
財務内容よりも毎月の保険請求の安定性が重視されるため、準備書類が比較的少なく、審査スピードも早いというメリットがあります。
銀行や信用金庫の通常融資では、融資までに1〜2週間程度を要するのが一般的で、急ぎの資金調達には不向きです。
その点、スピーディーな資金調達が可能な診療報酬担保融資は、資金繰りに逼迫しがちな医療機関にとって大きなメリットといえるでしょう。
運転資金や設備投資など幅広い用途に活用できる
診療報酬担保融資は、資金使途が比較的自由です。薬品や消耗品の仕入れ、人件費、設備投資、納税資金など、多様な用途で使えるのも大きなメリットです。
銀行融資では、資金使途が厳密に限定され、使途証明として見積書や領収書の提出が求められるのが一般的です。
診療報酬担保融資では、厳格な制限が設けられていない業者も多く、明確な目的がなくとも、運転資金など余裕資金を確保したい場合にも適しているでしょう。
経営の安定化とキャッシュフロー改善が図れる
診療報酬は、一般的に診療行為から実際の報酬入金まで、約2ヵ月かかります。このタイムラグは、収支のズレを生み、キャッシュフローを痛めかねません。
こうしたズレを埋め、経営の安定化を図りたい場合も、診療報酬担保融資は適しています。
また、季節要因による収入減少、急な人件費増加など、予期せぬ事態に備えるためには一定の余剰資金を確保しておく必要があります。
診療報酬担保融資を活用できれば、こうした不測の事態にも冷静に対応できるでしょう。
診療報酬担保融資を利用する際の注意点
診療報酬担保融資の利用にあたってはいくつかの注意点があります。
金利や手数料、将来的な診療報酬の減少リスクなどを理解したうえで利用しないと、思わぬコスト負担や返済困難に直面する可能性があります。
金利や手数料が高めに設定される場合がある
診療報酬担保融資は、利便性が高い反面、金利や手数料が高めに設定されている場合があります。
ノンバンク系の貸金業者が提供する商品は、柔軟な審査をしてくれる一方、貸し倒れリスクをカバーするため高めの金利が設定されるケースがほとんどです。
- 年2〜10%超の金利が設定されることもある
- ノンバンク系は銀行・信用金庫より金利が高い
- 契約時の事務手数料や実行手数料(1〜3%)がかかることも多い
また、債権譲渡登記の手続き費用が発生する点には注意が必要です。
金利や手数料を含めた総コストを計算すると、実質年率で10%近くになるケースもあるため、総額の返済コストがいくらかかるのか理解しておきましょう。
債権譲渡登記が必要となることが多い
診療報酬担保融資では、債権譲渡登記が必要になるケースがある点にも注意が必要です。
債権譲渡登記とは、担保設定の事実を法務局で公的に記録し、第三者に対抗できるようにするための手続きです。
・債権譲渡登記制度は、法人がする金銭債権の譲渡について、債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。
法務省「債権譲渡登記制度の概要」
・債権譲渡登記制度は、債権流動化をはじめとする法人資金調達手段の多様化を背景に、債権譲渡の対抗要件具備方法等に関する民法の特例として、「債権譲渡登記」という簡便な対抗要件具備の方法の仕組みを創設するものであり、平成10年10月から運用が開始されました。
万が一返済が滞った場合でも、登記があることで貸主は優先的に債権を回収できるようになります。
多くの業者は公式サイトで「債権譲渡通知」を明記していても、「登記」の必要性までは記載していない場合がほとんどです。
ただし、実際には登記が求められるケースもあるため、契約前に必ず確認しておきましょう。
100%審査に通るとは限らない
診療報酬債権が担保となるとはいえ、必ずしも融資を受けられるとは限りません。
診療報酬は信用力が高い債権ですが、あくまで「返済可能な事業者」であるかどうかが融資の前提です。
経営状況や納税状況に問題がある場合は、否決されることもあるため注意しましょう。
- 税金や社会保険料の未納、滞納がある
- 過去に金融事故や延滞履歴がある
- 業況が悪く、今後の診療収入で返済が見込めないと判断された場合
- 債務超過など財務体質に問題がある
診療報酬の減少リスクを考慮する
診療報酬は一定の安定性があるものの、将来的に減少する可能性も十分にあります。
競合となる医療機関の出現、患者数の減少、診療スタッフの離脱などが原因で、予想よりも診療報酬が落ち込むリスクについては注意しましょう。
診療報酬担保融資は、一時的な資金不足への対応には有効ですが、恒常的な利用は控えましょう。
診療報酬担保融資と診療報酬ファクタリングの違い
診療報酬を活用した資金調達には、大きく「診療報酬担保融資」と「診療報酬ファクタリング」の2種類があります。
どちらも診療報酬という将来債権を活用する点では共通していますが、仕組みや返済義務の有無など、いくつかの違いがあります。
所有権移転の有無による違い
診療報酬債権の「所有権がどこにあるか?」という点は、担保融資とファクタリングのもっとも大きな違いです。
診療報酬担保融資では、診療報酬債権は医療機関が保有したまま担保として提供されます。
一方、ファクタリングでは債権そのものを業者に譲渡(売却)するため、所有権は業者に移転します。
この違いにより、入金先の管理や責任の所在に違いがある点は覚えておきましょう。
| 診療報酬担保融資 | 診療報酬ファクタリング | |
|---|---|---|
| 債権の所有権 | 医療機関に残る | 業者に譲渡 |
| 契約の性質 | 融資契約 | 債権譲渡契約 |
| 債務不履行時の処理 | 担保権に基づき債権回収 | 業者の所有権により自由に回収可 |
返済義務の有無による違い
もう一つの大きな違いは、「返済義務の有無」です。
診療報酬担保融資は、あくまでも借入であるため、元本と利息を返済する義務が生じます。
一方で、ファクタリングは診療報酬債権を売却し、代金を受け取った時点で取引が完了するため返済義務は発生しません。
会計処理や資金調達コストの違い
診療報酬担保融資とファクタリングは、会計処理の仕訳方法や資金調達コストの面でも大きな違いがあります。
担保融資はあくまで負債計上され、支払利息は費用として処理されますが、ファクタリングは債権の売却によって資産が減少し、譲渡益や譲渡損が発生します。
| 診療報酬担保融資 | 診療報酬ファクタリング | |
|---|---|---|
| 貸借対照表での 会計処理 | 借入金として負債に計上 | 売掛金の減少として資産減額 |
| 損益計算書での 会計処理 | 支払利息として費用処理 | 譲渡益または譲渡損として処理 |
| 実質コストの目安 | 年利2〜10%+事務手数料・登記費用 (実質年率5〜20%弱) | 手数料10〜20% (債権額から差し引かれる) |
診療報酬を担保に資金調達をすることは違法ではない
診療報酬を担保に融資を受けることについて、「違法ではないか?」「医療機関が債権を譲渡してよいのか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。
診療報酬債権は民間の財産権として譲渡が可能であり、これを担保として利用することは法律上まったく問題ありません。
医療機関が診療報酬という売上債権を担保に資金調達を行うことは、民法上認められた正当な行為です。
債権は財産権の一種であり、自らの資産として譲渡・担保設定が自由にできるという「債権譲渡自由の原則」が適用されます。
この原則は、民法第466条第1項に明記されており、「債権は譲渡することができる」とされています。
診療報酬債権も例外ではなく、債権者である医療機関が自らの意思で金融機関に譲渡することは合法です。
さらに、厚生労働省や社会保険診療報酬支払基金といった公的機関も、債権譲渡の存在自体を否定しておらず、債権譲渡通知の受付も実務上行われています。
したがって、診療報酬担保融資の利用自体には法的な問題はなく、むしろ医療機関にとっては信用力のある債権を有効活用できる合理的な資金調達手段であるといえるでしょう。
診療報酬担保融資の利用でよくある質問
最後に、診療報酬担保融資でよくある質問についても見ていきましょう。
診療報酬担保融資は個人開業医でも利用できますか?
はい、個人開業医でも診療報酬担保融資の利用は可能です。
医療法人でなくとも、診療報酬という債権を保有していれば、法人個人を問わず利用は可能です。
債権譲渡登記とはなんですか?
債権譲渡登記とは、診療報酬債権を第三者に譲渡した事実を法的に証明する手続きです。
法務局で登記が行われると、債権者は優先的に回収できる権利を得ることができます。
登記は、貸金業者側が手続きを代行するのが一般的ですが、登記費用や司法書士報酬が別途かかる点には注意が必要です。
融資とファクタリングならどちらを選ぶべきですか?
どちらを選ぶべきかは、資金調達の緊急度やコスト、金額によって判断する必要があります。
即日で資金が必要で、かつ返済義務を負いたくないならファクタリング、コストを抑えつつ高額資金が必要な場合は融資が向いています。
審査から融資実行までどれくらいの期間がかかりますか?
申込みから融資実行までは、おおむね3日〜1週間程度で完了するのが一般的です。
一部の銀行や信用金庫では取り扱いが少なく時間を要する場合が多いため、スピードを重視する場合は民間の医療専門ノンバンクの利用がおすすめです。
取引先に知られることはありませんか?
通常、知られることはありません。
診療報酬担保融資は、医療機関と金融業者の間で完結する契約であるため、外部の病院や関係者に情報が漏れることはありません。
ただし、取引先が債権者や株主の場合には、決算書などの財務資料を通じて融資の存在が認識される可能性はあるため注意しましょう。
診療報酬担保融資を賢く使って安定経営を目指そう
診療報酬担保融資は、診療報酬という安定的な債権を利用し、迅速かつ柔軟に資金調達できる方法です。
返済義務や登記などの注意点を理解したうえで活用すれば、急な資金調達ニーズにも対応できるでしょう。
利用する際には、信頼できる金融機関やノンバンクを選び、複数の条件を比較しておくことが大切です。
【医療・介護事業者の新しい融資】

ヘルスケア事業者が資金繰りに困ったら「AGメディカル」の診療報酬担保融資がおすすめ。
赤字OKで、将来入る診療報酬を担保にすることで最大4ヶ月分の借入が可能!
ファクタリングから乗り換えるヘルスケア事業者様が増えています。