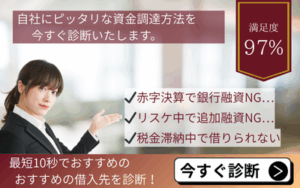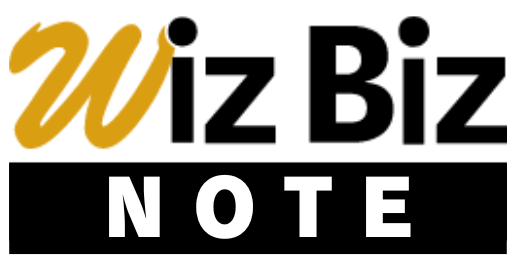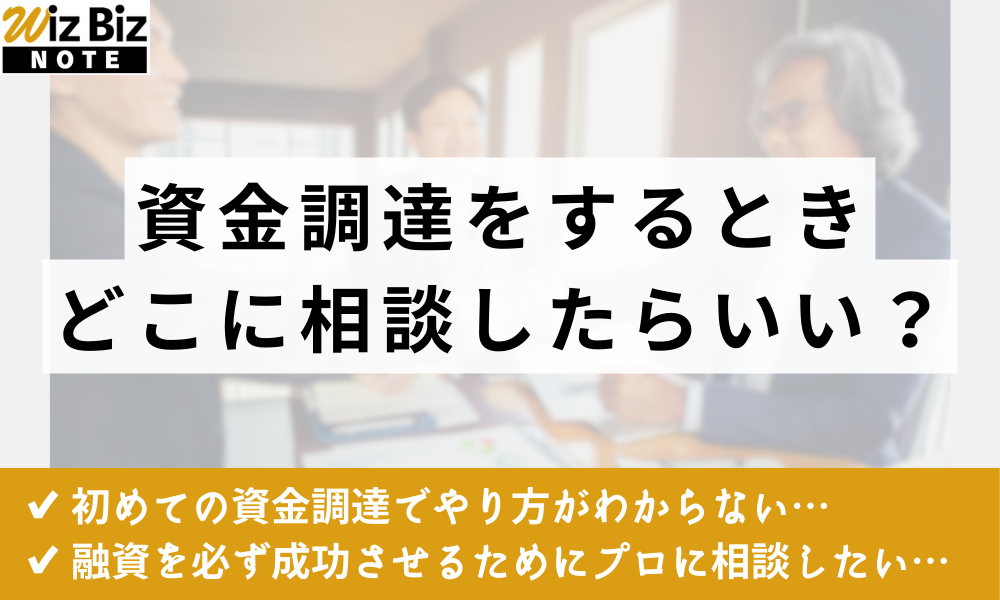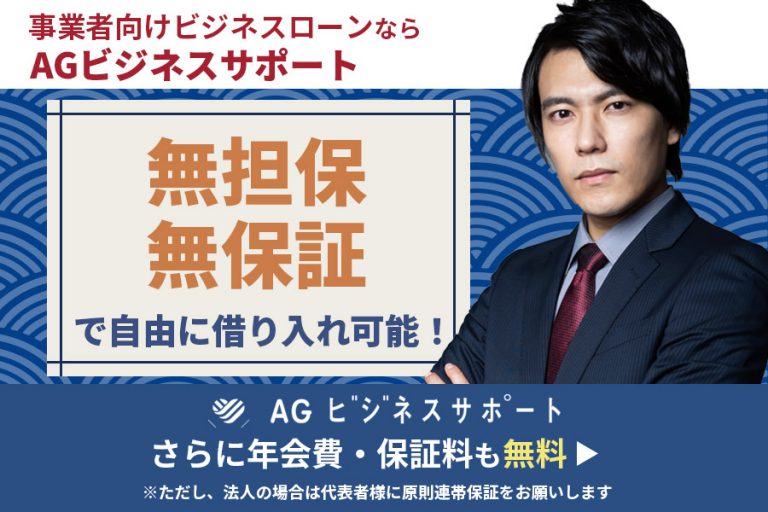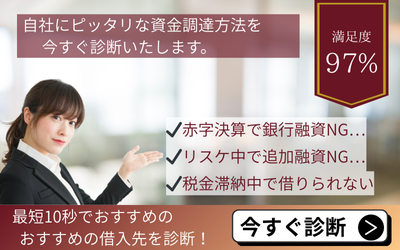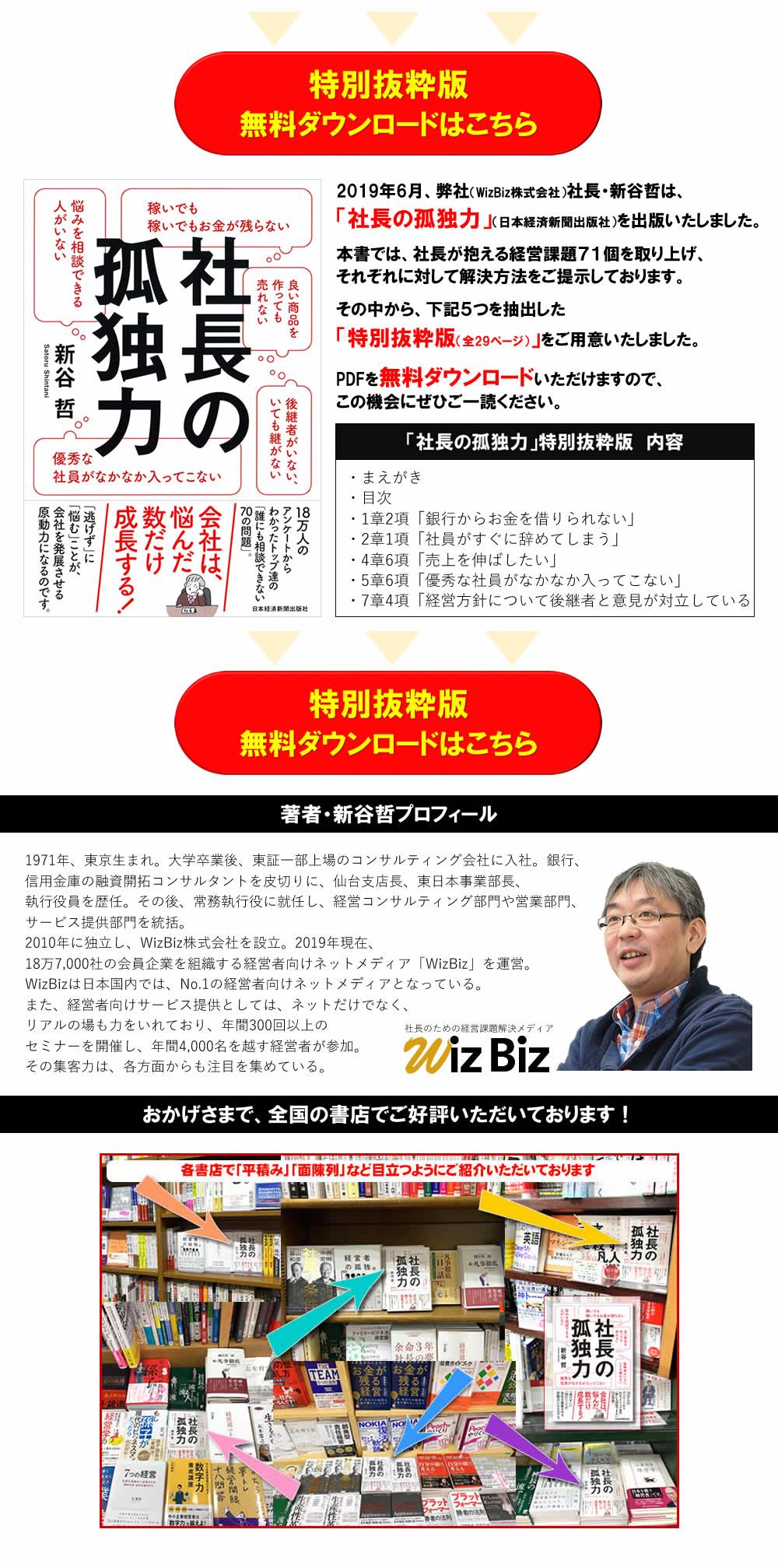事業を運営していると、資金繰りや設備投資・人件費確保など、資金調達をしなければならない場面が多々発生します。
しかし、「どこに相談すればよいか分からない」「金融機関にどう話せばいいか不安」と悩む経営者も少なくありません。
今回は、資金調達に関する相談先やサービスをいくつかご紹介します。
融資の成功率を高めるためのコツについても解説しますので、資金調達に不安を抱える中小企業や個人事業主の方は、ぜひ参考にしてください。
【最短即日・個人事業主もOK!】
資金繰りに困ったら「AGビジネスサポート」の無担保ビジネスローンがおすすめ。
銀行融資ではないため、銀行融資を断られた方でもビジネスローンを組める可能性は非常に高いです。
また、AGビジネスサポートなら原則無担保・無保証で即日融資を受けることができます!
※AGビジネスサポートは法人・個人事業主を対象としたビジネスローンです。

1971年東京生まれ。大学卒業後、東証一部上場のコンサルティング会社に入社。銀行、信用金庫の融資コンサルタントを皮切りに、仙台支店長、東日本事業部長、執行役員を歴任。その後、常務執行役に就任し、経営コンサルティング部門や営業部門、サービス提供部門を統括。2010年に独立しWizBiz株式会社を設立。現在、経営者向けネットメディア「WizBiz」を運営。国内では経営者の会員登録数でNo.1のメディアとなっている。また、経営者向けサービス提供としては、ネットだけでなく、リアルの場も力をいれており、年500回以上のセミナーを開催し、4000名を越す経営者が参加。18万人の社長アンケートから1000個の悩みを回収。
著書:社長の孤独力
資金調達をする前にプロへ相談した方が良い理由
資金調達をする際は一人で悩まず、まず専門家に相談しましょう。
専門家への相談には、融資の通過率を高めたり、資金繰りのリスクを最小限に抑えられるなど、さまざまなメリットがあります。
プロのアドバイスがあれば、金融機関との交渉を有利に進められるほか、経営戦略そのものの見直しにもつながるでしょう。
審査通過しやすい資料を用意できる
資金調達のプロに相談すれば、「審査に通りやすい資料を準備できる」というメリットがあります。
融資を申込む際は、決算書や事業計画書・資金繰り表などの資料が必要ですが、金融機関が重視するのは「書類の中身」です。
専門家と一緒に書類を整備すれば、信頼性の高い資料を用意でき、審査担当者にも良い印象を与えられるでしょう。
金融機関からの想定質問も教えてくれるため、適切な回答を用意できる点も大きなメリットといえます。
【関連記事】
【テンプレートつき】事業計画書の作り方をプロが解説!融資時に見られるポイントとキャッシュフローの見直し方
経営者の思考整理・戦略立案に役立つ
融資に詳しいプロに相談すれば、「なぜ資金が必要なのか?」「どのように返済していくのか?」など、経営者自身の思考整理が進みます。
事業の強みや競合との差別化ポイントを見直す機会にもなり、経営戦略そのものを練り直すきっかけにもなるでしょう。
結果として、融資交渉だけでなく、今後のビジネス展開にも有益なヒントを得られる可能性があります。
有利な借入条件を引き出せる
金融機関が提示する貸付条件が妥当かどうかは、自分だけでは判断しにくいことがあります。
プロに相談すれば、融資の成功事例などを教えてもらうことができ、金利や返済期間など有利な貸付条件を引き出せるかもしれません。
金融機関から提示された条件が厳しすぎる場合は、専門家のアドバイスを受けながら交渉できる場合もあります。
返済リスクの見極めができる
事業資金の借入では、「どれだけ借りられるか?」より「いくらなら無理なく返済できるか?」が重要なポイントです。
プロと一緒に事業計画を作成・検証すれば、計画の現実性や収支のバランス、返済リスクを客観的に判断してもらえるでしょう。
そうすることで、過剰な借入による資金繰り悪化や破綻を防ぐこともできます。融資だけでなく、補助金や助成金などのアドバイスを受けながら、自社にとって最適な資金調達手段を選ぶことができます。
【関連記事】
【テンプレートつき】返済計画書の作り方をプロが解説!事業資金の融資を成功させるために必要なポイントとは?
資金調達時の相談ができる窓口・サービス
資金調達に関する相談先には、どのようなところがあるのか詳しく見ていきましょう。
公的機関や商工会議所などを上手に利用できれば、無料で専門的なアドバイスが受けられます。
日本政策金融公庫
小規模事業者や個人事業主が資金調達の相談をするなら、国の公的機関である日本政策金融公庫を利用しましょう。
日本政策金融公庫は、中小企業や個人事業主に対する融資に特化した政府系金融機関であり、特に創業期や赤字決算の企業への資金支援に積極的です。
全国の支店窓口だけでなく、「創業サポートデスク」やオンライン相談にも対応しており、事前予約により専門の担当者との個別相談が可能です。
- 無料相談が可能で、申請前の書類チェックも受けられる
- 創業融資に特化したアドバイスが受けられる
- 他の公的支援制度との併用アドバイスも得られる
特に「新創業融資制度」などでは、自己資金要件や創業計画の妥当性が審査の鍵を握ります。
公庫の専門家に相談をすれば、事業計画書なども不備なく用意できるでしょう。
参考:日本政策金融公庫 相談予約、経営課題のご相談 (外部機関紹介)
【関連記事】
日本政策金融公庫の審査は厳しい?審査通過のために意識すべきポイントを解説
中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)
中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)は、事業承継やM&A・成長戦略の立案など、中長期的な経営課題にも相談にのってくれる公的機関です。全国9ヵ所に地域本部があり、対面・オンライン・メール相談が利用可能で、各種専門家との連携も充実しています。
【中小機構に相談するメリット】
- 中小企業診断士による支援が受けられる
- 事業再構築や承継対策など専門性の高いテーマにも対応してもらえる
- 公的機関とのネットワークを活用した継続的な支援が受けられる
中小機構は、「補助金活用」「事業再構築補助金の申請支援」「海外展開の伴走支援」など、さまざまな経営課題にも相談にのってくれます。
商工会議所
商工会議所および商工会は、小規模事業者や地場企業の経営課題に寄り添ってくれる地域密着型の経営支援機関です。
地域金融機関との強固なパイプがあるため、商工会経由で制度融資の申込や紹介が受けられる点も大きなメリットといえます。
- 無料または低額で資金調達相談が可能
- 地元の信金や地銀と連携した融資のアドバイスが受けられる
- 補助金申請支援や書類作成に関する相談ができる
特に「小規模事業者持続化補助金」など、地域支援型補助金の活用においては、商工会を通じた申請が有効です。
また、事業計画書の作成や、創業時の運転資金確保など、実務に即したきめ細やかなアドバイスが受けられるのも商工会議所ならではのメリットといえます。
よろず支援拠点
よろず支援拠点は、中小企業庁が全国47都道府県に設置した公的な経営支援窓口で、経営・資金調達・IT・販路開拓など多岐にわたる相談に対応しています。
専門家(中小企業診断士・税理士・ITアドバイザー等)による支援があり、課題が曖昧なままでも相談を受けられるのが大きなメリットです。
- 相談はすべて無料
- 分野横断型の専門家が在籍し、多角的なアドバイスが受けられる
- 漠然とした悩みでも相談可能。解決の糸口が見つけやすい
資金調達に関しては、金融機関に提出する事業計画書のブラッシュアップ、補助金・助成金の活用提案・返済可能性の検証など、実務寄りの具体的な支援が期待できます。
特に中小企業支援に精通した専門家によるアドバイスは、銀行からの評価を高めるうえでも有効でしょう。
参考:よろず支援拠点
資金調達前に相談(準備)しておくべきこと
資金調達を成功させるには、事前の準備が極めて重要です。
金融機関は、資金を必要とする背景や返済の見込み、企業の財務状況などを総合的に判断して融資可否を決定します。
そのため、融資を申込むまでに、資金使途や事業計画、財務の問題点などはは整理しておきましょう。
資金使途を明確にしておく
資金調達に関する相談をする際は、事前に「何にいくら必要なのか?」資金使途を明確にしておきましょう。資金使途が曖昧なままだと、審査において「計画が甘い」と判断される恐れがあります。
- 何に、いくら使うのかを数値で説明できるよう準備する
- 設備投資に使う場合は投資効果の裏付け資料を準備する
金融機関では、資金使途の妥当性を確認することから稟議がスタートするため、ここが曖昧なままだと、審査が前に進まず最悪の場合は審査落ちにつながります。
事業計画をチェックしておく
事業計画に妥当性があるかどうかは、金融機関が融資判断をするうえで重要なポイントです。どんなに素晴らしいビジネスでも、売上や利益計画が過大で現実味がないと、融資は否決されるでしょう。
- 売上予測や利益計画が過大すぎないか再確認する
- キャッシュフローと返済計画に妥当性があるかをチェックする
金融機関が注目するのは、キャッシュフローの安定性や資金繰りの見通し、そして返済能力の裏付けです。
提出した資料に、市場規模や競合分析に基づいた根拠があれば、審査通過の確率も高まります。
事業計画書提出後は修正が難しいため、事前に会計士など専門家の目でチェックしてもらうとよいでしょう。
財務上の問題点を整理しておく
事業者自身が自社の財務状態を正しく理解し、課題を把握しておくことは、金融機関との信頼構築につながります。
貸借対照表の数字を理解し、自己資本比率や固定負債比率など基本的な数字は押さえておきましょう。
- B/SとP/Lから課題を読み解き、説明できるようにしておく
- 財務上に問題点があれば、改善策を用意しておく
金融機関は、「財務リスクを正確に把握しているか?」「改善に向けた意識があるか?」を見極めようとします。
赤字や債務超過などの課題があっても、原因と今後の改善方針を説明できれば、審査上のマイナスは最小限に抑えられるでしょう。
問題点を自ら説明できる経営者は、金融機関にとって「伴走する価値がある」と判断されやすいのです。
融資を申込む金融機関を選んでおく
すべての金融機関が、同じ基準で審査を行うわけではありません。
「創業期であれば日本政策金融公庫」を、「自社の信用に不安があるなら信用保証協会」を選ぶなど、申込む金融機関を事前にチェックしておきましょう。
- 自社のステージと目的に合った金融機関を選ぶ
- 保証付き融資、プロパー融資、公的融資の違いを理解しておく
- 金融機関の担当者とコミュニケーションをとっておく
金融機関により支援の姿勢も異なるため、自社の状況とニーズに合った金融機関を選ぶことが重要です。
また、事前に金融機関の支店担当者と接点を持っておくと、手続きもスムーズに進むでしょう。
資金調達をするべきタイミング
資金調達は「資金が足りないときにだけ必要」と考えがちですが、実際には事業拡大や経営の安定化を図るタイミングで計画的に行うのが理想です
。特に、業績が好調なタイミングでは、金融機関の審査も通りやすいでしょう。
創業時
創業時は支出が集中する一方で売上が不安定なため、余裕をもった資金を調達しておきましょう。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」を活用すれば、担保や保証人がなくても資金を確保できます。
創業時に適切な資金調達ができれば、妥協せずに設備投資や人材補強を行うことができ、事業の成長スピードも加速できるでしょう。
設備投資時
事業拡大や、新たな需要に対応するための設備投資も、資金調達をすべきタイミングです。
投資によって生産性や利益率の向上が見込める場合、金融機関は将来的な回収の可能性を重視して、前向きに融資を検討します。
投資効果を裏付ける事業計画と収支シミュレーションが整っていれば、有利な条件での融資もしてくれるでしょう。
【関連記事】
個人で開業資金を調達するおすすめの方法は?いくら必要?
業績が順調な時
業績が好調なときは新たな借入を避けがちですが。むしろ好機ととらえて、積極的に融資を利用するのがおすすめです。
金融機関は、財務内容が健全な企業への融資に前向きです。業績が好調な時こそ資金調達をしておけば、突発的支出や経営環境の変化にも備えられるでしょう。
また、融資実績を積んでおくことで、金融機関との信頼関係も強化され、「将来の大型融資がスムーズになる」というメリットもあります。
銀行との関係を深めたいとき
銀行との関係性を強化するために、戦略的に小口融資を活用するという方法もあります。
金融機関は、単なる預金や事業決済だけでなく、融資取引の実績を重視する傾向があります。
今後、多店舗展開などの計画があるなら、あらかじめ取引実績を作っておけば、大型融資時にも有利に交渉を進められるでしょう。
資金調達の種類・方法
資金調達の方法には、融資や補助金のように外部から資金を得る方法や、自社資産を活用した方法もあります。
融資をはじめ、リースバックや助成金の活用など、いくつかの資金調達方法についても見ていきましょう。
【関連記事】
資金調達をする方法とそれぞれのメリット・デメリットは?経営者向けにプロがポイントを解説
金融機関や公庫からの借入
銀行や政策金融公庫などからの借入は、資金調達手段としてもっとも一般的です。
プロパー融資は銀行の裁量で実施されるため、貸付条件に柔軟性がありますが信用力が求められます。
銀行から借りられないなら、信用保証協会を利用した保証付き融資を検討しましょう。
また、創業期には日本政策金融公庫を利用することで、低金利かつ担保・保証人不要の融資が受けられる可能性があります。
各融資制度の特性を理解し、自社の事業フェーズに応じた選択が重要です。
【金融機関のからの借入|メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・大口資金調達にも対応してくれる ・保証協会を利用すれば融資が受けやすい ・政策金融公庫は創業期でも利用しやすく低金利 | ・プロパー融資は信用審査が厳しく時間もかかる ・保証協会融資は保証料の負担がある |
【関連記事】
銀行融資の審査は厳しい?審査基準や通過率を上げるためのコツを法人融資のプロが解説
アセットファイナンスによる資金調達
アセットファイナンスとは、自社保有の資産(不動産・機械・売掛債権など)を使って資金を調達する方法です。
売掛債権を担保とするABLや、ファクタリング、不動産担保融資などもアセットファイナンスに該当します。
アセットファイナンスは資産を活用するため、負債計上を避けられるのが特徴で、短期資金ニーズへの対応に向いています。
売掛債権や在庫を多く保有する企業にとっては、メリットの大きい資金調達方法といえるでしょう。
【アセットファイナンスによる資金調達|メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・自社資産を現金化できるため迅速な資金調達が可能 ・財務体質を悪化させず資金調達ができる | ・手数料が高い ・売掛先の信用力により審査結果が左右される ・長期の資金調達には不向き ・売掛債権の管理が面倒 |
リースバック
リースバックは、保有している資産をいったん売却して資金調達を行い、そのあと同じ資産をリースで使い続ける手法です。
資産を手放さずに資金調達ができるため、設備投資後に資金繰りが苦しくなった時に活用できる方法といえます。
売却損が出た場合は節税メリットがあり、リース料は経費計上できますが、所有権がリース会社に移るため資産利用の自由度が無くなる点には注意が必要です。
【リースバックのメリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・新たな負債を増やさず資金調達が可能 ・売却した後もそのまま資産を使い続けられる ・再購入オプションにより資産を買い戻せる契約もある ・売却価格が簿価より小さい場合は法人税の節税につながる | ・売却価格は市場価格よりも安くなる ・リース料の支払が発生する(固定費が増加する) ・所有権が移るため資産の自由な活用が制限される ・再購入オプションがない場合、契約期間満了後に利用できなくなる可能性がある |
助成金・補助金による調達
助成金や補助金は、国や自治体が企業を支援するために提供される返済不要の資金です。企業のIT化、新商品開発、創業支援などで広く活用されています。
自己資金に乏しい事業者にはメリットが大きい手法ですが、申込に必要な書類準備や実績報告などの事務負担が大きく、自由な資金使途が認められない点には注意が必要です。
【助成金・補助金による調達|メリットデメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・返済の必要がない ・資金負担なく新しい技術や製品の開発が可能になる | ・書類作成が大変で、審査に時間がかかる ・使途が限定され自由に使えない ・資金は立て替える必要があり後日助成金などが支給される |
資金調達時の相談まとめ
はじめて資金調達をするとなると、「利用する金融機関」「融資の条件が妥当性」などで迷うことも多いでしょう。
そんな時は一人で悩まず、金融機関の担当者や公庫の窓口、自治体などの「資金調達のプロ」に相談しましょう。
資金使途や事業フェーズに沿った、適切な資金調達の方法をアドバイスしてくれます。