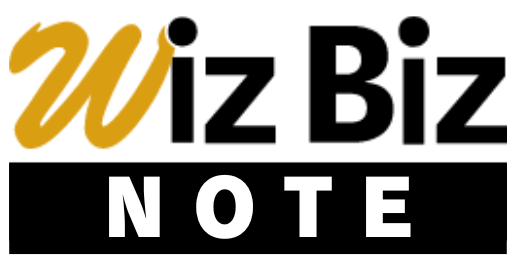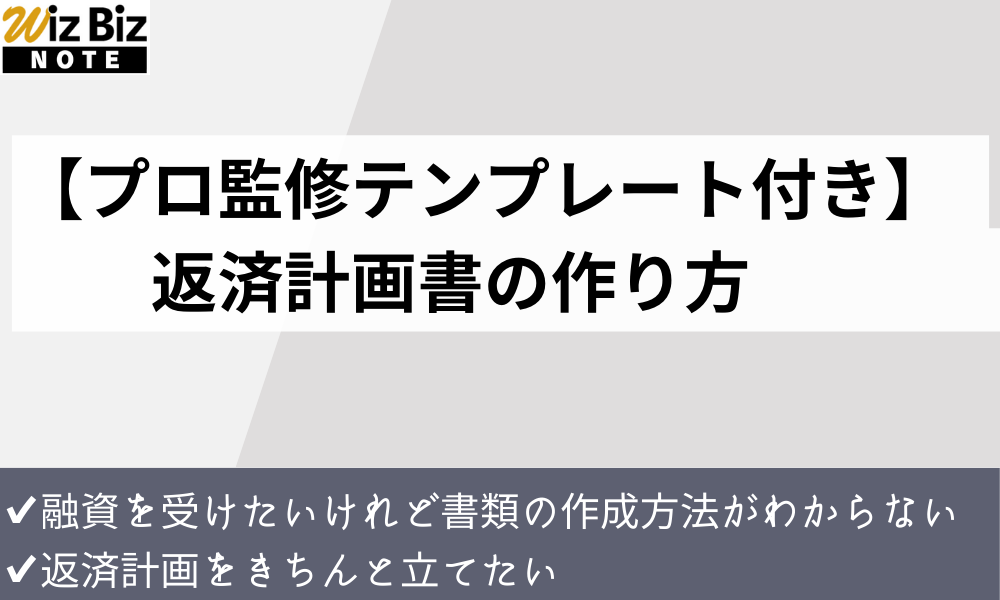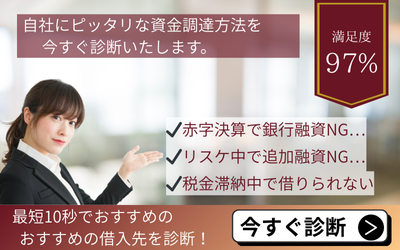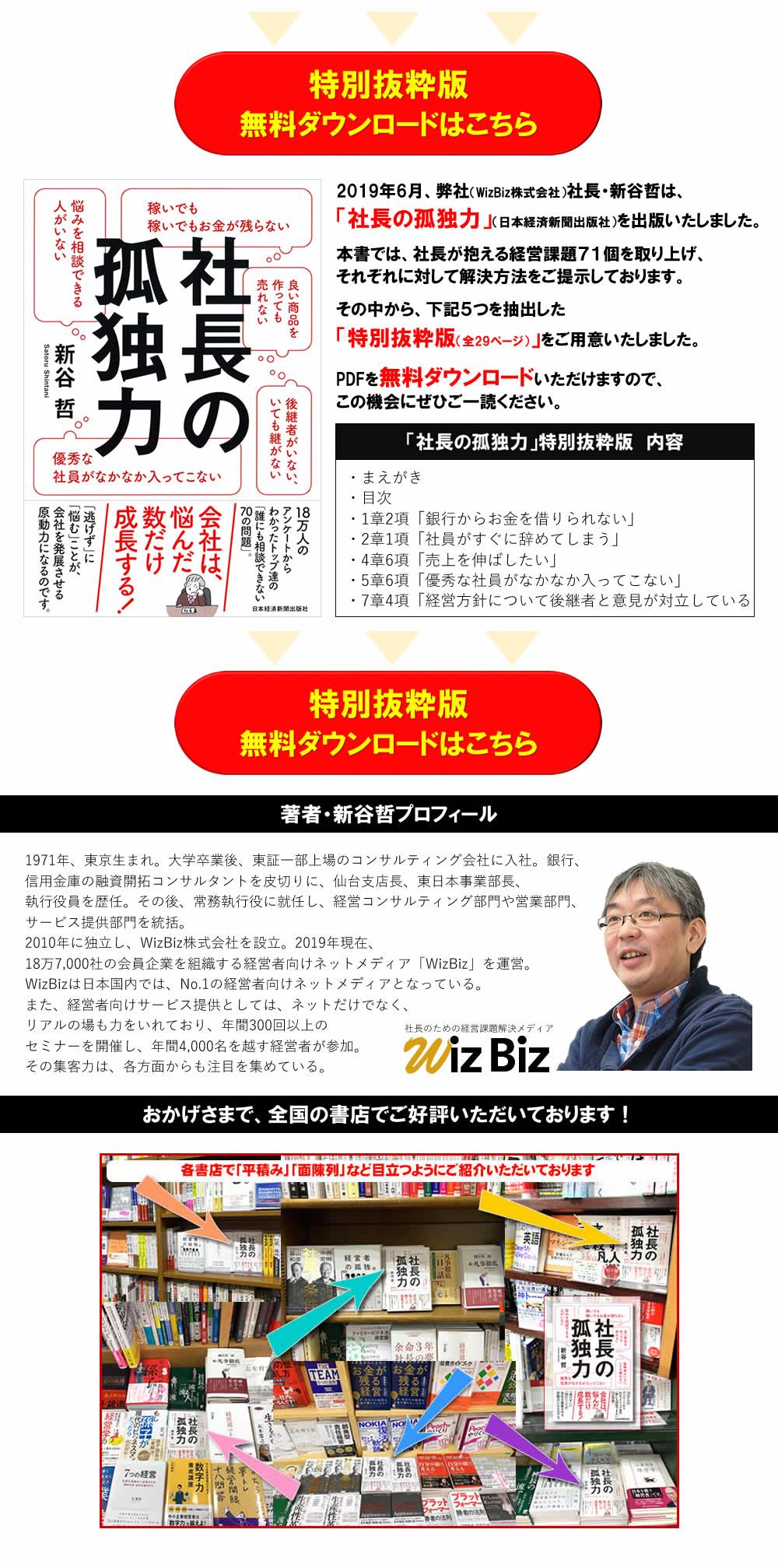事業運営において銀行や公的機関から融資を受ける際、しばしば提出を求められるのが「返済計画書」です。
返済計画書は、返済をどのように進めていくのかを示す資料であり、金融機関との信頼関係を築くうえでも重要な意味を持ちます。
今回は、返済計画書の作成のポイントと、返済が難しくなった場合の対処法、そしてキャッシュフローを改善する具体策について解説します。
元融資担当者が作成した「返済計画書のテンプレート」もダウンロードできますので、融資を申込む際の参考にしてみましょう。
◎返済計画書テンプレート
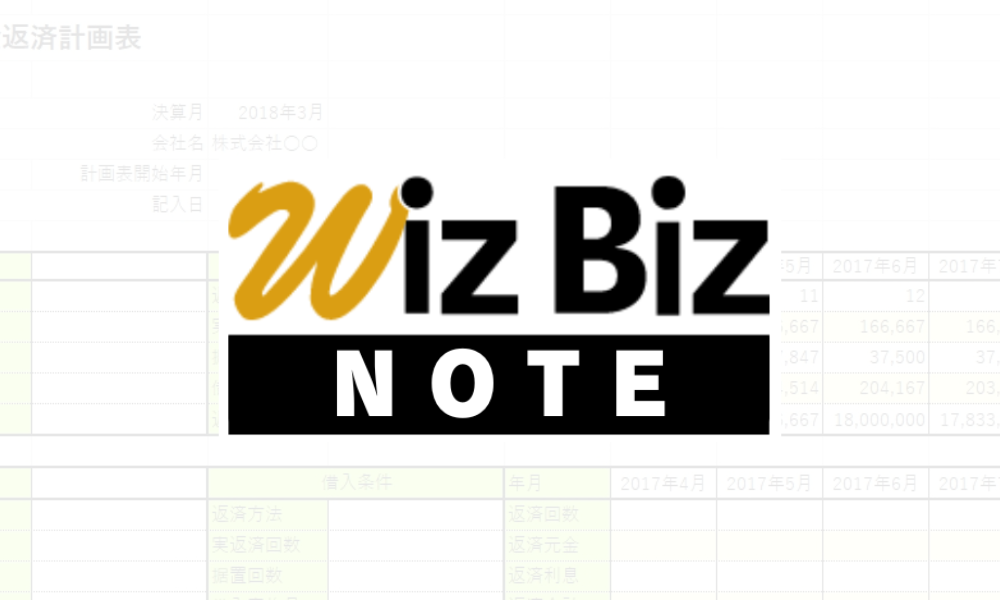
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、資金繰り表のテンプレートをお送りします。
返済計画書とは?
返済計画書とは、金融機関が融資を行う際に重視する「返済能力」を、根拠ある数字で示した書類のことです。
多くは、事業計画書の一部として提出されることが多く、企業がどのように毎月の返済を行い、完済を目指すのかを可視化する意味合いがあります。
返済計画書の役割
返済計画書の役割は、「融資を受ける側が確実に返済できる根拠を示す」ことにあります。
金融機関が融資判断をする際は、過去の実績(決算書や確定申告書)だけでなく、将来的に事業がどのように推移し、その結果として返済が問題なく進むかどうかを慎重に見極めます。
融資の審査時には、「100%返済計画書の提出が求められる」というわけではありません。
しかしながら、申込時に能動的に返済計画書を提出すれば、下記のようなメリットがあるのです。
売上予測や利益計画、既存借入金の返済スケジュールをまとめて提示することで、「借入額に見合う返済能力がある」ことを、金融機関に示せる。
例えば、新規設備導入を検討しているなら、その設備投資がどの程度の収益向上につながり、返済原資を確保できるかを返済計画書+事業計画書で説明できる。
大きな投資ほど長期的な返済になるため、計画書があると金融機関からの理解を得やすくなる。
複数の役員や株主がいる場合、「借りた資金はどのタイミングで、どれだけ返済していくのか」を共有しないと、資金繰りや意思決定に齟齬が生じる。
返済計画書は「無理のない返済計画」を示すうえでも重要。
なお、金融機関が発行する「返済予定表」「返済明細表」は、契約時に手交される書類を指すケースがほとんどです。
一方で、返済計画書は「事業計画書と返済予定表を合わせたもの」と理解すると良いでしょう。
返済計画書が求められるケース
返済計画書の提出を求められるケースとしては、下記4つのパターンが考えられます。
書面による提出が必須でなくとも、事業計画書内に返済の根拠や既存借入の状況を記載するよう求められる場合もあります。
ちなみに、建設業が短期資金(外注費支払・先行諸経費支払)などで資金調達する際には、提出を求められることはありません(工事請負契約書・注文書が必要)
大規模な投資を伴う融資などでは、金融機関は事業計画とあわせて「返済原資となる利益がどう生まれるのか?」を確認する必要がある。
その確認の過程で返済計画書を提出するよう求められる。
行政機関や地方自治体の補助金を申請する際に、既存借入金の返済状況や返済計画を盛り込むよう指示されることがある。
補助金・助成金を受けた後の返済リスクや事業継続性を確認するのが目的。
借入先の金融機関に他行との取引状況を示すために、返済計画書が求められる場合がある。
他の金融機関の借入明細が決算書からわからないとき、個別に返済計画を提示すると交渉がスムーズに進む。
既存借入金の返済が難しくなり、返済条件を見直す「リスケジュール」を申請するときに提出する。
今後どの程度の返済額なら現実的に支払えるのかを、金融機関に提示する。
返済計画書の入手先
返済計画書は、法律や規定で定まった統一フォーマットがあるわけではありません。
下記のような方法で入手または作成するのが一般的です。
融資申込時に「事業計画書や返済計画書を出してください」と言われた場合は、金融機関所定のフォーマットを提供してもらえるケースが多い
会計事務所との顧問契約があれば、既存の返済予定表を共有し、返済計画書に反映してもらう。実際、金融機関側は会計事務所が作成した資料を信頼する傾向が強い
Web上で公開されているフォーマットをダウンロードしてExcelなどで編集し、自社の事情に合わせてカスタマイズする
返済計画書は「自社の将来を数字でまとめる」資料であるため、はじめからExcel等で自作しても問題はない
◎返済計画書テンプレート
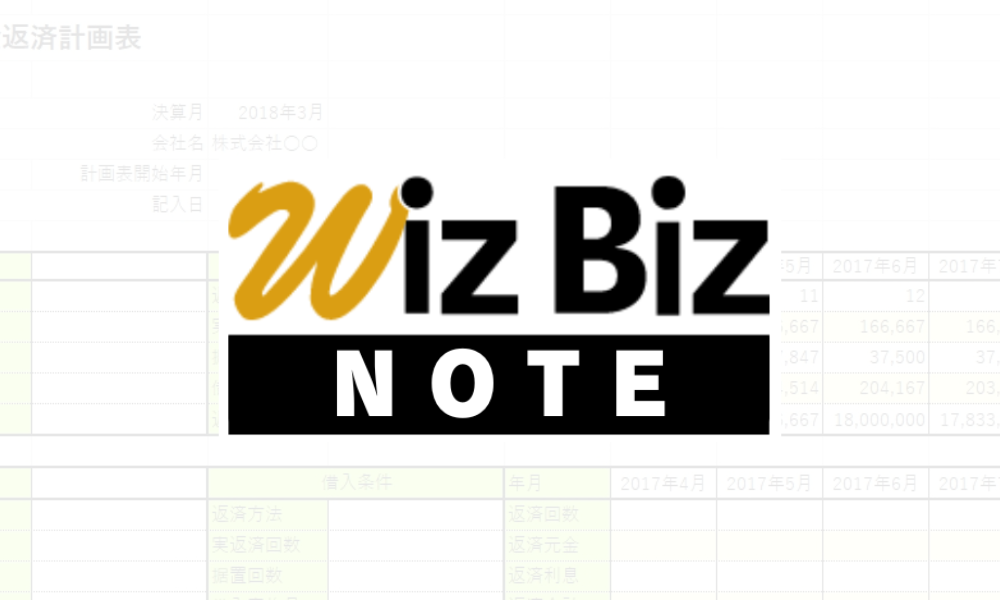
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、資金繰り表のテンプレートをお送りします。
返済計画書を作成した方が良い理由
返済計画書は、金融機関から求められた場合だけでなく、経営者が自主的に作成しておくべき書類の一つです。
資金ショートを未然に防ぐ目的もあるため、借入金がある、またはこれから融資を申込む際は、まず返済計画書で無理のない経営が続けられるのか慎重に検討しましょう。
理由1:金融機関へ返済の確実性を示せる
金融機関の融資審査で最も重視されるのは、「債権を確実に回収できるかどうか?」です。
過去の財務諸表だけでなく、これからの利益見込みと返済スケジュールに整合性があるかは、入念にチェックされるでしょう。
返済計画書を作成することで、既存借入金の返済状況と新規借入金の返済をどのように両立させるのかを具体的に示せるため、説得力が増します。
なお、返済計画書を自主的に提出しない場合は、金融機関が独自で返済計画を精査しなければいけません。
その結果、審査時間が長くなったり、十分な評価を得られず融資条件が厳しくなったりするリスクが発生します。
理由2:資金不足や過剰な借入を防げる
返済計画書は事業計画書の一部として作成されることが多いため、「資金ショートがいつ起こるのか?」や「どのくらい不足するのか?」を明確に把握できます。
また、実際には借りなくてもよい額を過剰に借りてしまうリスクも回避できるため、過剰債務を抑える効果も期待できます。
計画書を作らずに融資を申し込んだ場合、焦って借りてしまうことで、金融機関の一方的な条件を受け入れざるを得ないケースが少なくありません。
計画をきちんと立てておけば、必要な金額を、交渉しやすい条件で借りられる可能性が高まります。
理由3:経営判断を速やか下せる
決算期ごとに事業計画を見直す際、返済計画書があれば、将来のキャッシュフローをイメージしやすく、業績悪化や市場の変化に対して早めに手を打てるようになります。
また、返済に余裕が出てくる時期や、返済額のピークがいつなのかも把握しやすくなるでしょう。
返済金の流れをつかむことができれば、必要なタイミングで新たな投資を検討したり、逆に支出を抑えたりといった経営判断も迅速に行えます。
理由4:経費削減を中心とした効率化が図れる
企業が恒常的に増収増益を続けるのは難しいですが、返済計画書を参考に経費を見直し、利益を最大化することは可能です。
また、返済計画書を作る過程で、借入金ごとの金利を管理していけば、高金利の借入の借り換え検討もしやすくなるでしょう。金融機関同士を比較し、条件交渉を進める材料にもなります。
すべての金融機関の借入状況が一目でわかる資料があれば、事業拡大や新規投資の際に「どこから借りるのが得策か」を判断しやすくなります。
逆に返済計画書を作っていない場合、支出項目や金利の把握が曖昧になり、経費削減が進まない事態になるかもしれません。
理由5:事業再建がスムーズに進む
経営が厳しくなり、既存借入金の返済が滞りそうなときには、リスケジュール(返済条件の変更)を金融機関に申請する必要が生じます。
その際、具体的に「どれくらいの元金返済を減らせば、いつごろから安定した返済が可能になるのか?」を示せれば、金融機関も納得してリスケに応じやすくなります。
複数の金融機関から借入がある場合は、全行と同時に交渉を進めねばならないため、返済計画書がなければ手戻りや説明不足が起こりやすく、再建スピードが落ちてしまうでしょう。
ちなみに、リスケ対応は借入中の全金融機関が同時、かつ按分で痛み分けをするのが一般的です。
シェアの最も多いメインバンクがリスケの承認をすれば、他行もそれに従うのが通常です。
【テンプレート】返済計画書の書き方とポイント
返済計画書の具体的な書き方とチェックポイントについても見ていきましょう。
自社に合ったテンプレートを使えば、作業もスムーズに進み、金融機関との交渉もやりやすくなります。
返済計画書のテンプレート
返済計画書といっても、法令で定められた様式はありません。
今回は、どのような業種でも利用できる返済計画書のテンプレートを用意しました。事業計画書や資金繰り表などと併せて提出すると、金融機関による審査もスムーズに進むでしょう。
◎返済計画書テンプレート
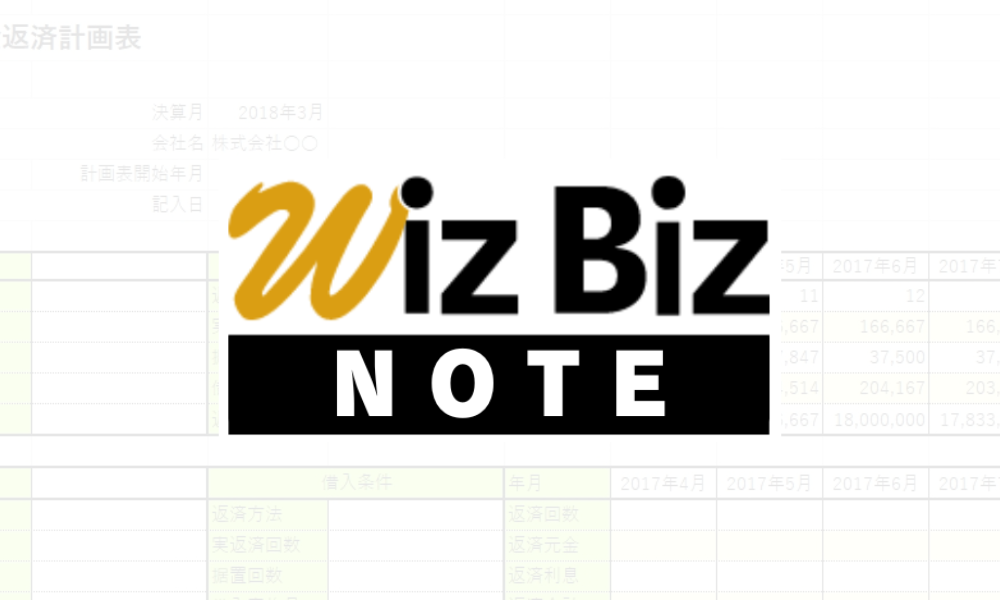
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、資金繰り表のテンプレートをお送りします。
返済計画書に書くべき要素
返済計画書は、大きく「契約内容をまとめた部分」と「返済明細欄」とに分けて記載するのが一般的です。下記の項目は、最低限含めましょう。
- 借入先
どこの金融機関・ノンバンクか?複数ある場合は一括して整理
- 契約日(借入日)
契約したタイミング
- 返済日(約定日)
毎月どの日に返済するか?
- 返済回数
トータル何回の返済を行うか?
- 最終期日
完済予定日はいつか?
- 借入金額
当初借入額は?
- 返済開始日(初回返済日)
初回の返済はいつからか?
- 年率(金利)
何%の利率で返済するか?
これらが曖昧だと「いつ、いくらを返済すればいいのか」を見失う原因になり、延滞リスクや資金ショートを引き起こしかねません。また金利は利益に直結するため、正確に記載しましょう。
上記の要素をきちんと整理すれば、金融機関だけでなく社内でも返済状況を正確に共有できるようになります。
「どこで資金繰りが苦しくなるか」「いつ追加借入が必要になりそうか」も、早期に見極められるでしょう。
返済計画書を書くときのポイント
返済計画書を作る際は、下記の点にも気を配りましょう。
- 項目(要素)を正確に記載する
返済日や返済額、回数などは資金計画の根幹となるため、誤りがあると金融機関の信用を損ねる
- 返済内訳を明確に示す
「元金と利息が毎月いくらになるのか」を分かりやすく提示すると、利息負担の大きさや完済までの見通しが立てやすくなる
- 事業計画とリンクさせる
設備投資の効果や売上増加の根拠など、将来のキャッシュフローを見込む根拠をきちんと示すと、金融機関への説得力が向上する
- 金融機関から交付された返済予定表を添付する
自作の返済計画書だけでなく、金融機関が発行した正式な返済予定表をあわせて提出することで、信頼性がアップする
誤ったデータや実現性の乏しい計画を書いてしまうと、むしろ金融機関からの評価が下がったり、社内の混乱を招く原因になるため注意が必要です。
返済計画書の予定通りに返済することが難しくなった場合
事業を運営していると、計画どおりの売上や利益を確保できず、返済に支障をきたす事態に陥るかもしれません。返済が難しくなったら、下記4つの対策を検討してみましょう。
- 対策1:「借り換えを検討する」
- 対策2:「経費の削減」
- 対策3:「資産の売却」
- 対策4:「返済計画の再調整(リスケの検討)」
対策1:借り換えを検討する
毎月の返済が重荷になり、資金繰りが逼迫しているなら、借入金を借り換えて月々の返済額を軽減する方法があります。
複数の金融機関から借り入れている場合は、1行にまとめる「一本化」を検討すると交渉がしやすくなるでしょう。
ただし、金融機関は「条件緩和による借り換え」を渋る傾向が強く、貸出条件緩和債権(※)として扱われる可能性があります。
借り換えを交渉するなら、返済が滞りなく行えている段階で、資金ショートのリスクを早めに提示し、交渉を始めるのが良いでしょう。
※貸出条件緩和債権とは……返済が困難な債務者に対し、金融機関が返済条件を緩和した債権のこと。
対策2:経費の削減
人件費や役員報酬の見直し、賃借料や外注費といった固定費の削減など、支出を圧縮することで返済原資を確保する方法もあります。
ただし、経営が苦しくなっている場合、経費削減だけで資金繰りを改善するのは難しいでしょう。
売上増加や仕入条件の見直しなど、収益面にもテコ入れをしないと、根本的な改善にはつながりません。
それでも、短期的には「経費カット」が、もっとも迅速に効果を出せる手段です。
返済計画書においても、どの費用をどの程度削れば返済に回せるかを具体的に示し、金融機関にも努力の姿勢を見せることが大切です。
対策3:資産の売却
遊休不動産や余剰の営業車両など、資産として保有しているものを売却すれば、まとまった資金が確保でき、返済に充てられる可能性があります。
使っていない土地や建物がある場合、速やかに現金化して負債を圧縮すれば、利息負担も減らせるでしょう。
とはいえ、固定資産は一度売却すると再取得が難しいうえ、買い手がすぐにつくとは限りません。
資産売却だけで根本的な事業改善が見込めないケースも多いため、あくまで最後の手段として検討するのが現実的といえます。
対策4:返済計画の再調整(リスケの検討)
どうしても返済が追いつかないときは、金融機関に「元金据置」や「返済額の削減」を含む、返済条件の見直し(リスケ)を申し入れましょう。
リスケは経営が厳しい企業を救済するための一時的な処置です。リスケに応じてもらうためには「毎月いくらなら返済可能で、いつから再び正常返済できるのか」を説明する返済計画書が必須になるでしょう。
ただし、一度リスケをすると新規借入は事実上困難になり、金融機関の格付けでも「要注意先」に分類されてしまいます。
複数行から借入をしている場合は全行で協調しなければならず、各金融機関に根回しも必要になるかもしれません。
リスケをするにしても、返済できる最小限の金額を提示して、破綻を回避しながら再建を目指すことを考えましょう。
◎返済計画書テンプレート
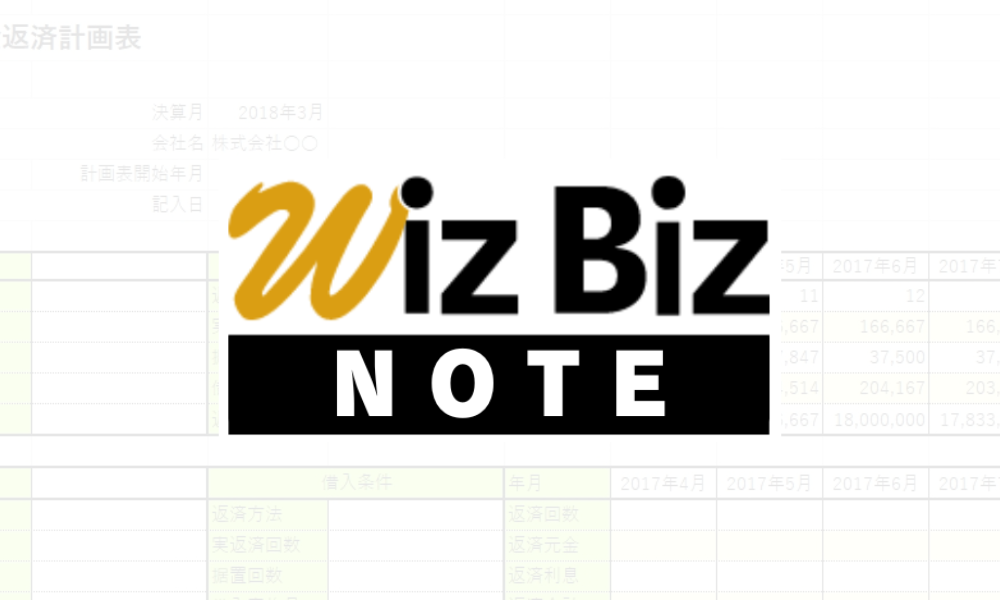
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、資金繰り表のテンプレートをお送りします。
返済計画書と資金繰り表をうまく活用してキャッシュフローを見直す方法
返済が苦しくなってから対策を考えても、間に合わないケースがほとんどです。
リスケなどを検討する前までに、キャッシュフローを見直す方法も考えておきましょう。
特に建設業や運送業では、売上とコストの発生タイミングが偏りやすいこともあり、一度資金繰りが苦しくなると抜本的な対策が必要になります。
売上原価の改善に努める
売上を伸ばすのが難しい局面でも、粗利益率を向上させることでキャッシュフローを安定させることができます。
経費削減だけに頼るのではなく、売上原価を見直すことで根本的な利益体質を強化していくのがポイントです。
建設業の場合、工事にかかる外注費や資材費が収益を圧迫する傾向があります。外注先の選定や契約形態を見直し、必要以上に外注コストが膨らまないように工期管理を徹底しましょう。
また、複数の業者に分割発注をすれば単価交渉の余地が広がり、資材費の削減にもつながります。
資材は、まとめ買いによるロット割引を狙う一方で、保管コストや在庫リスクも考慮し、最適な発注量を検討しましょう。
運送業では、燃料費と車両維持費が大きな負担になりがちです。ドライバーへのエコドライブ指導や配送ルートの最適化を行い、無駄な走行距離をできる限り削減することで燃費の改善を図ります。
また、老朽化が進んだ車両を燃費効率の良い車両に更新することも、中長期的な視点からは有効な手段です。積載率や運行ダイヤを見直し、同じ人数・同じ台数でより多くの荷物を運べる体制を整えることで、コスト削減も図れるでしょう。
支払・回収条件を調整する(売掛サイト・買掛サイトを調整する)
キャッシュフローが厳しくなる大きな要因のひとつに、「売掛金の回収時期と買掛金(仕入や外注費など)の支払い時期のズレ」が挙げられます。
これを解消するためには、取引先との交渉で売掛サイト(回収期限)を短くし、買掛サイト(支払い期限)をできるだけ延ばす方向を検討しましょう。
建設業では、注文主からの入金が工事の完了後や検収後になるケースが多く、工期が長引くと外注費や材料費の支払いが先行してしまいます。
そこで、発注者に対しては工程ごとの部分的な検収・部分請求を交渉し、早期の売掛金回収を目指しましょう。
一方で、下請業者や資材業者には、支払いサイトを一定の範囲で猶予してもらえないか相談してみるのも一案です。
支出項目の見直し
キャッシュフローの改善をめざすうえでは、支出項目の精査も欠かせません。
すでに大きな経費削減を行っている場合でも、定期的に見直しを続けることで無駄な出費が浮き彫りになることがあります。特に通信費や接待交際費、保険料、リース料などは検討余地があるかもしれません。
たとえば、運送業の場合なら、有料道路代や車検費用などの間接経費を削減できるか再検討してみましょう。
高速道路の利用頻度を最適化したり、点検・整備の頻度を適切に保つことで、不測の整備費用が発生するリスクを抑えることもできます。
役員報酬を下げる方法もありますが、役員報酬の増減は「利益操作ではないか」と金融機関に疑われるリスクがあります。
どのタイミングで、どのくらいの意図をもって役員報酬を見直したのか、理由を明確にしておくと資金調達の際にも信用を損ねにくくなります。
余剰資金の活用を検討する
現預金が潤沢にあるなら、金利の高い借入金を繰上返済して、利息負担を軽減するというのもキャッシュフロー改善の一手です。
ただし、どの程度の資金を「余剰」とみなすかは、リスクを踏まえて慎重に判断しなければいけません。
大きな余裕資金がある場合には、投資による運用益を狙う選択肢も考えられますが、建設業や運送業など景気や季節要因に左右される業種においては、まずは経営の安定を優先すべきです。
余剰資金を積極的に使いすぎた結果、急な受注増や燃料費の高騰に対処できなくなると、本末転倒となってしまいます。
自社の安定経営を最優先に考えながら、繰上返済や投資による運用などを検討するとよいでしょう。
返済計画書の作り方まとめ
返済計画書は、金融機関からの融資をスムーズに引き出すだけでなく、経営者自身が自社のキャッシュフローを俯瞰して管理するのに有効なツールです。
返済計画書を上手に利用できれば、金融機関の信頼を得ながら無理のない経営判断を下すことができます。
万が一予定通り返済が難しくなったときも、リスケや借り換えなどの交渉がやりやすくなり、事業再建の可能性も高められるでしょう。
◎返済計画書テンプレート
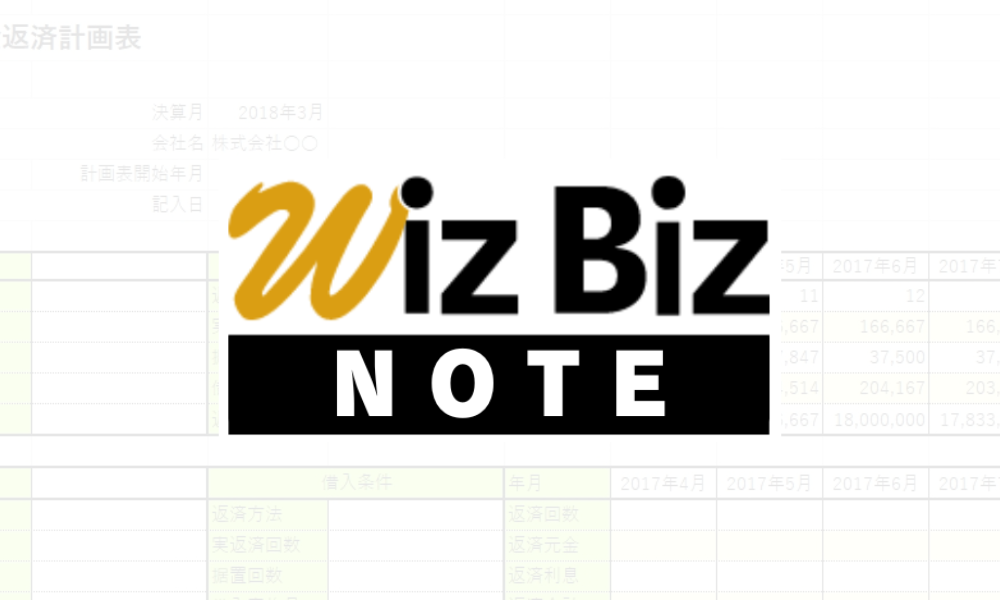
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、資金繰り表のテンプレートをお送りします。