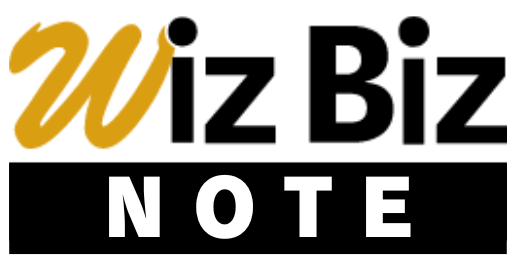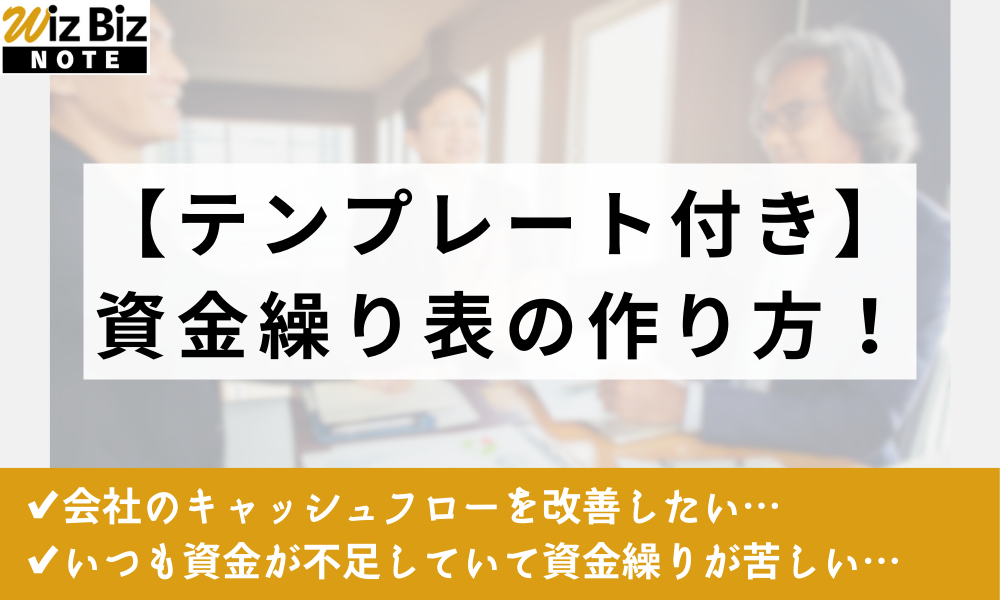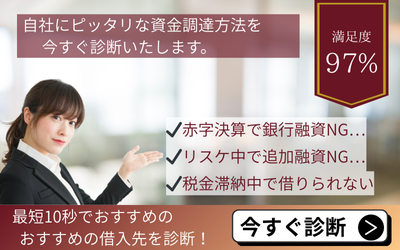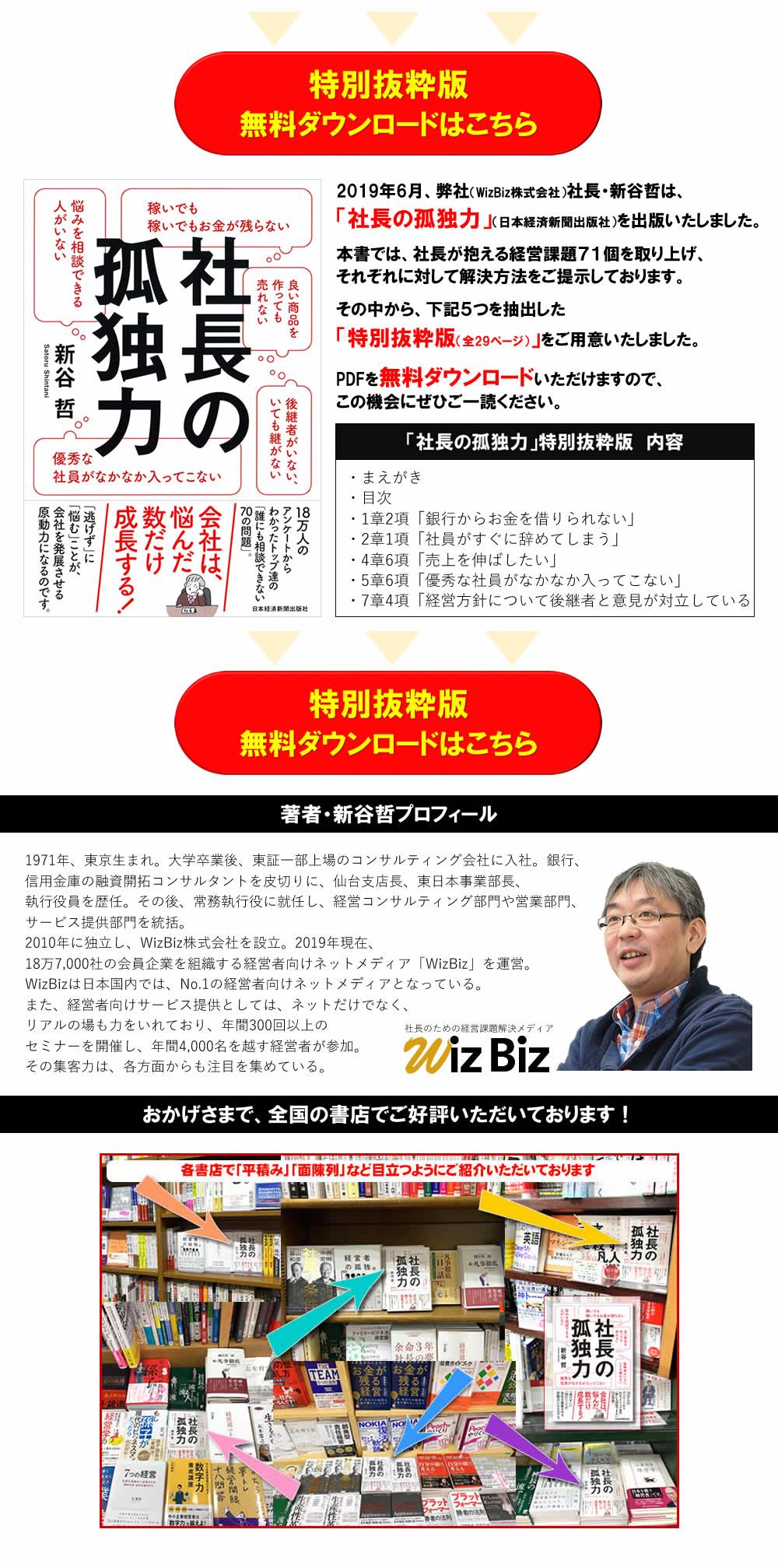資金繰り表は、事前に現金の流れを「見える化」するための重要な書類です。融資時に金融機関へ提出するケースもあるため、上手に作り込めば信用度を高めるアピール材料にもなります。
今回は、資金繰り表の作り方や活用メリットを元銀行員がプロ目線でわかりやすく解説し、すぐに使えるテンプレートもご用意しました。
キャッシュフローの見直しや、資金不足リスクの早期発見に役立てながら、金融機関から融資を引き出しましょう。
◎資金繰り表テンプレート
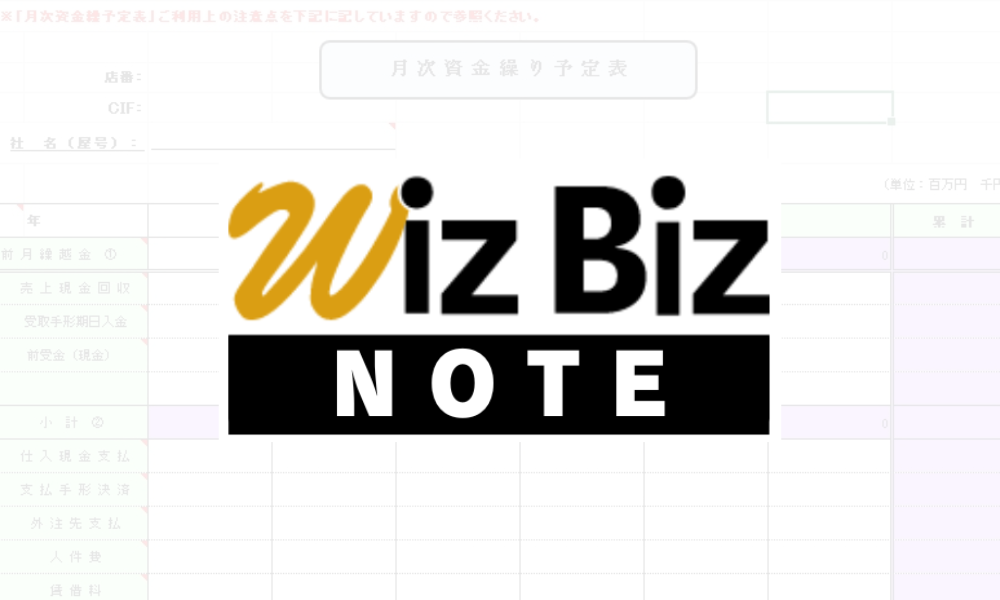
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、資金繰り表のテンプレートをお送りします。

WizBiz株式会社 代表取締役
経歴
1971年東京生まれ。大学卒業後、東証一部上場のコンサルティング会社に入社。銀行、信用金庫の融資コンサルタントを皮切りに、仙台支店長、東日本事業部長、執行役員を歴任。その後、常務執行役に就任し、経営コンサルティング部門や営業部門、サービス提供部門を統括。2010年に独立しWizBiz株式会社を設立。現在、経営者向けネットメディア「WizBiz」を運営。国内では経営者の会員登録数でNo.1のメディアとなっている。また、経営者向けサービス提供としては、ネットだけでなく、リアルの場も力をいれており、年500回以上のセミナーを開催し、4000名を越す経営者が参加。18万人の社長アンケートから1000個の悩みを回収。
著書:社長の孤独力
資金繰り表とは?
資金繰り表とは、「自社の現金の流れを見える化し、将来の資金ショートリスクを未然に防ぐために作成する書類」です。
季節的に支払いが増える月や、売掛金の回収が遅れがちな時期などをあらかじめ把握することで、スムーズな経営判断ができ、金融機関に融資を依頼する際のアピール材料にもなります。
資金繰り表を作成する目的とメリット
資金繰り表を作成する最大の目的は、「現金の過不足(とくに不足)を把握し、支払いをスムーズに行うため」です。
支払当月になり慌てて資金を調達しようとすると、取引先や金融機関との交渉が難しくなるばかりか、信用にも関わります。あらかじめ資金繰り表を用意しておけば、「季節的な要因で支出が多くなるタイミング」や、「売上は計上できているのに、なぜか資金が足りない原因」などが把握でき、事前に対策を打つことも可能です。
資金繰り表を定期的にチェックし、翌月繰越金の動きを追えば、資金面での経営の安定性や事業の成長性を客観的に確認できます。これは、決算書やキャッシュフロー分析のような「事後に分析を行うための資料」とは異なり、資金繰り表が「事前的」な将来予測に焦点を当てているためです。
資金繰り表は、経営状況そのものの良し悪しを判断するものではなく、あくまでも現金の動き(キャッシュフロー)の把握を目的とした書類です。決算書で利益が出ている企業でも、売掛金の回収遅延や、買掛金の先行決済などにより、現金が不足しているケースは少なくありません。
いわゆる「黒字倒産」が起きる原因も、こうした現金管理の甘さにあるといえます。資金繰り表をこまめに作成し、収支のズレを早期に発見できれば、事前の資金手当(調達など)をタイムリーに行えるため、経営リスクを大幅に抑えられます。
資金繰り表に記載するべき内容
資金繰り表には、下記の項目を記載するのが基本です。「売上」や「月初残高」から始まり、「経常収支・経常外収支(設備投資に伴う支出)・財務収支」などを経て、最終的には「翌月繰越金」を算出する流れが一般的です。
【資金繰り表に記載するべき内容】
| 売上 | 企業のメインとなる営業収益。入金時期や回収サイトを明確にしておくことで、月単位の資金流入が予測しやすくなる |
|---|---|
| 月初残高 | 前月から繰り越された資金のスタート額。この数字が正確に把握できていないと、支払い余力や追加資金が必要となるタイミングを見誤る |
| 経常収支 | 通常の営業活動による入出金を指す。主に売掛金の回収や仕入れ・外注費などの一般的な経費が含まれ、毎月のキャッシュフローの基礎となる |
| 経常外収支(設備収支) | 設備投資や固定資産の取得など、通常の営業とは直接関係しない大きな支出・収入を示す。長期の設備資金を調達する際は、この項目を明記するのが一般的。一方、短期資金の申込時には、簡易的な資金繰り表を提出することが多いため、この欄がない様式も存在する |
| 財務収支 | 借入金の返済や新たな融資の受け入れなど、金融機関との取引に関わる出入りを記載する。企業が資金を調達するうえで欠かせない部分であり、返済計画を明確にすることで融資時の信用度が高まる |
| 翌月繰越金 | 当月末時点で残る資金額で、翌月の「月初残高」として繰り越される重要な数字。黒字(プラス)か赤字(マイナス)かによって、経営状態の安定度や将来的な資金不足のリスクを把握できる |
ちなみに、資金繰り表には金融機関や用途によって多様なフォーマットが存在します。
- 月単位の計画だけを簡潔に記載したもの。
短期資金の申し込み時に使われることが多い。
- 月単位の予定に加えて、その後の実績もあわせて記載する形式です。
予定と実績の乖離を一目で比較できるため、管理面で優れています。
資金繰り表を作成する際は、企業の規模や資金需要、金融機関の審査方法などに応じて、適切な表を作成しましょう。特に、設備資金など長期にわたる融資を申込む場合は、経常外収支も含めた詳細な資金繰り表を作成して提出すると、金融機関からの評価が高まります。
資金繰り表はいつ使う?作成のタイミング
資金繰り表の活躍する場面は大きく分けて、「1:事業者自身が現金の過不足を把握したいとき」と、「2:金融機関が融資判断のために資料を求めるとき」の2つです。
- 現金の過不足を確認したいとき
毎月の支払いが予定通りに行えるかを判断し、資金不足のリスクを早期に察知するために作成します。 - 翌期の事業計画を立てるとき
決算終了後に1年間の経営方針や売上目標を定める際、合わせて資金繰り表を作成するのが理想です。しかし、実際には多くの中小企業が資金繰り表を作成していないのが現状です。 - 作成にかかる期間と注意点
資金繰り表は、外部の税理士や会計士に丸投げして作れるものではなく、受注状況や支払いスケジュールを熟知している経営幹部が中心となり、月単位でしっかりと作成していく必要があります。
- 融資の検討資料として
事業者が融資を申し込む際、銀行などの金融機関は、資金繰り表を用いて資金調達の根拠や返済原資を確認します。将来、確実に回収できる見込みがあるかどうかを見極めるためです。 - 長期融資と短期融資で提出要件は異なる
長期資金(返済期間1年超)の場合は、原則として提出が求められません。毎月の営業利益金で返済するイメージのため、詳しい短期的キャッシュフローまで確認しないケースが一般的です。一方で、短期資金(1年以内に一括返済)の場合は、必ず資金繰り表の提出が必要です。いつ資金が足りなくなり、いつ返済原資が確保できるのかを明確に示さなければ、審査を通過しにくいのが実情です。
ちなみに、立替払いが多い建設業者や下請業者などでは、短期資金の借り入れと返済を繰り返すケースも多く、金融機関から資金繰り表を提出するよう頻繁に求められます。そのため、簡易資金繰り表を常に更新しておき、契約書や注文書などを参考に金融機関側でも再調整して融資承認を得る流れが一般的です。
資金繰り表の提出は、金融機関に限らず社内の経営管理にも欠かせないツールです。短期・長期の区分を理解し、「必要なタイミングで正確なデータを盛り込むこと」が、円滑な資金調達と安定経営への近道といえます。
◎資金繰り表テンプレート
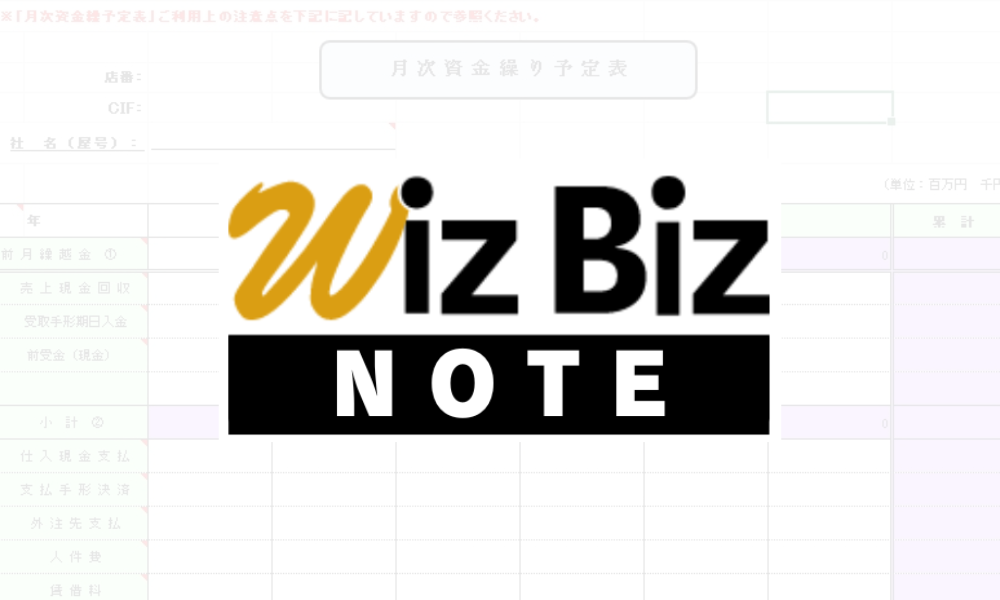
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、資金繰り表のテンプレートをお送りします。
資金繰り表を作成したほうが良い理由
資金繰り表を作成すれば、毎月の資金不足リスクを早期に把握できるだけでなく、金融機関からの信頼度も高めやすくなります。また、経営判断のスピードと正確性が向上し、黒字倒産などのリスク回避にも有効です。
ここでは、資金繰り表を作成したほうが良い4つの理由を解説します。
理由1:月次ベースでの資金不足を早期に発見できる
資金繰り表を作成したほうが良い最大の理由は、月次ベースで資金の過不足(とくに不足)を一目で確認するためです。
資金繰り表の下部には、「翌月繰越金」という欄があり、この数字が赤字(マイナス)を示すようであれば、事前に資金手当てや資金繰りの再調整が必要になります。対策を講じずに放置すると、取引先や従業員への支払いが間に合わず、経営に大きな影響を及ぼしかねません。
また、売掛金と買掛金の支払いサイトを見直すための資料としても役立ちます。「売掛金の回収が遅れている」、あるいは「買掛金の支払いを早めてしまっている場合」など、収支のタイミングを改善できる余地がないかを可視化できるのが資金繰り表の強みです。
なお、翌月繰越金が黒字になったとしても、その金額の大きさに注目することが大切です。黒字の幅を把握しておけば、経営にどれほどの支払い余力があるかを客観的に判断できます。
理由2:金融機関からの資金調達を有利に進められる
金融機関は、返済に少しでも懸念のある企業に融資を行うことはありません。
企業の経営状況を把握するため、まずは決算書や試算表といった「過去の実績」をチェックして「融資しても問題なく回収できるだろう」と判断するのが一般的です。しかし、これらの書類からは、未来の入出金やキャッシュフローを十分に読み取ることができません。
一方、資金繰り表は将来の資金の流れを可視化する資料であり、企業の先行きや資金不足リスクを確認するのに役立ちます。そのため、金融機関に対して「返済原資が確保できる根拠」を示すことができ、融資審査を有利に進められるのです。
なお、決算書や試算表は、意図的に「良くも悪くも見せることが可能」ですが、資金繰り表はあくまでも現金の実際の入出金を記載するため、操作の余地がありません。返済原資が明確にわかる資金繰り表を提示することで、金融機関からの信頼度が高まり、融資獲得の可能性を広げる効果も期待できます。
理由3:経営判断が容易になる
資金繰り表で翌月の現金残高が増加傾向にある場合は、設備投資や従業員への還元など、資金を有効に活用する施策を検討しやすくなります。一方で減少傾向が続いているようであれば、経費削減や売掛・買掛サイトの見直しなど、支払いと入金のタイミングを調整する具体策を講じる必要があるでしょう。
資金繰り表の構成(経常収支・経常外収支・財務収支)ごとに入出金の内容を分類しておけば、「どの部分に支出が集中しているのか?」あるいは「収入を増やせる余地があるのか?」を細分化して把握できます。これにより、経営判断の精度がさらに高まります。
理由4:事業の健全性が把握できる
決算書で黒字を計上している企業でも、現金が不足しているケースは意外と多いものです。これは、決算書や試算表と資金繰り表では「収支を計上するタイミング」が異なることが原因です。
資金繰り表は、現金が実際に出入りした段階で記載するため、黒字決算であっても実際のキャッシュが追いついていない状況が浮き彫りになります。こうした現金不足の実態を客観的に把握できるのは、資金繰り表ならではのメリットといえます。
ちなみに、決算書には回収が遅れている(あるいは回収できない)売掛金も含まれます。一方、資金繰り表は実際の取引ベースで作成するため、決算書では見えにくい企業の真の健全性が把握できます。
◎資金繰り表テンプレート
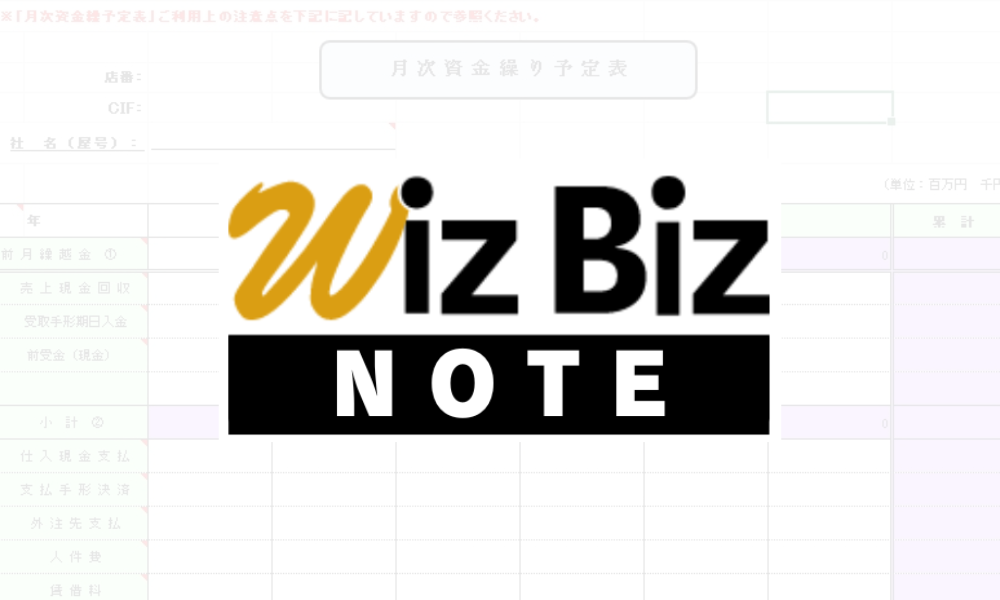
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、資金繰り表のテンプレートをお送りします。
資金繰り表を作るために必要な資料
資金繰り表を正しく作成するには、過去の業績や現金残高、借入金の返済予定などを把握できる資料が欠かせません。これらをもれなく準備することで、より正確なキャッシュフロー予測を立てられ、金融機関からの信用力も高まります。
必要な資料1:決算書
資金繰り表を作成するうえで、まず参照すべきなのが決算書です。決算書は、前期までの業績を示す「事後的」な資料ですが、取引先や従業員数・売掛・買掛サイトなど、継続してほぼ変化しない要素を把握するためには欠かせません。この情報をもとに、実効性と実現性の高い資金計画を立てることができます。
決算書は、あくまで過去の結果をまとめた資料である一方、資金繰り表は今期の予測を示す資料です。両者を組み合わせることで、より現実的な資金計画を立案できます。無理に売上増加を見込むのではなく、前期実績をベースに適正な数値を設定するのが大切です。
同業他社との競争が激化している場合など、急激な売上拡大を前提とした資金繰り計画を作ってしまうと破綻を招きます。現実的な計画を練りましょう。
必要な資料2:試算表(合計残高試算表)
資金繰り表を作成するときには、試算表(合計残高試算表)も確認しましょう。
試算表は会計記録の整合性を確かめるための帳簿で、決算書とは異なり期中の実績を月次ベースで把握できます。とくに、毎月発生する固定費や、そのほかの経常支出を予測するうえで重要な参考資料となります。
決算書をベースに作成した資金繰り表に、試算表で確認できる「月次の実績推移」を反映することで、より実現性と精度の高い数値を盛り込めます。 試算表は過去の実績を細かくチェックできるため、毎月の諸経費(固定費)の確認にも活用できるでしょう。
なお、中小企業では試算表の作成を顧問税理士に依頼するケースが多く、事業主が必要書類を提出しないと作成が遅れるという問題がよく発生します。 直近の試算表を求めても、作成時点から数カ月前の実績分しか確認できないことも珍しくありません。事業融資を依頼する予定があるなら、試算表のタイムラグを踏まえたうえで、早めに作成してもらうよう依頼しておきましょう。
必要な資料3:現金出納帳・預貯金通帳
資金繰り表で前月繰越金を正確に記載するためには、現金出納帳と預貯金通帳の両方で確認した正味の残高を把握する必要があります。これらの書類に記載されている合計金額が、正しい月初残高のベースとなるため、資金繰り全体を左右する重要なポイントとなります。
- 現金出納帳
会社や個人事業で発生する現金の入出金を、発生したタイミングで記録する帳簿。現金の流れをリアルタイムで追うことができる。
- 預貯金通帳
銀行口座の残高や取引履歴を確認するための通帳やWeb明細などの書類。毎月の入出金のトレースに加え、口座残高を正確に確認できる。
なお、前月繰越金の計算を間違えると、そのあとの資金計画に大きく影響を及ぼします。現金出納帳と預貯金通帳の合計金額を厳密に確認して、資金繰り表の信頼性を高めましょう。現金出納帳は、入出金があったタイミングで迅速に記録するのが理想です。あとからまとめて記入すると、記帳ミスが起こりやすくなるので注意が必要です。
必要な資料4:元帳(売上帳・仕入帳・売掛金台帳・買掛金台帳)
資金繰り表に現金の入出金を正確に記載するためには、元帳類のデータが欠かせません。下記のように取引内容ごとに管理することで、売上や仕入、未回収の売掛金、未払いの買掛金などをタイミング別に把握できます。
- 売上帳
すべての売上取引を記録し、収益の把握と管理を行うための書類。売上の入金サイクルを意識することで、今後の資金流入が予測しやすくなる。 - 仕入帳
仕入取引を一括管理し、原価や費用の把握をおこなう。仕入れのタイミングや額を整理すると、資金の流出時期を正確に想定できる。 - 売掛金台帳
取引先ごとの未回収金額や回収予定日などを管理する書類。入金遅延が起きそうな取引先を早期に発見し、資金繰りを事前に調整できる。 - 買掛金台帳
取引先ごとの未払い金額や支払い条件を管理する書類。支払期日を明確にすることで、未来のキャッシュアウトを見越した計画を立案できるようになる。
元帳を正確に記録・更新しておけば、資金繰り表作成の際にスムーズに現金の入出金を把握でき、経営判断の精度を高められます。
必要な資料5:経費元帳・税金や社会保険料の納入告知書(納付書)
資金繰り表を作成する際は、経費元帳を参照して過去の経費支出を洗い出し、毎月どれだけの経費が発生するのかを正確に見積もる必要があります。税金や社会保険料に関しては、納付書などの現物を確認し、正確な支払い時期と納付額を反映することが大切です。
- 経費元帳
過去の経費支払内容を詳細に確認できるので、毎月・毎年の支出パターンを把握できる。特に固定費(家賃・リース料・光熱費など)の見積もりに役立つ。 - 税金や社会保険料の納付書
納付時期や金額を誤って記載すると、資金繰り全体の計画にズレが生じる。実際の納付書をもとに、確定した納付額と支払日を盛り込むのがポイント。
なお、資金繰り表の項目に挙げる支払いは、金額の大きなもの(主要なもの)を中心に列挙すれば問題ありません。小さい支出は「その他」でまとめるなど、管理しやすいフォーマットを心がけましょう。
必要な資料6:借入金返済予定表
資金繰り表の財務支出を正しく記入するためには、借入金返済予定表が必須です。金融機関から融資を受けると、返済金額や返済スケジュールが記載された返済予定表が必ず手交されます。短期・長期を問わず、実際に支払う金額を正確に資金繰り表へ反映させることで、キャッシュフローを適切に把握できるようになります。
なお、返済予定表には「返済金額」や「返済スケジュール」を正確に記載しましょう。金融機関は、資金繰り表と決算書の借入金明細の内容を照合し、整合性を確認します。返済金額に誤りがあると信用を損ない、融資条件が悪化する可能性もあります。
ちなみに、「他行借入金一覧表」という書類を金融機関側で作成し、借入残高や融資シェアを調査しているケースも多々あります。期中での一括返済や追加融資などもすぐ把握されるので、常に正確に記入するよう心がけましょう。
必要な資料7:事業計画書
設備投資を行う際には、事業計画書の作成が不可欠です。資金繰り表と事業計画書の数値が大きく食い違っていると、融資を受ける金融機関から「計画に無理があるのでは?」と判断されかねません。したがって、経常収支や経常外収支の部分を事業計画書と整合性をとりながら反映することが重要です。
実際には、多くの中小企業が事業計画書を作成していないのが現状です。しかし、設備資金を金融機関から借り入れる際には必ず求められるため、融資を申込む段階で作成するケースがほとんどかもしれません。金融機関は、提出された事業計画書がどれほど緻密に作成されているかを慎重にチェックするため、融資が必要になる前に綿密な計画を練っておくと良いでしょう。
計画の信憑性と資金繰り表の内容が整合しているかどうかが、融資判断に大きく影響します。
資金繰り表を作成する際の注意点
資金繰り表は、正確かつ継続的に作成してこそ効果を発揮します。「数字を良く見せるための誤った記載」や「古いデータ」を放置すると、経営判断を狂わせるリスクが高まります。
資金繰り表作成時に押さえておきたいポイントや、陥りがちな注意点も見ていきましょう。
虚偽申告をしない
資金繰り表を作成するうえで、見通しの立たない売上を予測として計上してはいけません。経常収入を実態以上に大きく見せると、正確な翌月繰越金を把握できなくなり、実際の資金不足リスクを見逃す可能性があります。経費を過小計上することも同じで、実際の支出額より少なく記載すれば、翌月以降のキャッシュアウトのタイミングを誤る恐れが大きいです。
予定と実績に乖離が生じるのはある程度仕方のないことですが、「なぜ乖離が発生したのか?」などの原因を追究し、改善策を講じることが大切です。安易に数字を良く見せるのではなく、現実を反映させることで、次回以降の予測精度を高められます。
ちなみに、資金繰り表は基本的に内部資料です。融資を申込む際に金融機関に提出する可能性はありますが、株主や債権者に開示する必要はありません。あくまでも自社の実態把握を目的とし、正直な数字を記載する姿勢が重要です。
参照するデータの正確性に注意する
資金繰り表を作成する際は、決算書・試算表・元帳・借入金返済予定表など、あらゆる会計資料をもとに数字を積み上げていきます。使用するデータが誤っていれば、資金繰り表全体の信憑性が一気に低下してしまいます。憶測に頼らず、できる限り最新かつ正確な数値を反映することが重要です。
資金繰り表に限らず、経営に関わる書類は正確性が求められるものです。数値の確認を徹底し、信頼できる資料に基づいた作成を心がけましょう。
定期的に見直す
理想は、入出金が確定した時点で資金繰り表を更新するのがベストですが、実務上それを毎回行うのは難しいでしょう。そのため、最低限でも月末の営業終了時に見直しを行い、入出金データを反映するようにすると、資金繰り表の信憑性を高いレベルで維持できます。
ただ、取引先や業種によって、入出金のタイミングが大きく変動する場合があります。都度更新するのが理想ですが、少なくとも月単位のチェックを確実に実施し、リアルタイムに近い情報を保つよう心がけましょう。
ストレスなく作成できるフォーマットにカスタマイズする
資金繰り表を作成する際は、自社の勘定項目や業態に合わない項目は思い切って削除し、必要な項目を追加して使いやすいフォーマットに仕上げていきましょう。金融機関やインターネット上で提供される雛形をそのまま使用すると、不要な項目や複雑な欄がかえって混乱を招くことがあります。
自社の業務フローに合う形でカスタマイズすれば、記入する担当者の負担も減り、資金繰り表を更新するハードルが下がります。
たとえば、手形回収がない場合は手形に関する項目は不要ですし、買掛金が発生しない場合はその欄を省くなど、必要な項目だけを残しましょう。使いやすい形式にすることで、継続的かつ正確な作成が行いやすくなり、結果的に経営管理全体の質を高めることにもつながります。
資金繰り表のテンプレート
◎資金繰り表テンプレート
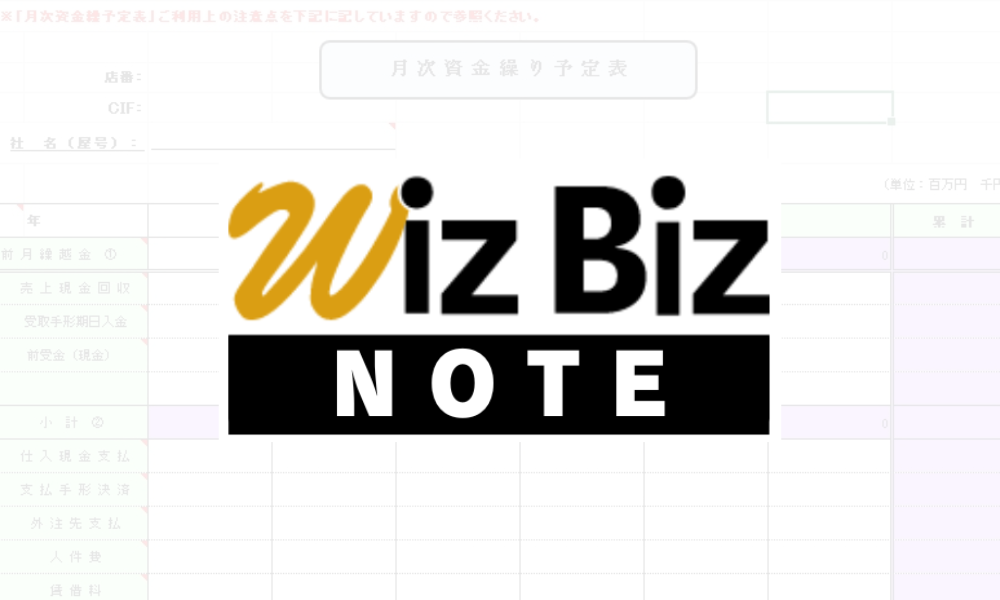
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、資金繰り表のテンプレートをお送りします。
資金繰り表の作り方と融資時のアピールポイント
資金繰り表を上手に作成すれば、金融機関からの評価が高まり、資金調達を有利に進めることができます。
資金繰り表の具体的な記入方法から、融資審査で重視されるポイント、アピールに効果的な見せ方についても見ていきましょう。
経常収入(売掛金)の回収予定はできる限り正確に見積もる
短期資金の融資審査では、資金繰り表の経常収入欄(売掛金回収)がとくに重要視されます。融資金を何に使い、いつ返済できるのかを示すうえで、売掛金の回収スケジュールは欠かせません。
以下のような具体例を想定して、返済原資と回収月のタイミングをしっかり把握しておきましょう。
- 申込額:300万円
- 期間:6カ月
- 資金使途:外注先への先行支払い
- 返済原資:ハウスメーカーからの売掛金回収(住宅購入者の決済代金の一部より)
このケースでは、外注支払い月に融資金を投入すると翌月繰越金が一時的に赤字(不足)になるかもしれません。しかし、売掛金の回収月に合わせて返済額を設定すれば、返済後でも翌月繰越金が黒字に戻るよう計画(作成)できます。
- 資金需要の妥当性
まず、注文書や契約書を確認し、当該資金需要が本当に必要であるかをチェックします。 - 支払条件との整合性
注文書に記載された支払条件と、売掛金の回収予定をすり合わせます。融資を入れるタイミングと回収月が合致していれば、翌月以降の資金不足リスクを低減できます。
資金繰り表に大きな問題がないと判断されれば、銀行員は融資承認を得るための書類(稟議書)作成に着手します。
短期融資を申し込む際は、回収予定を甘く見積もらず、できるだけ客観的根拠に基づく数字を資金繰り表へ落とし込むようにしましょう。
財務収支欄の「借入調達」と「返済」は正確に記載する
資金繰り表の財務収支欄には、融資の実行明細や返済予定表をもとに、借入金額と返済額を漏れなく記載することが必須です。経常収支・経常外収支に大きな変動がない場合でも、財務収支の増減によって翌月繰越金が大きく変動し、経営判断に影響を及ぼします。
返済が続けば、それだけ翌月繰越金は減少します。正確な返済額を入力しておけば、いつごろ長期資金(運転資金や折り返し資金)を依頼すべきか、そのタイミングを把握しやすくなります。 多くの場合、長期資金の申し込み時に資金繰り表の提出は求められませんが、あえて提出することで金融機関への説得力が高まり、安定的な資金調達がしやすくなります。
- 決算内容と他行借入状況との整合性
決算書や試算表、他行からの借入状況(借入金一覧表)と齟齬がないかを重視します。返済実績が良好で、他行分も含めた正確な借入金状況を示せれば、稟議書の承認を得やすくなるでしょう。
設備投資の際は、翌月以降の資金繰りに注意する
融資金で設備投資を行う場合は、毎月の返済額が高額になりやすいため、返済後の資金繰りに問題が生じないか慎重に検討しなければなりません。設備導入計画とあわせて、融資返済後の翌月繰越金や月次の支出入をシミュレーションしておくことが大切です。
具体的には、設備資金を借りると毎月の返済負担が大きくなるため、従来の運転資金に上乗せして計算する必要があります。設備導入のタイミングと売上の増加見込みがずれていると、短期的な資金ショートを引き起こすリスクが高まります。設備投資計画で想定している売上・利益の増加見込みが妥当かどうかを、資金繰り表や決算予測と照らし合わせて検証することが重要です。
- 利益償還が現実的か?
原則として、設備投資は「利益で返済していく」考え方が基本です。短期間で利益が上がらない事業に対しては、金融機関も慎重な姿勢を示す傾向があります。 - 売上増加見込みがあるか?
売上増を前提にした設備投資であっても、5期~10期程度の長期決算予測を提出するよう求められます。あわせて資金繰り表を作成し、設備投資後も返済が確実に可能であることを示すのがポイントです。 - 計画と資金繰りの整合性
設備投資によるコスト負担と、将来的な利益見込みが整合しているか、金融機関は資金繰り表を通じてチェックします。計画の前提条件があいまいだと融資審査は難航します。
設備投資を成功させるためには、返済後のキャッシュフローを十分に考慮し、計画と資金繰りに無理がないかを示すことが欠かせません。金融機関の視点を意識して、実現性の高い資金繰り表と事業計画を用意しましょう。
項目の数値は根拠を示せる範囲内で設定する
資金繰り表の各項目を入力する際は、過度に楽観的な数値を入れず、過去の実績や事業計画などから確実性の高い見込み額を計上しましょう。根拠のない数字を記載すると、いざ実際の入出金がずれた際に資金ショートを招いたり、金融機関から「実現性が低い」と判断されたりするリスクが高まります。
- 短期資金の融資審査の場合
資金不足が予想される月(融資実行月)と返済原資が入る月(返済月)のみを主眼に置いて審査し、期中の細かな収支までは深く追及しないことが多いです。ただし、注文書などで売上や入金の確実性を確認するため、根拠のない売上予測は通用しません。 - 長期資金の場合
返済能力を判断するために、期中全体の収支も含めた長期的な計画をチェックします。極端に売上を上振れしたり、経費を過小に見積もったりすると、計画の信憑性が疑われ、融資審査が厳しくなる可能性があります。
根拠を示せる数値で作成した資金繰り表は、金融機関に対しても説得力が高く、スムーズな資金調達や融資条件の有利化につながりやすくなります。
資金繰り表の作り方まとめ
資金繰り表は、現金の流れを「見える化」して資金不足を未然に防ぐための書類です。作成時は、決算書や試算表をベースに、出納帳や借入金返済予定表などで数値の信頼性を高めましょう。
売上・支出は根拠のある計画に基づき、翌月繰越金が赤字にならないよう事前対策を講じることが重要です。
短期融資では融資実行月と返済月が、長期融資では設備投資計画と利益償還の見込みが審査のポイントとなります。
資金繰り表は、基本的には内部資料です。ありのままを正直に記載し、定期的な更新で黒字倒産リスクを回避しながら、安定経営を実現しましょう。
◎資金繰り表テンプレート
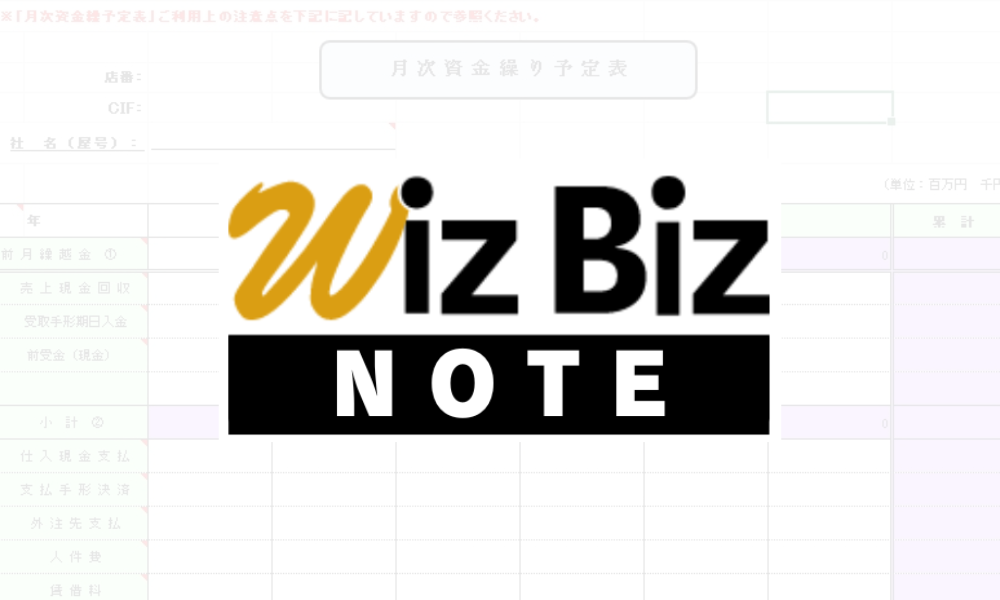
以下のフォームに入力いただいたメールアドレス宛に、資金繰り表のテンプレートをお送りします。